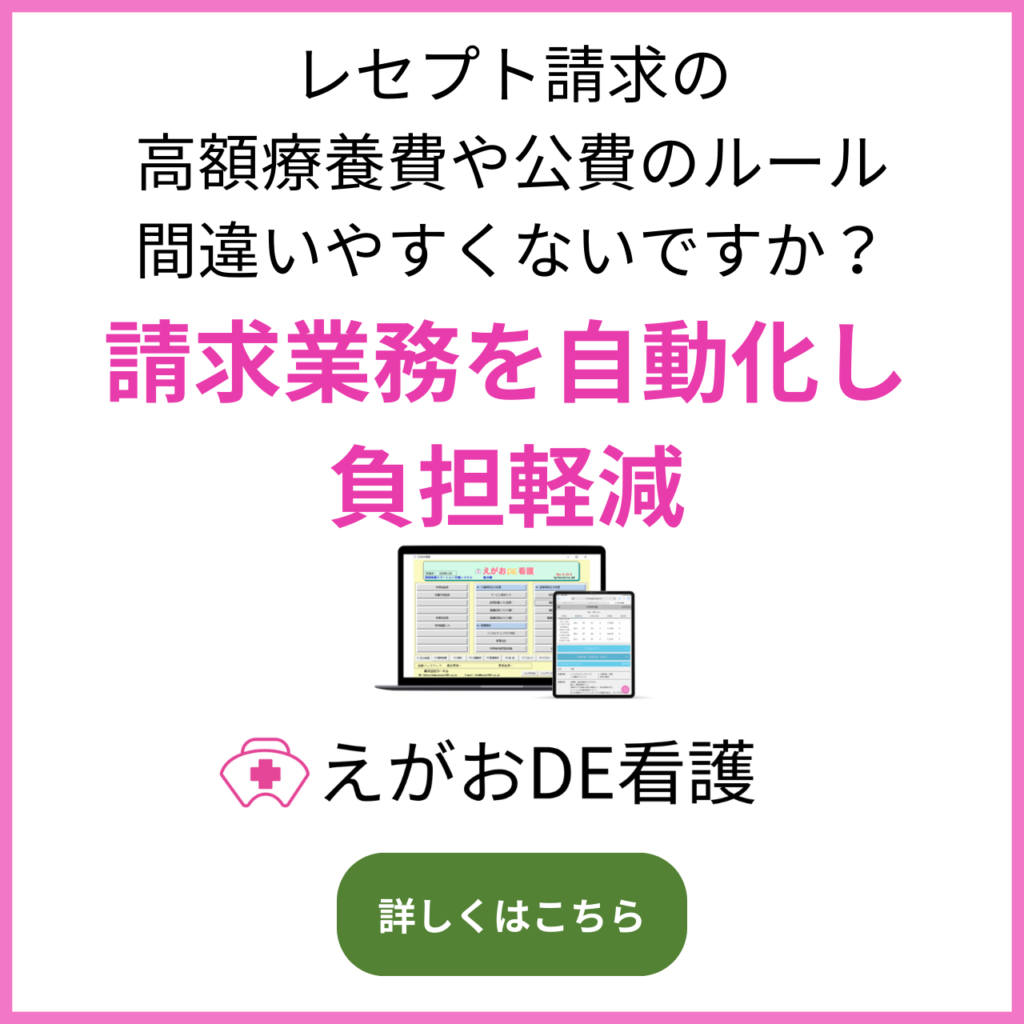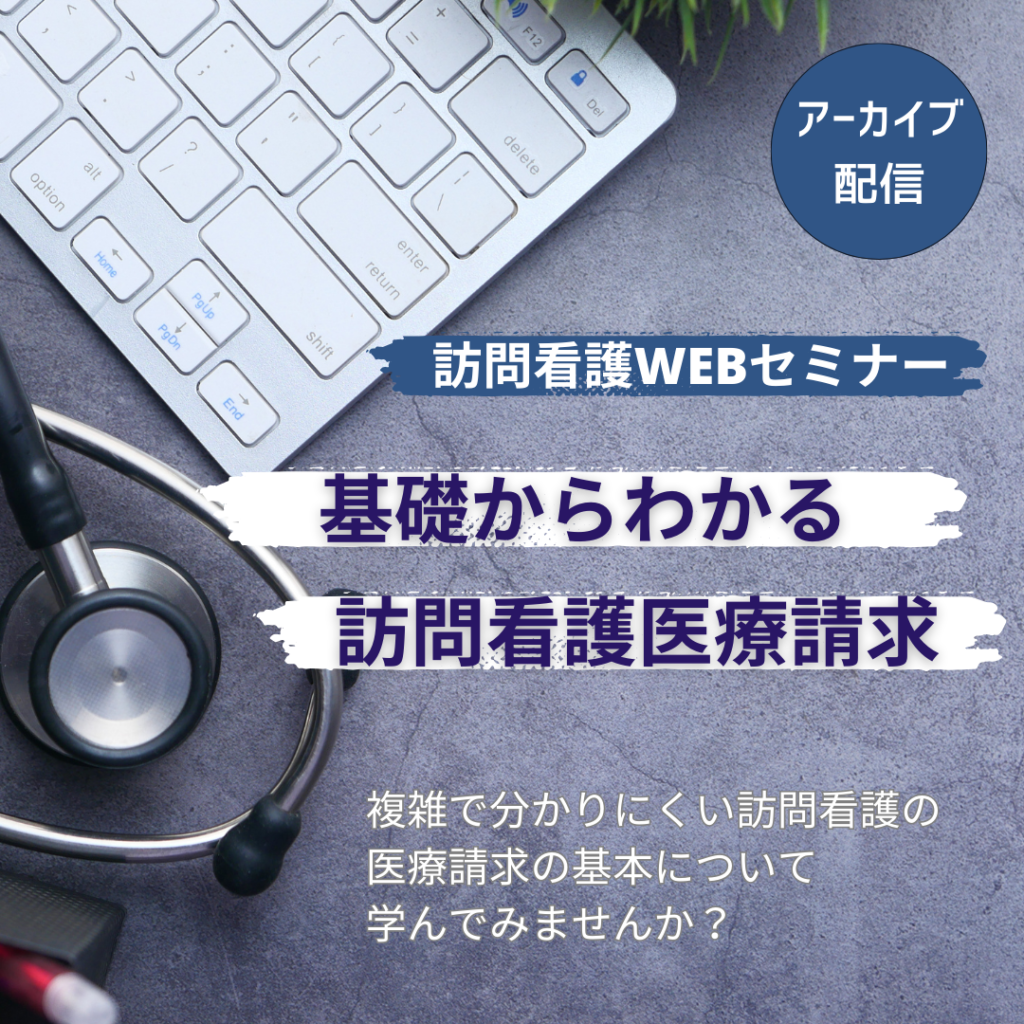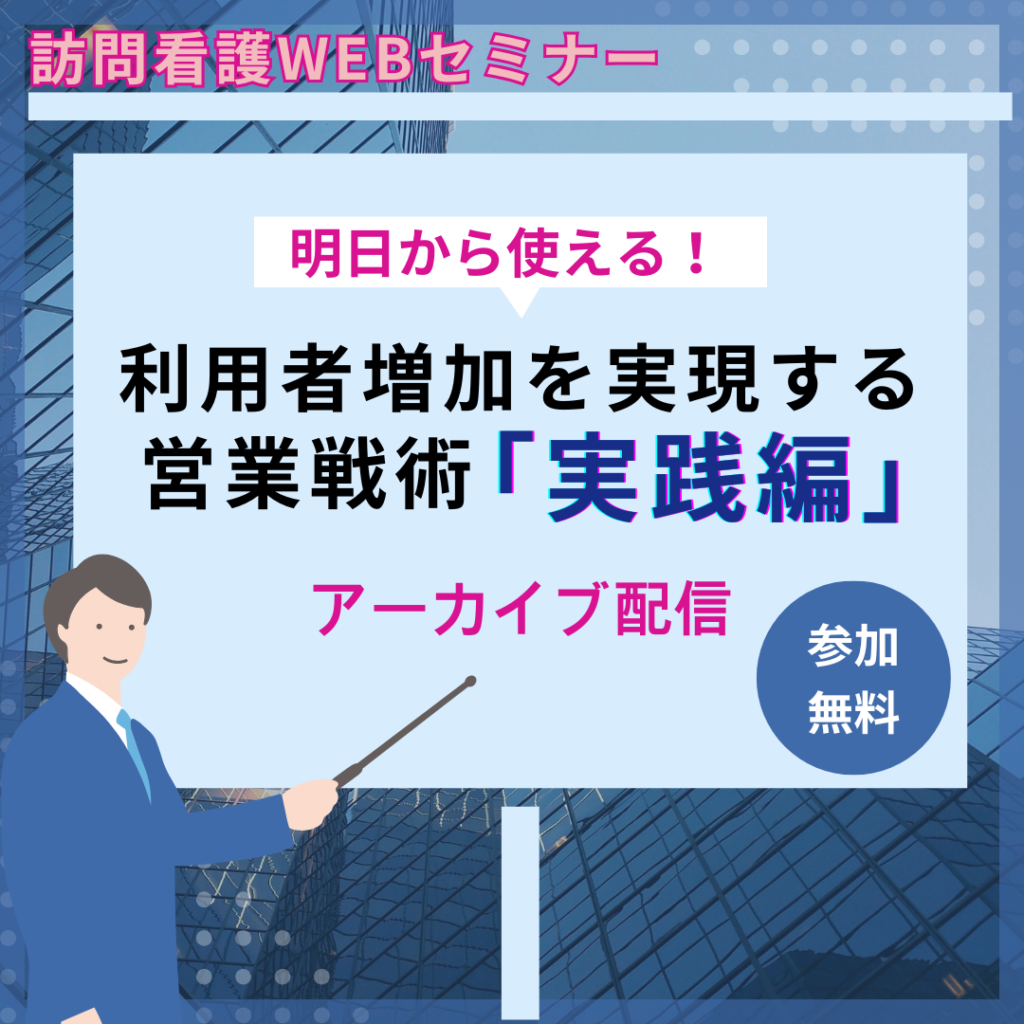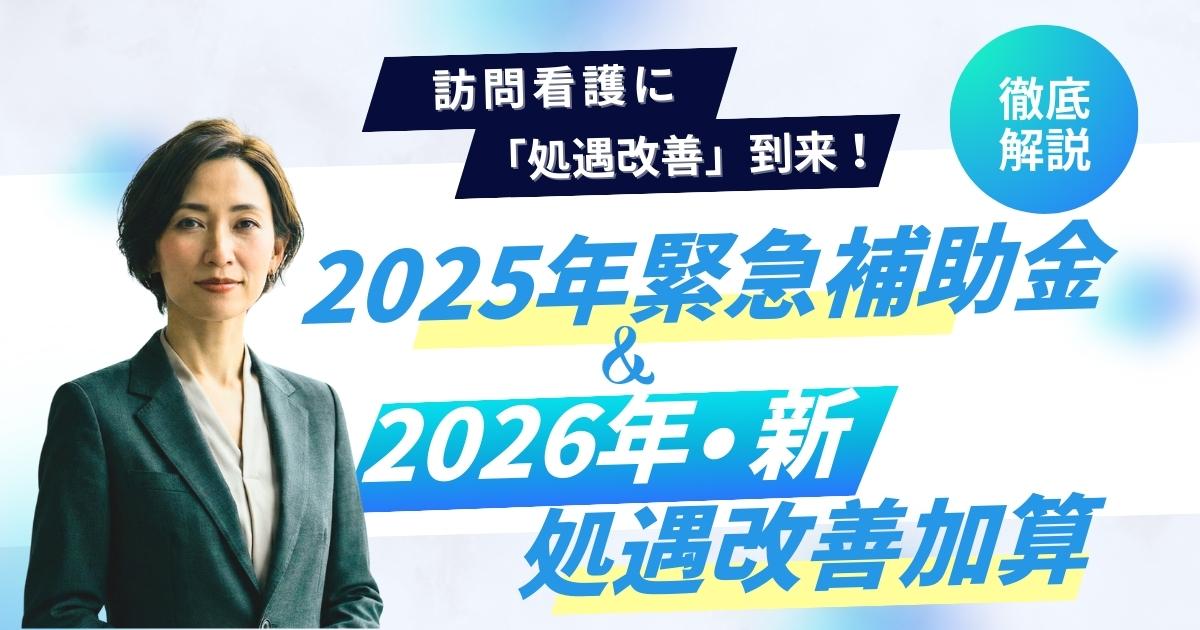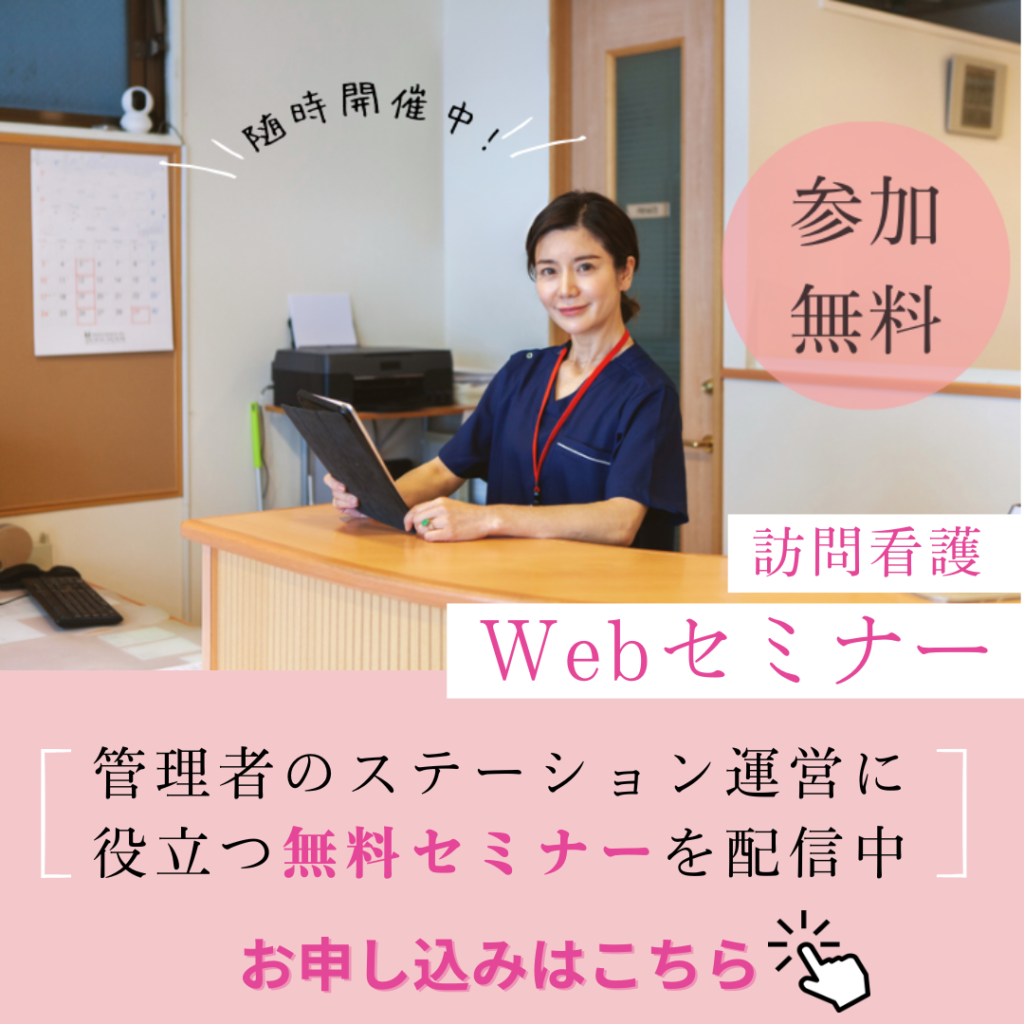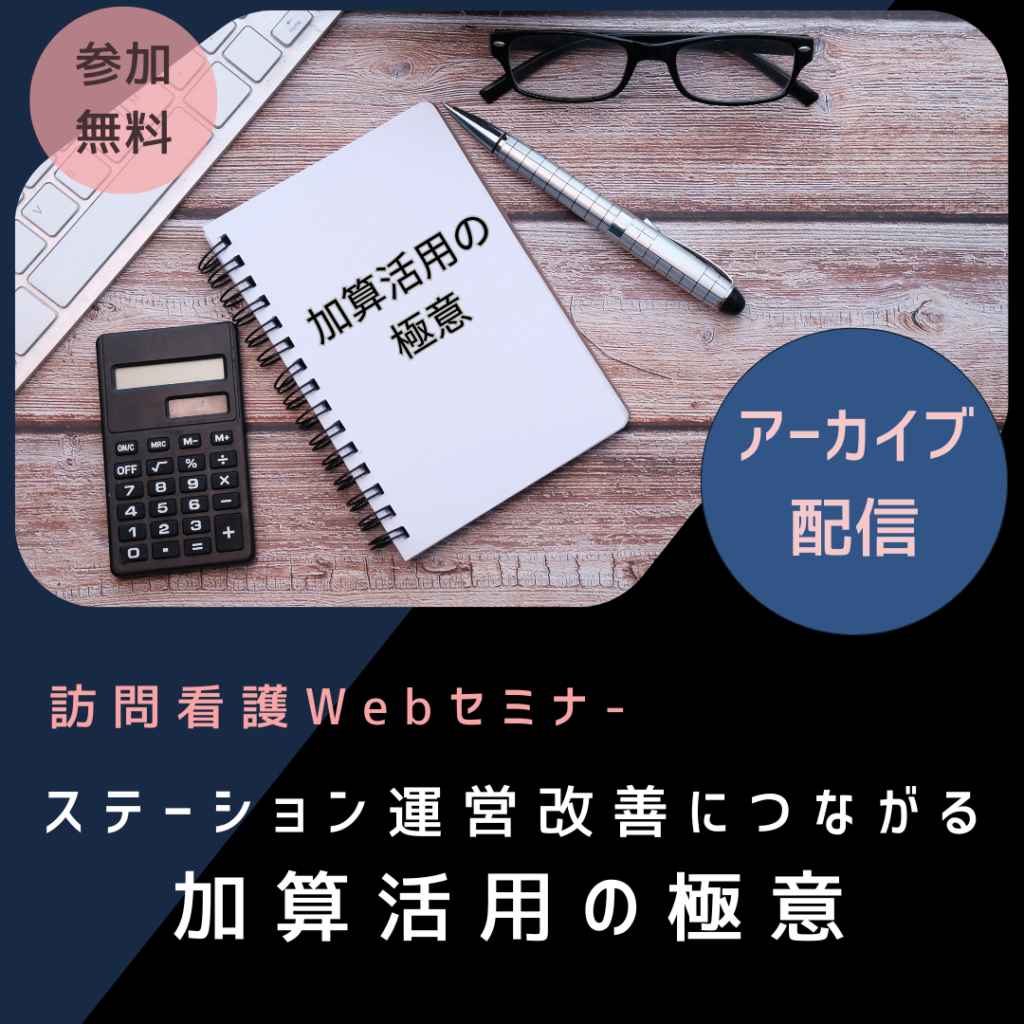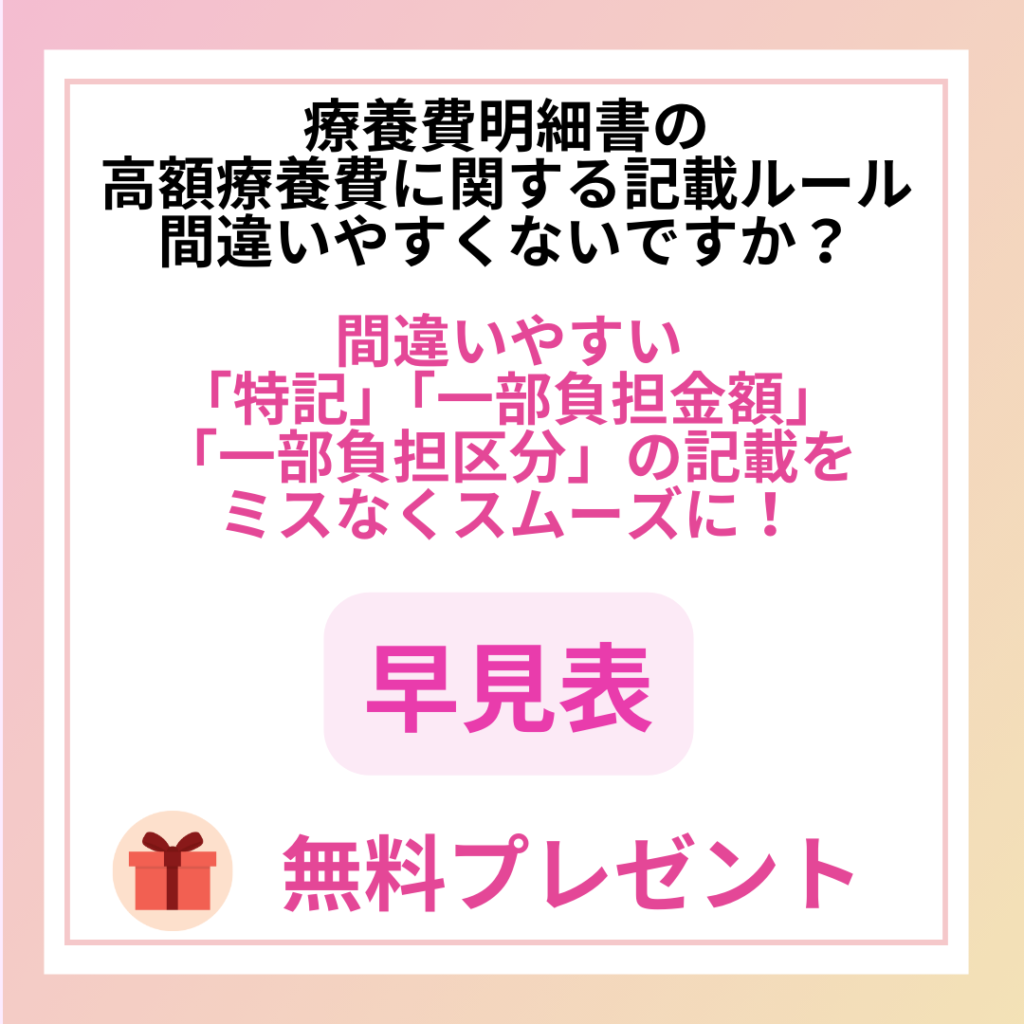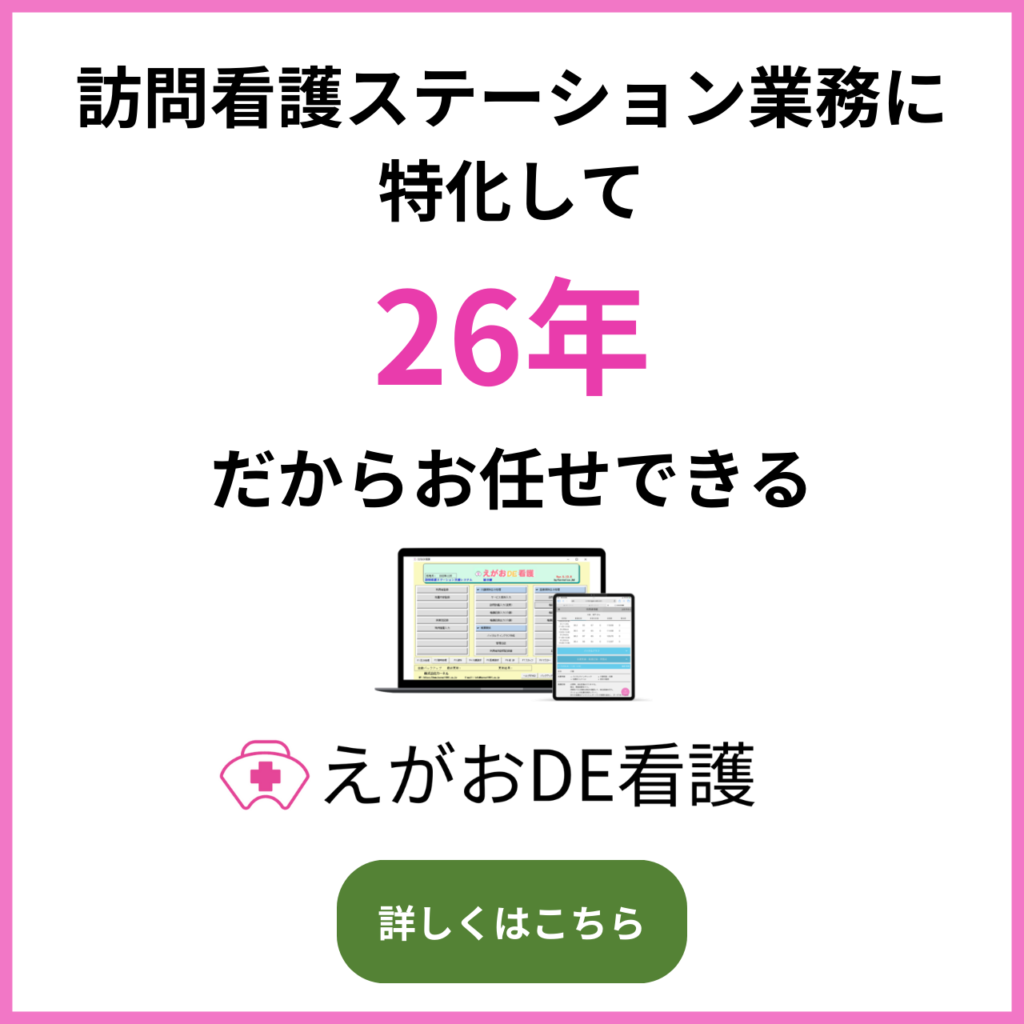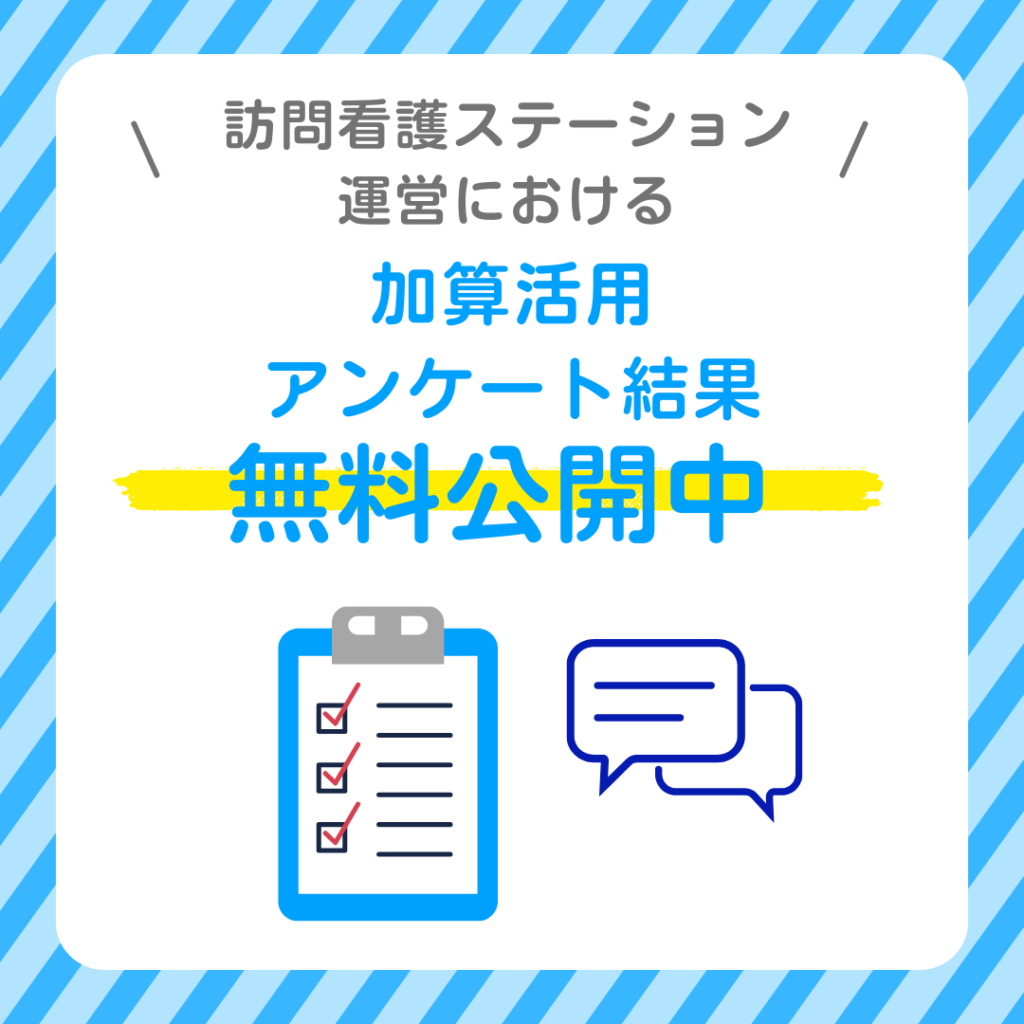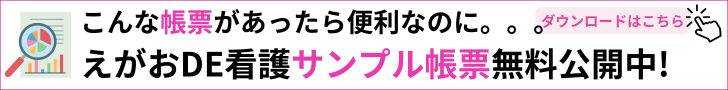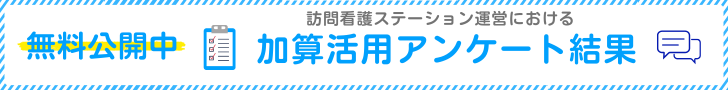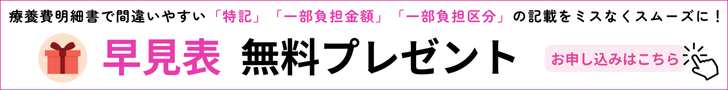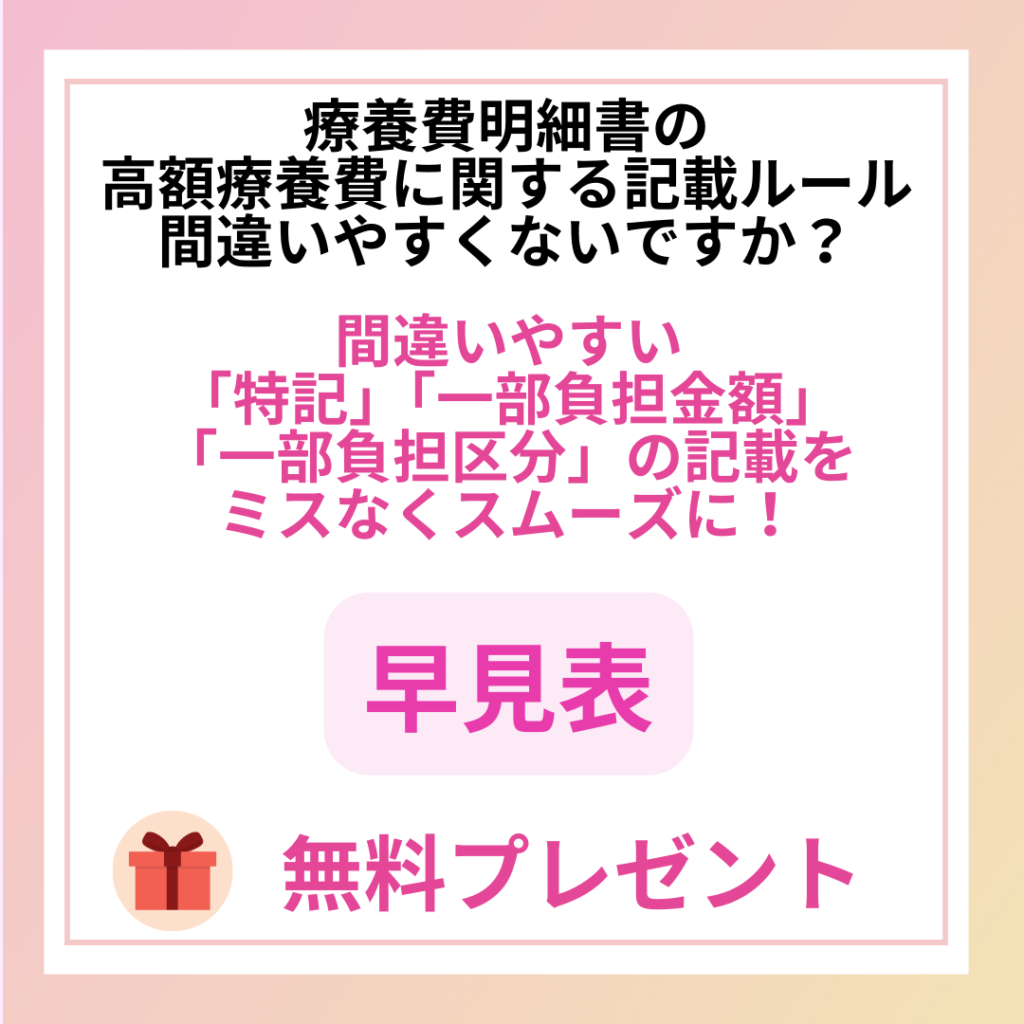そもそも高額療養費制度と「多数回該当」の基本

高額療養費制度のしくみと「多数回該当」の条件、そしてオンライン資格確認でなぜそれが分かるのか、という3つの基本を解説します。
高額療養費制度のしくみ
高額療養費制度とは、ひと月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
訪問看護では、利用者が「限度額適用認定証」を提示することで、ステーションでの支払いを自己負担上限額までにとどめる「現物給付」が基本となります。
「多数回該当」が適用される条件(直近12ヵ月で3回以上)
「多数回該当」は、継続的に医療費がかかる方の負担をさらに軽減する仕組みです。直近12ヵ月で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から自己負担上限額が引き下げられます。
- カウント期間: 診療月を含めた過去12ヵ月間
- 適用条件: 高額療養費の支給が3回以上
- 負担軽減: 4回目以降の自己負担上限額が下がる
この条件に当てはまる利用者は、通常の限度額よりも少ない負担でサービスを利用できます。
オンライン資格確認でなぜ「多数回該当」がわかる?
オンライン資格確認では、利用者の保険証情報をもとに、審査支払機関が持つ過去のレセプト(診療報酬明細書)情報を自動で照会します。
これにより、過去12ヵ月間の高額療養費の支給回数も把握できるため、「多数回該当」かどうかが端末画面に表示されます。
▼医療保険を使った訪問看護の基本や、介護保険との違いを復習したい方はこちら
【保存版】訪問看護で医療保険が使える条件は?介護保険との違いを徹底解説!
【実践編】高額療養費「多数回該当」の自己負担限度額の計算方法

オンライン資格確認の導入により、管理者の作業は「複雑な計算」から「システムが示す情報の確認と判断」へと変化しています。
以下の3つのステップで、請求額を判断することができます。
Step1: 利用者の医療保険「所得区分」を確認する
まず、オンライン資格確認の画面や「限度額適用認定証」で、利用者の正確な所得区分を把握します。自己負担限度額は所得によって決まるため、この確認が基礎となります。
Step2: 多数回該当の「自己負担限度額」を早見表でチェック
次に、下の早見表で対応する「多数回該当」の自己負担限度額を確認します。年齢によって表が異なりますのでご注意ください。
【70歳未満の方の自己負担限度額(月額)】
| 所得区分 | 通常の限度額 | 多数回該当の限度額 |
| ア (標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
|---|---|---|
| イ (標準報酬月額53万~79万円) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ (標準報酬月額28万~50万円) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ (標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 | 44,400円 |
| オ (住民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
【70歳以上の方の自己負担限度額(月額・世帯単位)】
| 所得区分 | 通常の限度額(世帯ごと) | 多数回該当の限度額 |
| 現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 一般 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税等 Ⅱ・Ⅰ | 24,600円 / 15,000円 | 24,600円 / 15,000円 |
⚠️政府は2026年8月以降に改めて見直し(段階的な上限引き上げ・区分細分化など)の実施を検討中で、2026年秋までに詳細方針を決める予定です。
Step3: 【ケース別】訪問看護の自己負担額を判断してみよう
実務では、オンライン資格確認で「限度額まであといくら残っているか」を確認し、自ステーションの請求額を判断します。
ケース1:月途中で限度額に達するパターン
- 前提: 68歳、所得区分「ウ」、自己負担3割。多数回該当の限度額は44,400円。当月の自ステーションの自己負担額は48,000円。
- 判断: オンライン資格確認で「他院支払額30,000円」と表示された場合、残りの上限額は14,400円(44,400円 – 30,000円)です。
- 結論: 自ステーションの請求額(48,000円)は残額を超えているため、請求は14,400円となります。
ケース2:公費(福祉医療)が絡む場合
- 前提: 78歳、所得区分「一般」、福祉医療(上限500円/月)も利用。
- 判断: まずは医療保険のルールで考え、オンライン資格確認で確認した限度額までの残額を請求します。
- 結論: レセプト上の請求は医療保険のルールで行いますが、利用者への請求書では公費適用後の500円とします。
ケース3:月の途中で保険が変わるパターン
- 前提: 月の途中で75歳になった利用者(所得区分「一般」)。
- 判断: この月は特例で、誕生日を境に限度額もそれぞれ半額になります。多数回該当限度額44,400円の半額、22,200円が各保険での上限です。
- 結論: 請求は、誕生日前の保険に上限22,200円、誕生日後の保険に上限22,200円までとなります。
ケース4:難病(公費54)利用者
- 前提: 70歳未満、所得区分「ウ」、指定難病(上限10,000円/月)の利用者。
- 判断: 「高額療養費の限度額(44,400円)」と「難病の限度額(10,000円)」を比べ、利用者はいずれか低い方の金額を支払います。
- 結論: このケースでの自己負担上限は10,000円です。
高額療養費「多数回該当」のレセプト記入方法と返戻防止のポイント
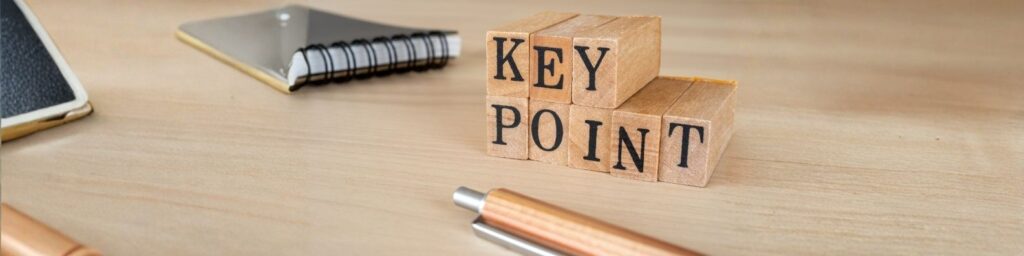
計算した自己負担額を正確にレセプトへ反映させることが、返戻を防ぐ鍵となります。
ここでは、療養費明細書への記入方法と、ミスをなくすための最終チェックリストを具体的に解説します。
訪問看護療養費明細書の「一部負担金額」欄への記入方法
算定した最終的な自己負担額は、訪問看護療養費明細書の「一部負担金額」欄に記入します。
訪問看護では、利用者の限度額情報に基づき、窓口負担を上限額までにとどめる「現物給付」が基本です。そのため、このレセプトへの正しい記入が、制度を適用するための重要な手続きとなります。
摘要欄に「高額療養費(多数回該当)」と記載すると、より丁寧です。
返戻を防ぐための最終チェックリスト
レセプト提出前に、以下の項目を確認しましょう。
□ 所得区分は正しいか?
オンライン資格確認などで確認した、最新の所得区分に基づいているか。
□ 限度額は正しいか?
70歳未満・70歳以上など、利用者の年齢に合った正しい限度額を参照しているか。
□ 他院利用分は考慮したか?
オンライン資格確認で表示された「他院での利用額」を差し引いた、上限額の範囲内で請求しているか。
□ 公費の計算順序は正しいか?
福祉医療や難病の公費が絡む場合、必ず「①医療保険(高額療養費)」を先に計算し、その後に「②公費」を適用しているか。
このリストで最終確認をする習慣をつけることで、請求業務のミスを減らすことができます。
▼多数回該当以外のレセプト業務全般のミスを減らし、返戻をなくしたい方はこちら
【実務者必見】訪問看護レセプト業務の基本と対策|効率化と請求ミスゼロへ
【このまま使える】高額療養費「多数回該当」の利用者への説明方法

請求額が変わる際は、利用者様との信頼関係を保つため、丁寧な説明が必要です。お金に関する不安を招かないよう、「国の制度で負担が軽くなった」という事実を、管理者側から積極的に伝えることが大切です。
ここでは、そのまま使える説明テンプレートと文例を紹介します。
▼ 口頭で説明する場合のテンプレート
「〇〇さん、今月のご請求額が先月よりお安くなっていますのでご説明します。これは『高額療養費制度』という国の制度が適用されたためです。〇〇さんはこの制度の対象となる月が続きましたので、『多数回該当』という、さらに負担が軽くなる仕組みの対象となりました。その結果、今月の自己負担の上限額は〇〇円となり、ご請求額も〇〇円となっております。ご不明な点はございませんか?」
▼ 請求書に添える場合の文例
- (シンプル版)
今月は高額療養費制度の「多数回該当」が適用されたため、自己負担上限額が変更となっております。 - (丁寧版)
【自己負担額についてのお知らせ】
今月は、高額療養費制度における「多数回該当」の適用により、自己負担上限額が変更となっております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
複雑な高額療養費「多数回該当」の計算・請求はソフトで効率化

ここまで、多数回該当の複雑な計算方法や請求時の注意点を解説してきました。しかし、多忙な管理者の方が、これらの作業を毎月、ミスなく手作業で行うのは負担が大きいのも事実です。
ここでは、その負担を軽減する方法を紹介します。
手計算による返戻リスクと管理者の負担
高額療養費の計算は、所得区分や公費の優先順位など、間違いがあれば返戻につながります。返戻が発生すると、入金が遅れるだけでなく、原因の調査や再請求といった追加の事務作業が必要になります。
スタッフの教育や利用者様のケア向上など、本来注力すべき業務に時間を使いたいとお考えの管理者の方も多いのではないでしょうか。
「えがおDE看護」なら高額療養費も公費も自動計算
訪問看護ソフト「えがおDE看護」は、こうした請求業務の負担軽減に役立ちます。
多数回該当や所得区分を自動で判別。福祉医療や難病といった公費の優先順位も考慮し、レセプトの自己負担額を自動で計算・入力します。
複雑な計算ルールを毎回確認する手間が減り、返戻リスクも軽減できます。請求業務の負担を減らし、管理者として本来注力すべき業務により多くの時間を使う。ソフトの活用は、そのための有効な選択肢の一つです。
▼訪問看護ソフトの基本機能から知りたい方はこちら
【経営管理をサポート】訪問看護ソフトとは?|運営状況の可視化から業務効率化まで徹底解説
まとめ:高額療養費「多数回該当」を理解し、利用者の負担軽減と健全な経営へ

今回は、オンライン資格確認で「多数回該当」と表示された際の対応方法について、計算からレセプト記入、利用者への説明まで解説しました。
オンライン資格確認の導入により、管理者の業務は複雑な合算計算から「確認と判断」へと変化しています。この記事で紹介したステップを活用することで、請求額の計算をより正確に行うことができます。
多数回該当は、適切に運用することで利用者の負担を軽減し、ステーションへの信頼にもつながる制度です。この記事が、日々の請求業務の一助となれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
【参考・引用】
本記事は、以下の公的機関が公開している情報と、訪問看護の実務経験に基づき執筆しています。