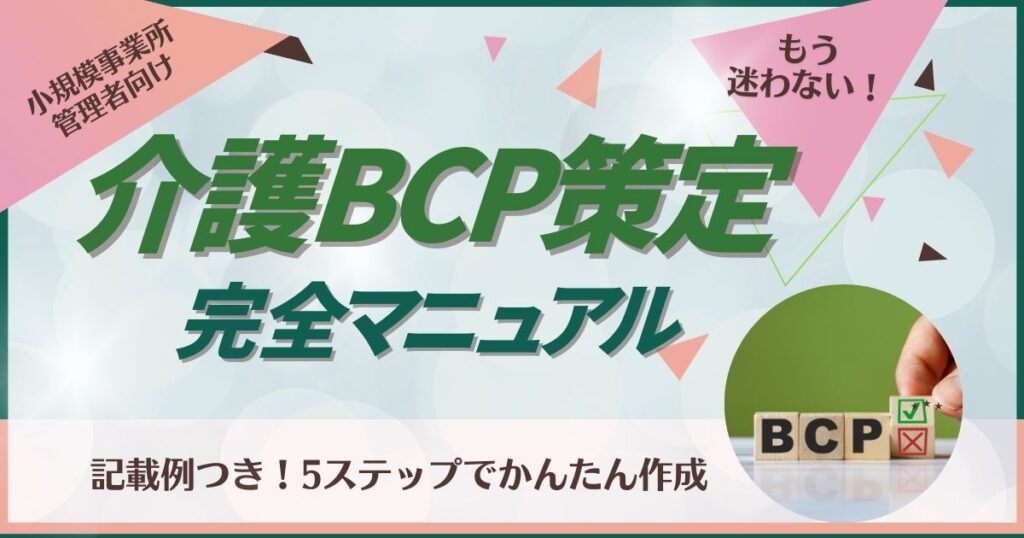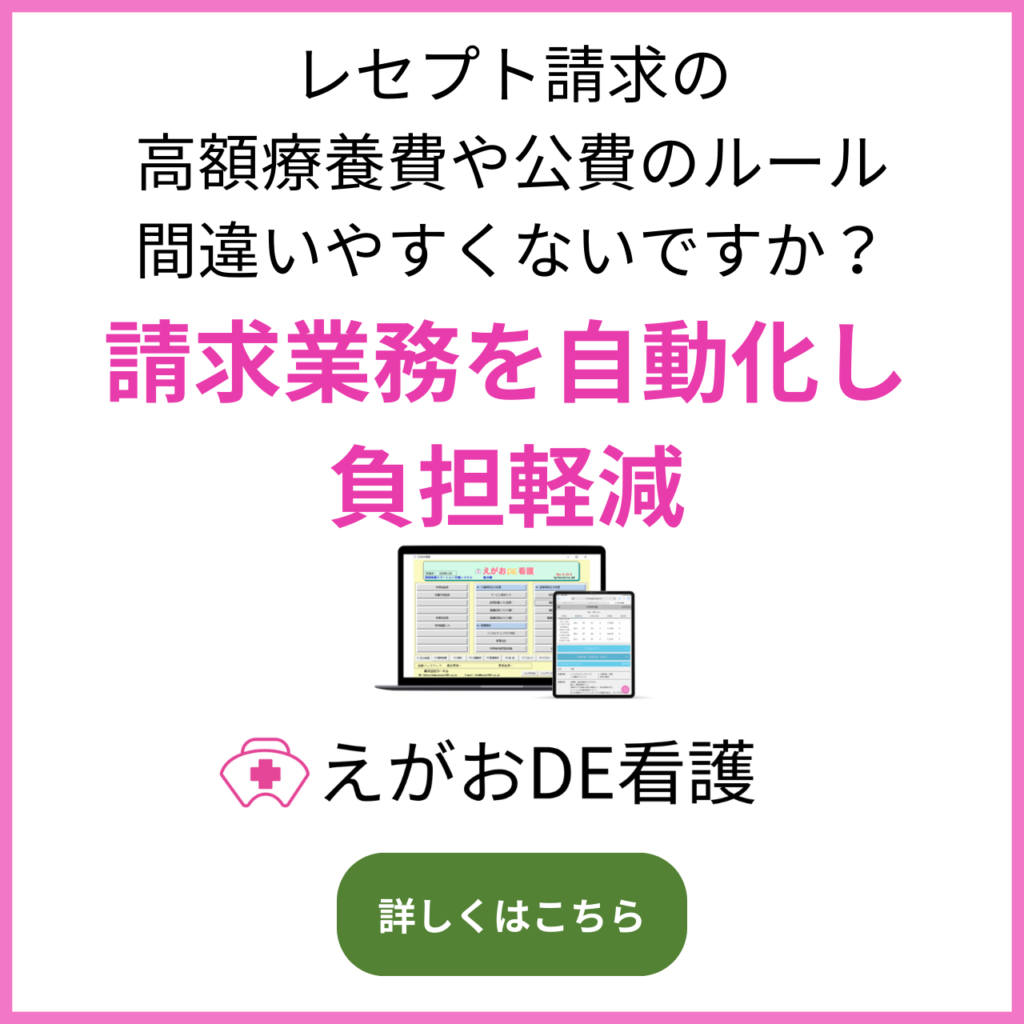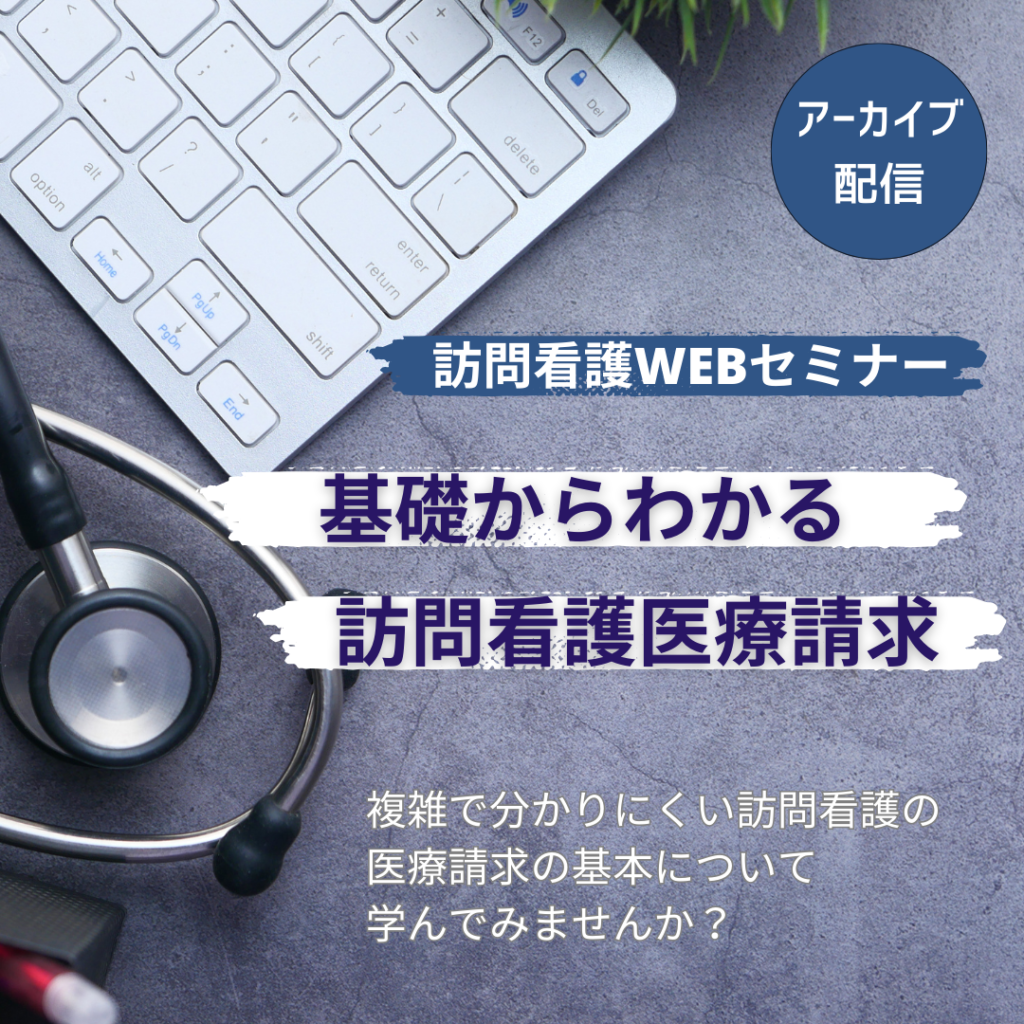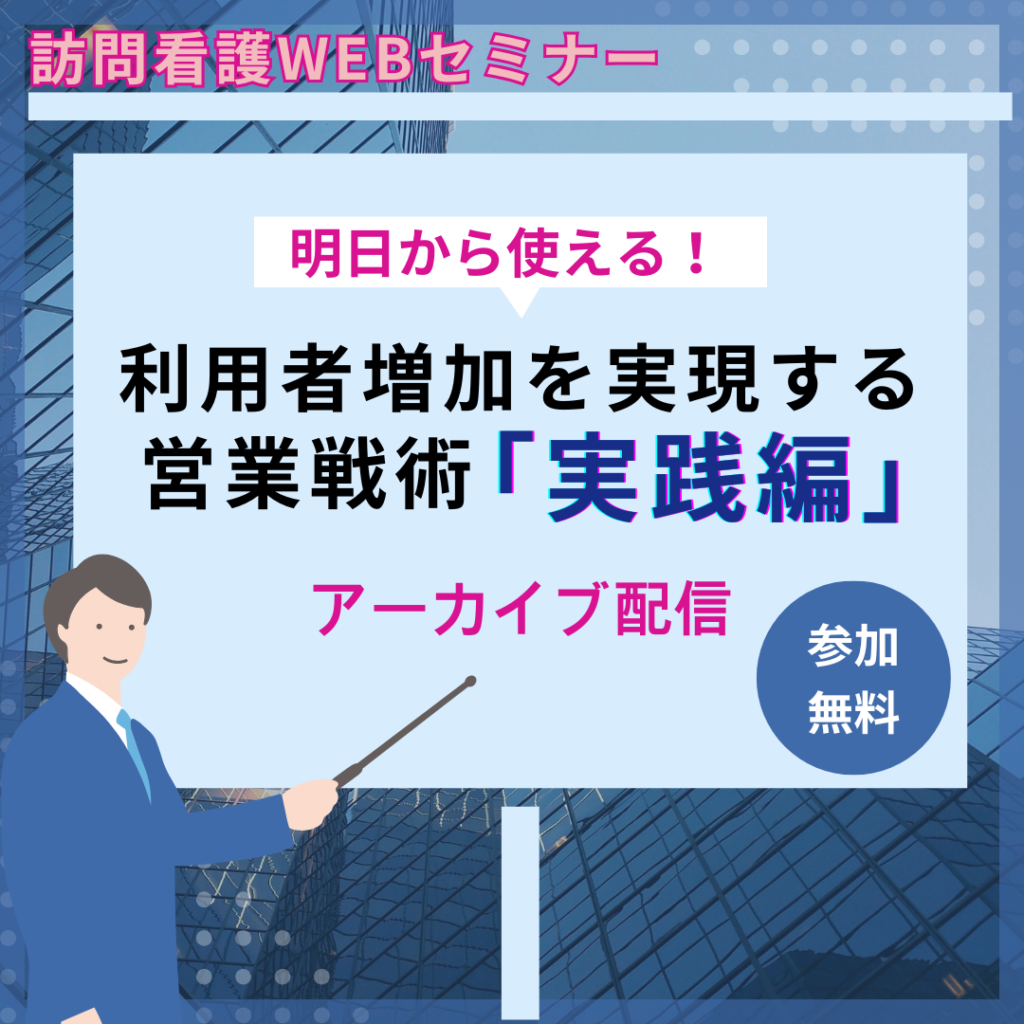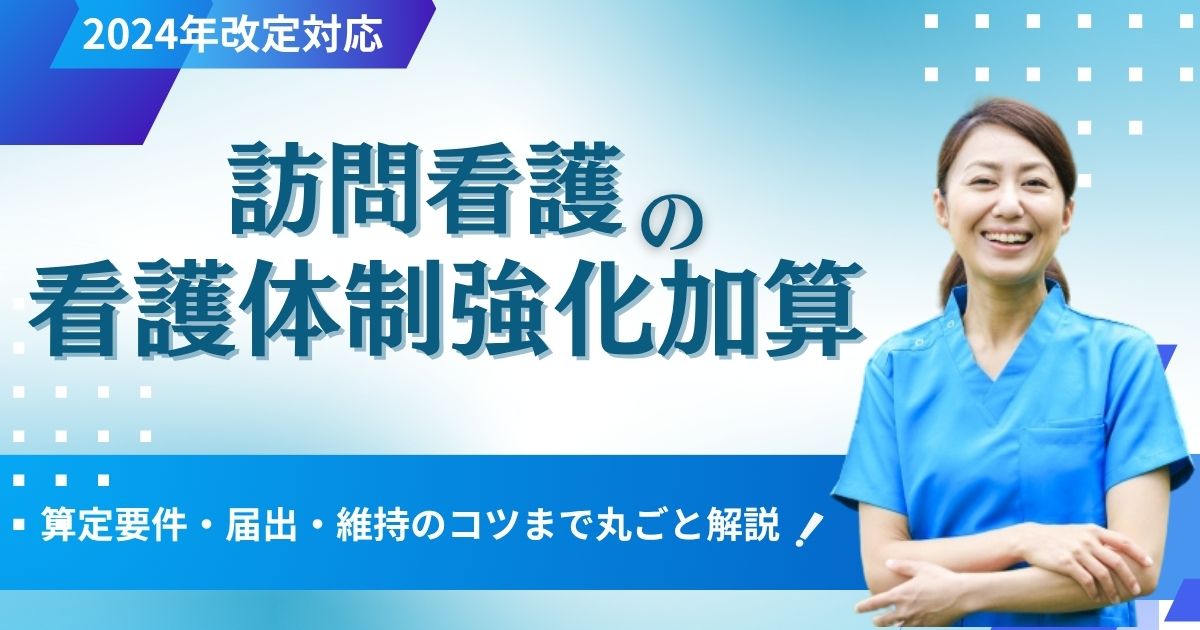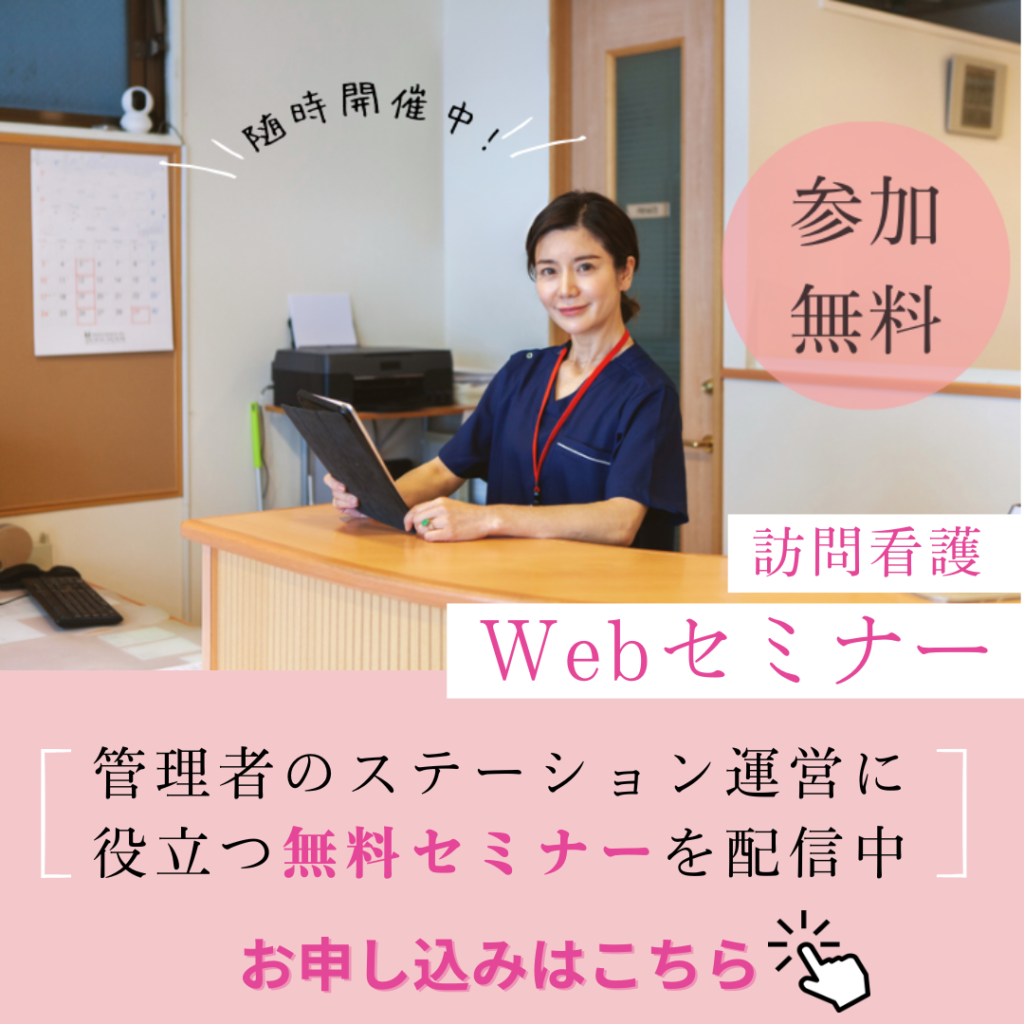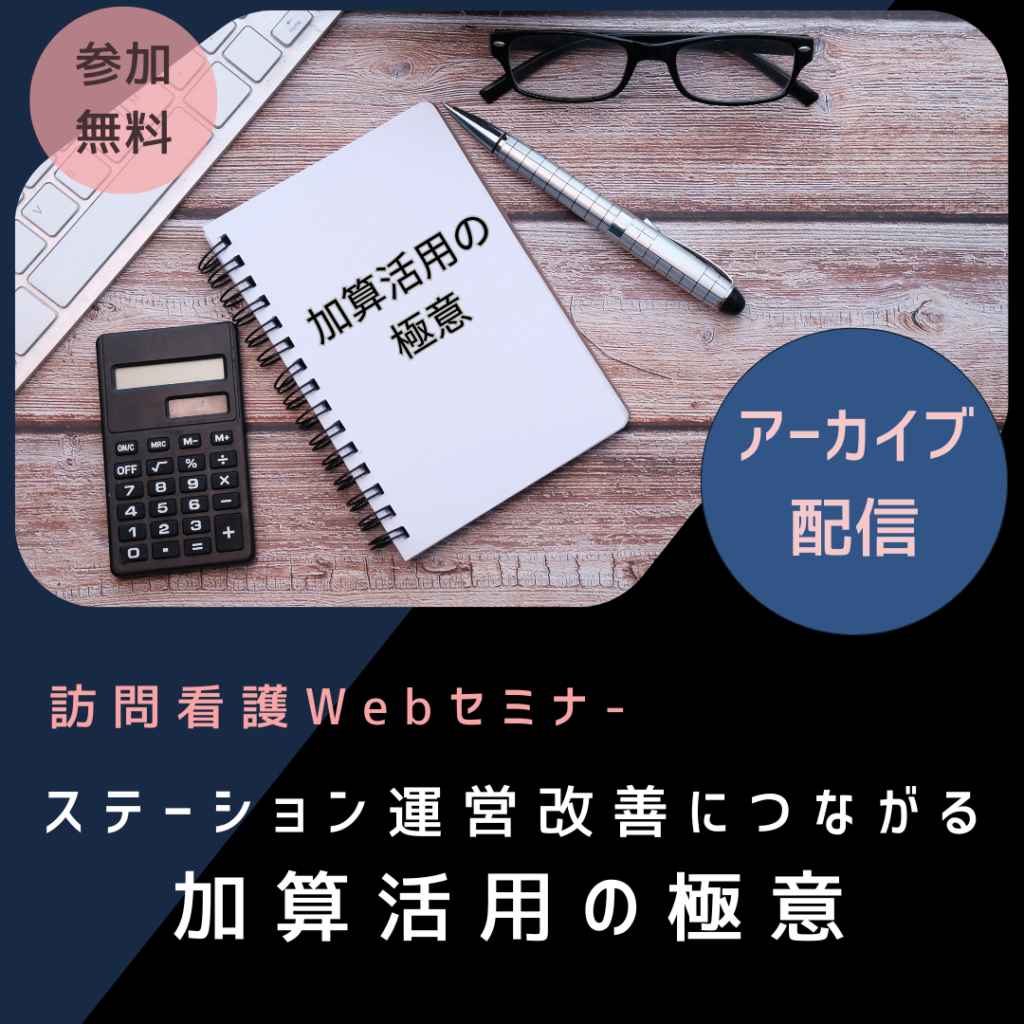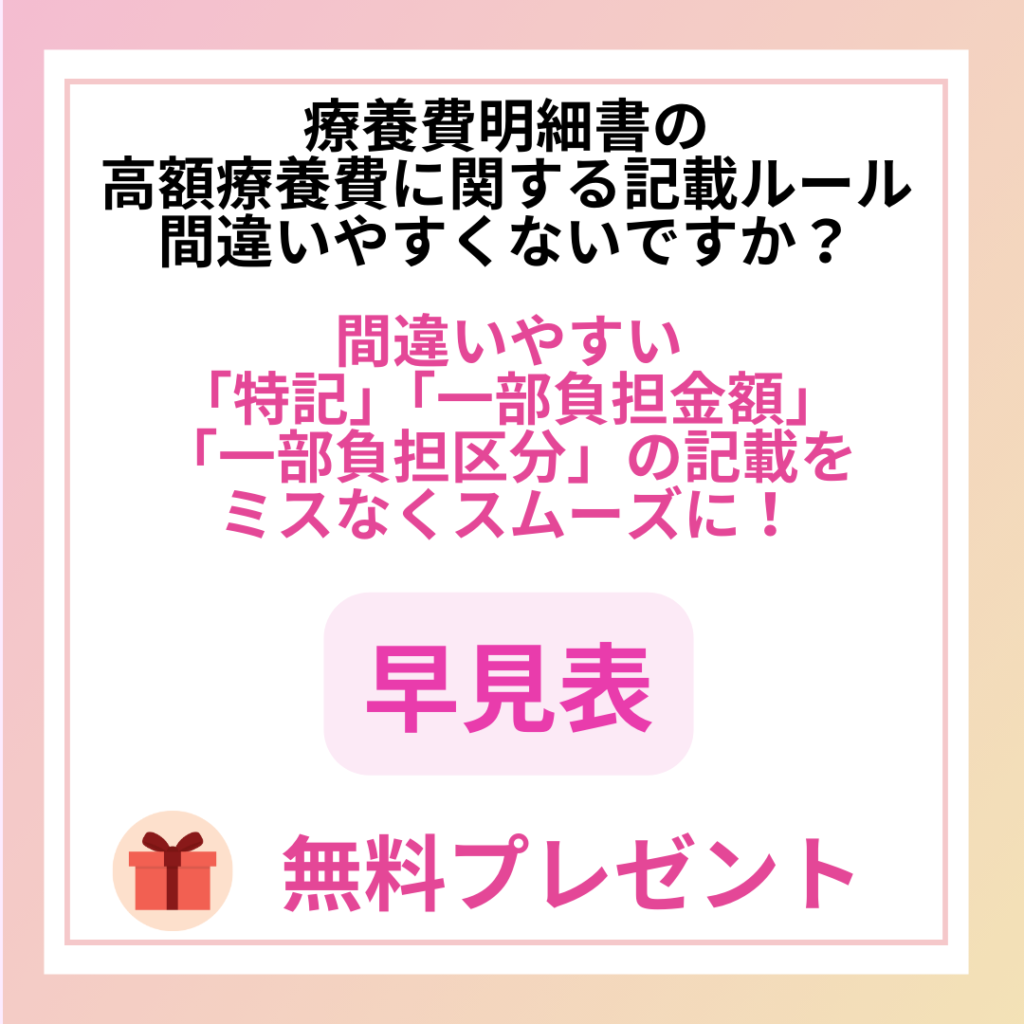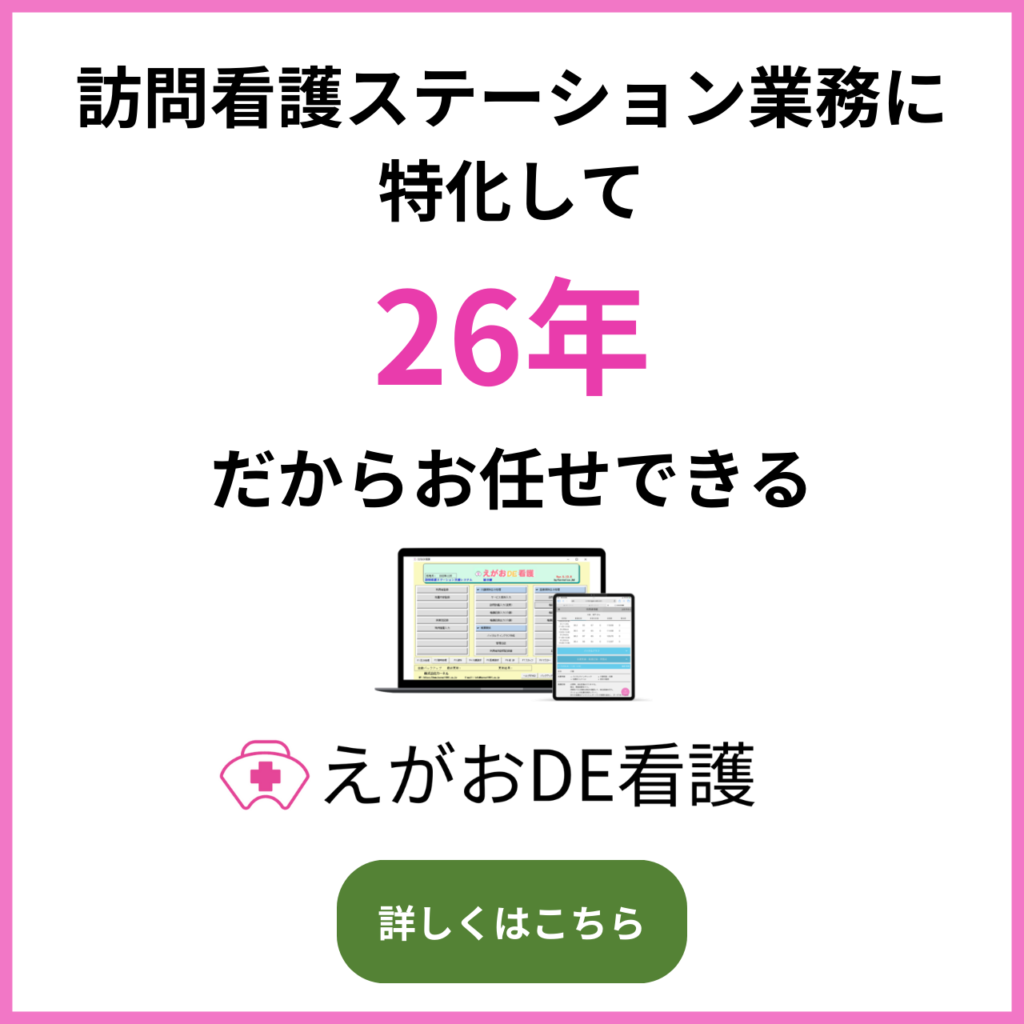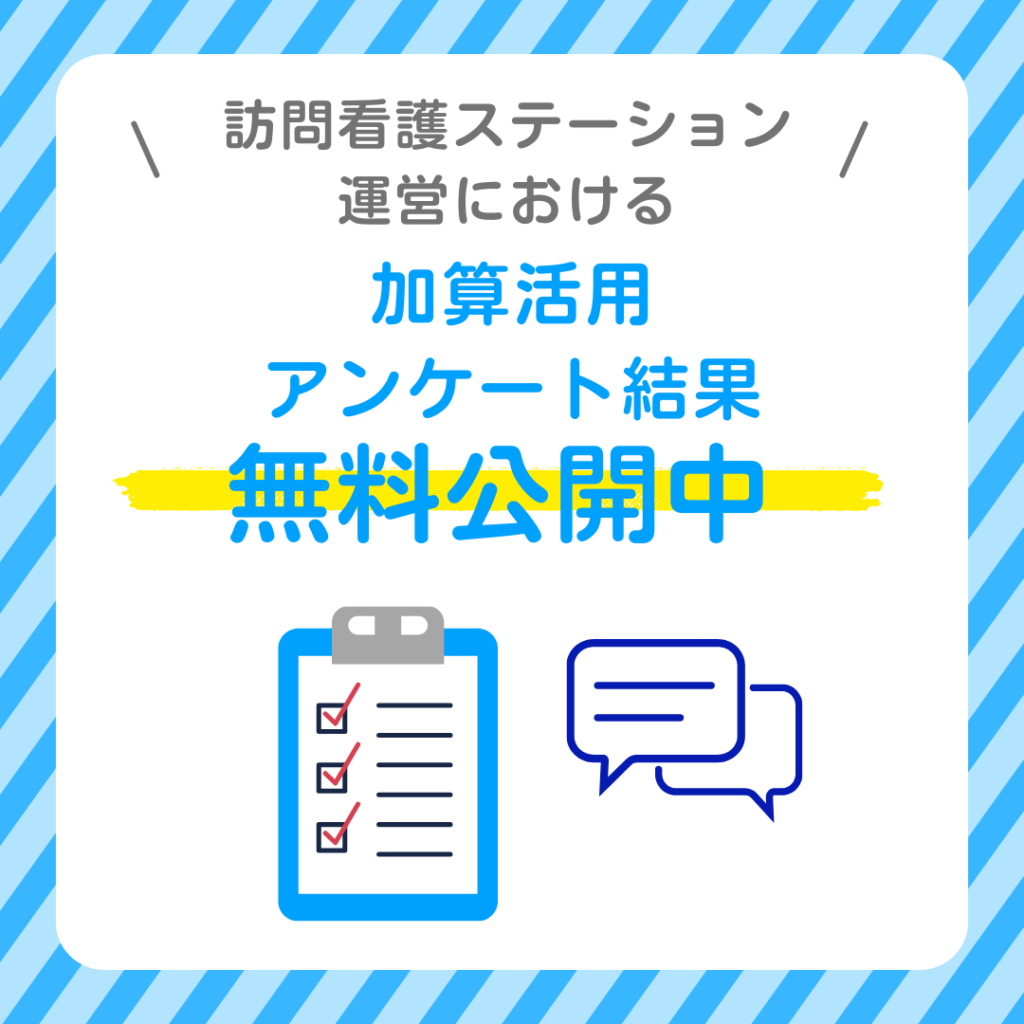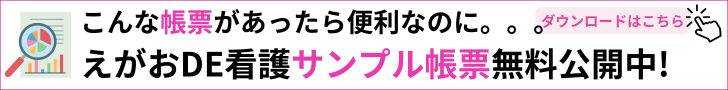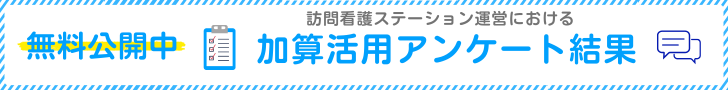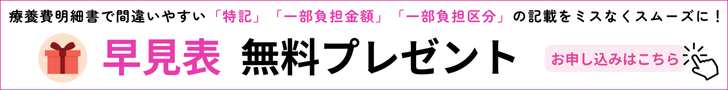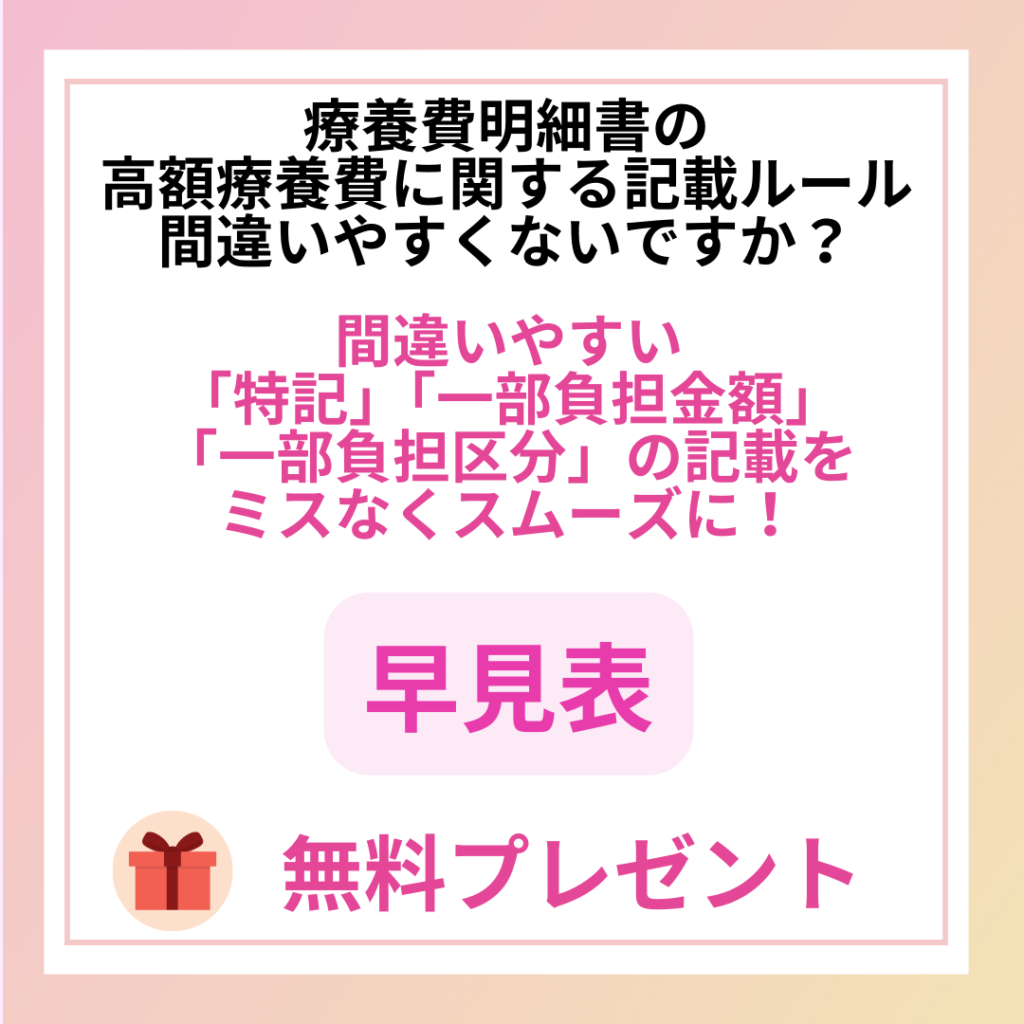介護事業所にBCPが必要な理由と義務化の背景

介護事業所になぜBCP策定が求められるのか、その理由と義務化の背景を解説します。
BCPは従来の防災対策とは異なり、あらゆる緊急時にサービス提供を止めないための計画です。
介護におけるBCP(事業継続計画)とは
介護におけるBCP(事業継続計画)とは、自然災害や感染症の発生といった緊急事態においても、介護サービスを中断させない、または中断しても短時間で復旧させるための計画を指します。
利用者の生活と健康を支える介護サービスは、簡単に止めることができません。そのため、事業所は利用者と職員の安全を守りつつ、優先すべき業務を継続できる体制をあらかじめ構築しておく必要があります。
BCP策定が求められる背景
BCP策定は、2021年度の介護報酬改定で方針が示され、経過措置を経て2024年4月からはすべての介護サービス事業者に義務付けられています。
近年、大規模な自然災害の頻発や新型コロナウイルスなどの感染症拡大により、多くの介護事業所でサービス提供が困難になる事態が生じました。
このような背景から、厚生労働省は利用者の生活を守るため、事業継続に向けた事前対策の強化を推進しています。
防災計画との違い
BCPと従来の「防災計画」は、災害への備えという点で共通しますが、目的が異なります。
防災計画は「人命の安全確保」や「被害の軽減」が主目的ですが、BCPはそれに加え「事業の継続と早期復旧」に重点を置いています。
| BCP(事業継続計画) | 防災計画 | |
| 目的 | 事業の継続と早期復旧 | 人命の安全確保と被害の軽減 |
|---|---|---|
| 対象 | 自然災害、感染症、テロなど全リスク | 地震、火災などの自然災害 |
| 内容 | 優先業務の特定、代替策、復旧手順など | 避難訓練、備蓄、安否確認など |
BCPは防災計画の内容を含みつつ、より網羅的に事業を守るための計画と理解しておきましょう。
参考:
・厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
・厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」
BCP策定は、事業所を安定して運営するための重要な準備の一つです。立ち上げ時のつまずきを未然に防ぐ方法について、以下の記事で詳しく解説しています。
≫【事例から学ぶ】訪問看護ステーション立ち上げで失敗しないための完全ガイド
介護BCPを作らないとどうなる?減算など2つのリスク

BCPを策定しない場合、事業所の運営には主に2つの大きなリスクがあります。ここでは、その具体的な内容を解説します。
介護報酬の減算
最も直接的なリスクが介護報酬の減算です。
2024年度の介護報酬改定により、BCP未策定の事業所は基本報酬が減算されることになりました。訪問看護の場合は1%の減算となります。
この措置は、訪問介護や通所系サービス等では1%、施設系サービスでは3%の減算が適用されるなど、ほぼすべての介護サービスが対象です。介護報酬の減算は収益に直結し、経営を圧迫しかねません。
安定した事業運営のため、BCP策定は必須の対応です。
BCP未策定による減算は、2024年度の介護報酬改定で決定された事項の一つです。改定の全体像を把握したい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
≫【知らないと減算⁈】訪問看護の2024年介護報酬改定|リハビリの変更点など徹底的に読み解きます!
安全配慮義務違反の可能性
次に、法的な責任を問われるリスクも考えられます。
介護事業者には、利用者や職員の生命や身体の安全を確保する「安全配慮義務」が法律で定められています。もしBCPを策定せず、災害発生時などに適切な初動対応ができなかった結果、利用者や職員に何らかの被害が生じた場合、この義務に違反したと判断される可能性があります。
そうなると、損害賠償責任を追及される事態に発展することも考えられます。BCPは、利用者だけでなく、万が一の際に事業所と職員を守るための備えでもあるのです。
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
【小規模事業所の事例あり】介護BCPの作り方5ステップと記載例

ここからは、介護BCPの具体的な作り方を5つのステップで解説します。小規模な訪問看護ステーションでも実践できるよう、記載例を交えてポイントを紹介します。
ステップ1:基本方針を決める
最初に、BCP全体の指針となる「基本方針」を定めます。
これは、災害や感染症といった危機的状況において、事業所として何を最優先に考え、どのように行動するのか、その理念を示すものです。
基本方針を明確にすることで、いざという時に職員一人ひとりが迷わず、一貫した対応をとれるようになります。
スタッフ5名規模の訪問看護ステーションでは、以下のようなシンプルな方針を掲げました。
【記載例:基本方針】
- 人命の最優先: 利用者、職員、その家族の安全確保を最優先します。
- サービスの継続: 地域の医療・介護と連携し、可能な限りサービス提供を続けます。
- 地域社会への貢献: 専門知識を生かし、地域の福祉活動に協力します。
このように、難しく考えすぎず、事業所の理念や責任を言葉にすることから始めましょう。
ステップ2:優先業務を洗い出す
次に、限られた人員や資源の中で、どの業務を優先して継続すべきかを洗い出し、順位付けを行います。
すべての業務を通常通り行うことは困難なため、特に利用者の生命維持に直結するサービスを特定しておくことが不可欠です。
以下の表のように、「最優先業務」「通常業務」「縮小・延期する業務」の3段階で整理すると、緊急時の判断が迅速に行えます。
| 優先度 | 業務内容 | 具体例(訪問看護の場合) |
| 高 | 生命維持に直結する業務 | ・利用者の安否確認 ・インスリン注射、点滴等の医療処置 ・褥瘡の処置 ・緊急オンコール対応 |
|---|---|---|
| 中 | 健康維持に必要な業務 | ・バイタルチェック ・配薬管理 ・関係機関との連絡調整 |
| 低 | 代替可能または延期できる業務 | ・清潔介助 ・リハビリテーション ・書類作成、新規契約 |
この整理が、災害直後の混乱した状況下での適切な判断を助けます。
ステップ3:厚労省ひな形・無料テンプレートの使い方
BCP策定には、公的機関が提供する無料のひな形を活用するのが最も効率的です。
- 厚生労働省
「自然災害編」と「感染症編」のひな形やガイドラインが公開されており、BCP策定の基本となります。 - 全国訪問看護事業協会
訪問看護事業所に特化した、より実践的な動画やマニュアルが参考になります。
重要なのは、これらのひな形をそのまま使うのではなく、必ず自事業所の地域特性や利用者、職員の状況に合わせて内容をカスタマイズすることです。
文章作成の補助としてAIチャットツールなどを活用しつつ、実用的な計画書に仕上げましょう。
ステップ4:「自然災害」と「感染症」それぞれの作成ポイントと記載例
BCPは、想定するリスクに応じて対策が異なります。ここでは「自然災害」と「感染症」それぞれのポイントと記載例を紹介します。
自然災害BCPの記載例
建物やライフライン(電気・水道・ガス)の被害を想定した対策が中心です。特に、職員との連絡体制の構築は初動対応の要となります。
【記載例:緊急時の連絡体制と情報共有】
- 安否確認: 災害発生後、管理者は職員の安否確認を最優先で行う。連絡方法は以下①〜③の順で実施する。
①法人用チャットツール(安否確認システム)
②個人の携帯電話(SMS)
③事前登録した家族の連絡先 - 情報共有: 事業所内のホワイトボードおよび上記チャットツールにて、被害状況、出勤可能な職員、対応中の利用者情報等をリアルタイムで共有する。
- 関係機関との連携: 市区町村の災害対策本部や地域の保健所、連携医療機関とは、平時から緊急連絡先を共有し、寸断に備え複数の通信手段を確保しておく。
感染症BCPの記載例
感染拡大防止と、職員不足への備えが重要です。衛生用品の備蓄や対応手順を定めます。
【記載例:職員が感染(または濃厚接触者)した場合の対応】
- 報告: 体調不良時は速やかに管理者に報告し、自宅待機とする。
- 業務調整: 他職員で代替できないか調整。困難ならケアマネジャーと連携し、サービス縮小も検討する。
- 衛生管理: 事業所内の消毒を徹底し、全職員の感染対策を再確認する。
- 備蓄確認: マスク、消毒液等の在庫を確認し、必要なら追加発注を行う。
ステップ5:職員共有と保管方法
BCPは、全職員がその内容を理解し、緊急時に活用できて初めて意味を持ちます。定期的な研修で周知の徹底を図りましょう。
保管方法は、「紙」と「データ」の両方で備えるのがおすすめです。
- 紙での保管: 停電時に備え、事務所の分かりやすい場所に保管
- データでの保管: クラウド上に保管し、職員がいつでもスマホ等で確認できるようにする
BCPは一度作ったら終わりではなく、訓練の実施や事業所の状況変化に応じて、少なくとも年1回は内容の見直しと更新を行いましょう。
介護BCP策定で必須の研修・訓練の方法

介護BCPは、策定するだけでなく、全職員にその内容を周知し、いざという時に計画通りに行動できるよう備えておく必要があります。
そのため、BCPには定期的な「研修」と「訓練」の実施が義務付けられています。ここでは、小規模事業所でも無理なく実施できる具体的な進め方を紹介します。
研修の進め方(小規模でもできる工夫)
研修の目的は、事業所のBCPの内容をすべての職員が正しく理解し、緊急時に自分が何をすべきか把握することです。しかし、全員を集めて長時間の研修を行うのは難しいでしょう。
そこで、以下のような工夫を取り入れることをおすすめします。
- 定例会議の活用: 毎月のミーティングで10〜15分をBCP研修の時間にあて、「今月は安否確認の方法」「来月は利用者への連絡手順」など、テーマを絞って少しずつ周知を徹底させます。
- 読み合わせと質疑応答: BCPの担当者が重要なポイントを読み上げ、その後、職員からの質問を受け付ける時間を設けます。これにより、認識のズレや疑問点をその場で解消できます。
- 新入職員へのオリエンテーション: 新しいスタッフが入職した際には、必ずBCPの内容を説明する機会を設けることで、組織全体の意識を維持します。
研修は一度きりではなく、定期的に繰り返し行うことで知識が定着します。事業所の状況に応じて、最も負担の少ない方法を検討してみましょう。
訓練の種類と最低限実施すべき内容
訓練は、策定したBCPが実際に機能するかどうかを検証し、課題を見つけて改善するために行います。厚生労働省のガイドラインでは、少なくとも年に1回以上の訓練実施が推奨されています。
訓練にはいくつか種類がありますが、小規模事業所ではまず「机上訓練」から始めるのが現実的です。
| 訓練の種類 | 概要 | 小規模事業所での進め方 |
| 机上訓練 | 緊急事態のシナリオを提示し、BCPを見ながら、各担当者がどう行動するかを話し合うシミュレーション形式の訓練 | ①「震度6の地震が発生し、停電と通信障害が起きている」などの具体的な状況を設定 ②参加者(全職員)で「まず何をすべきか」「誰が誰に連絡するか」をBCPに基づいて議論する ③出てきた課題(連絡がつかない等)や改善点を記録する |
|---|---|---|
| 全体訓練 | 実際に身体を動かし、役割分担に従って安否確認や避難、情報伝達などを行う、より実践的な訓練 | 地域の自治体や消防署が主催する防災訓練への参加を検討する。 |
まずは机上訓練をしっかりと行い、「計画通りに行動できるか」「計画に漏れはないか」を評価することが大切です。
訓練で見つかった課題は必ずBCP本体にフィードバックし、計画をより実用的なものへと見直し、改善していくことが求められます。
介護BCP策定に使える補助金・助成金まとめ

BCPの策定や運用には、安否確認システムの導入や備蓄品の購入など、ある程度の費用がかかることも事実です。
しかし、国や自治体が設けている補助金・助成金制度を上手に活用すれば、事業所の金銭的な負担を大きく軽減できる可能性があります。ここでは、代表的な制度を紹介します。
ICT導入補助金
BCPの実効性を高める上で、ICT(情報通信技術)の活用は非常に有効です。例えば、災害時でも迅速に職員の安否確認ができるシステムや、事業所の外からでも利用者の情報を確認できるクラウド型の介護ソフトなどは、事業継続の強力な支えとなります。
こうした中小企業向けのICTツール導入を支援するのが「IT導入補助金」です。この制度を活用すれば、介護ソフトや勤怠管理システム、チャットツールなどの導入費用の補助が受けられます。
制度の詳しい内容や申請方法は年度ごとに改定されるため、まずは公式サイトで最新の情報を確認しましょう。また、導入を検討しているシステムの販売企業が申請をサポートしてくれるケースも多いので、一度相談してみることをおすすめします。
参考: IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
地域独自の補助金・助成事例
国の制度とは別に、各都道府県や市区町村が、地域の中小企業向けに独自の補助金・助成金制度を設けている場合があります。BCP策定に特化した支援策も増えています。
これらの制度は、以下のような幅広い用途に活用できる可能性があります。
- BCP策定に関する専門家への相談費用
- マスクや消毒液、非常食といった備蓄品の購入費用
- 自家発電設備やポータブル電源などの設備導入費用
- 職員向けの防災研修にかかる費用
事業所が所在する地域で利用できる制度がないか、一度確認してみてください。
情報を探す際は、自治体のホームページで「事業所のある市区町村名 BCP 補助金」や「都道府県名 中小企業 災害対策 支援」といったキーワードで検索するのが有効です。
不明な点があれば、自治体の担当窓口や、地域の商工会議所に問い合わせてみるのもよいでしょう。商工会議所は地域の事業者を支援する公的な側面も持っているため、補助金に関する一般的な情報の相談に応じてくれる場合もあります。
まとめ:介護BCPはテンプレ活用で現場負担を減らせる

介護BCPの策定は、多忙な管理者にとって大きな負担に感じられるかもしれません。
しかし、本記事で紹介したように、国などが提供する無料のひな形を活用し、5つのステップに沿って進めることで、小規模事業所でも現場の負担を抑えながら実用的な計画を作成することが可能です。
作成した計画をただの書類で終わらせず、いざという時に本当に役立つものにするには、日々の情報共有や緊急時の連絡体制の整備が欠かせません。
まずはこの記事を参考に、自事業所に合ったテンプレートを手に取るところから、第一歩を踏み出してみてください。
BCP運用をはじめ、日々の記録や請求業務を効率化するには、訪問看護ソフトの活用がおすすめです。ソフトで何ができるのか、具体的に解説した記事はこちらです。
≫【経営管理をサポート】訪問看護ソフトとは?|運営状況の可視化から業務効率化まで徹底解説
最後までお読みくださり、ありがとうございました。