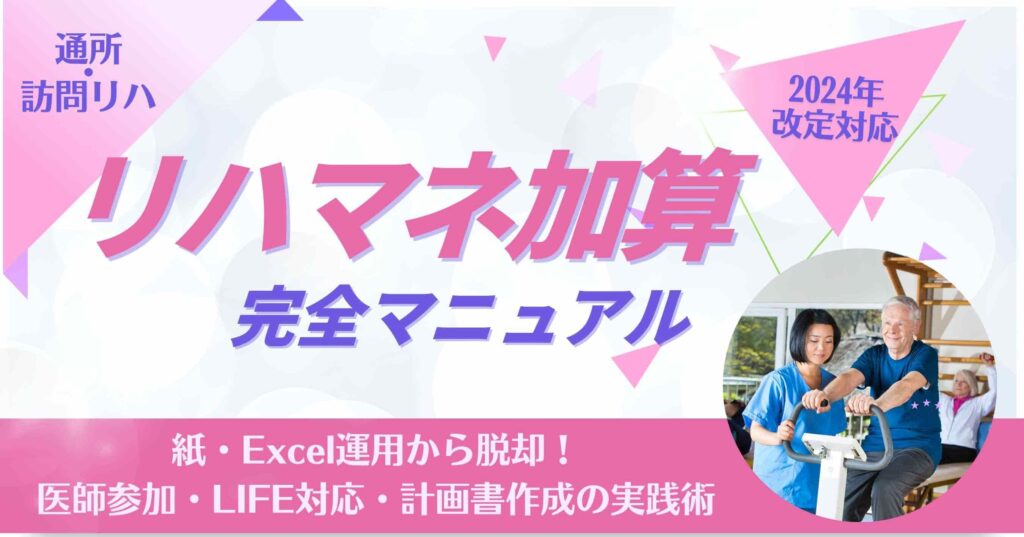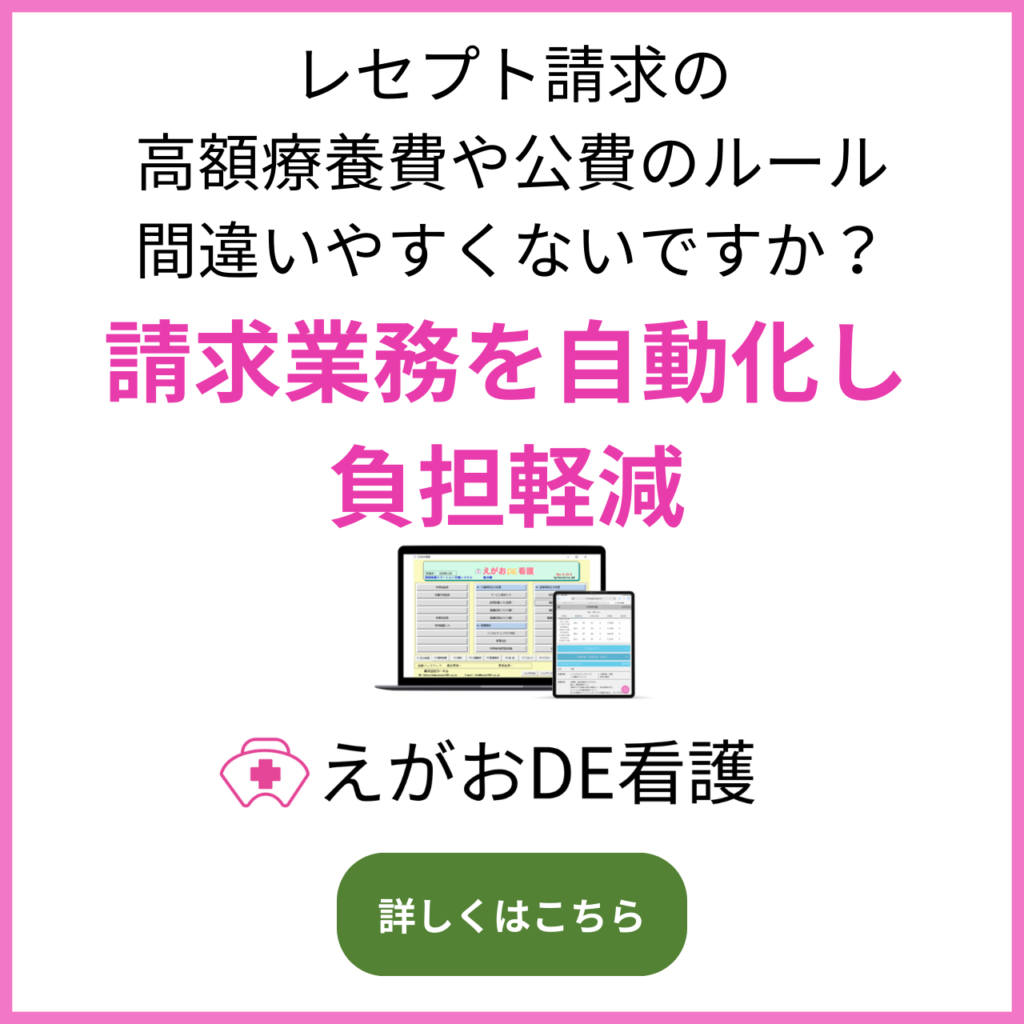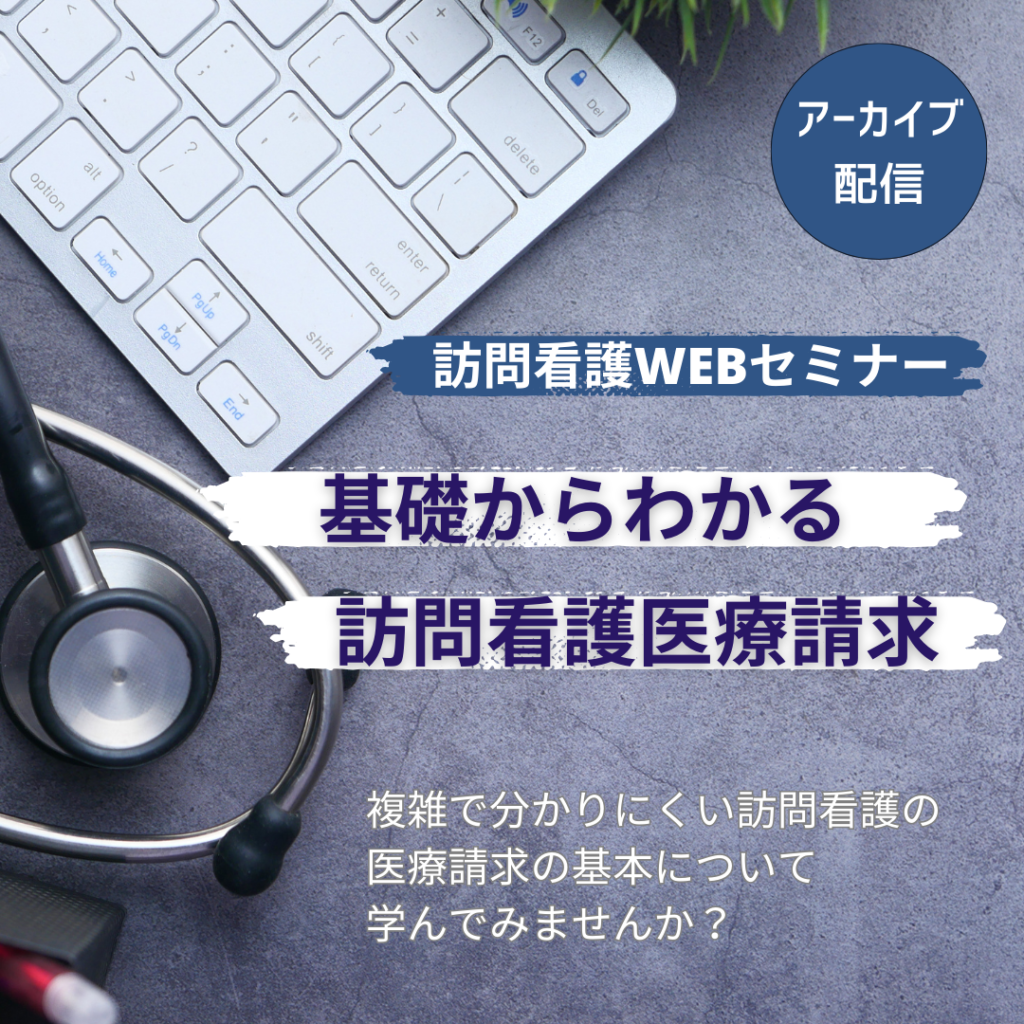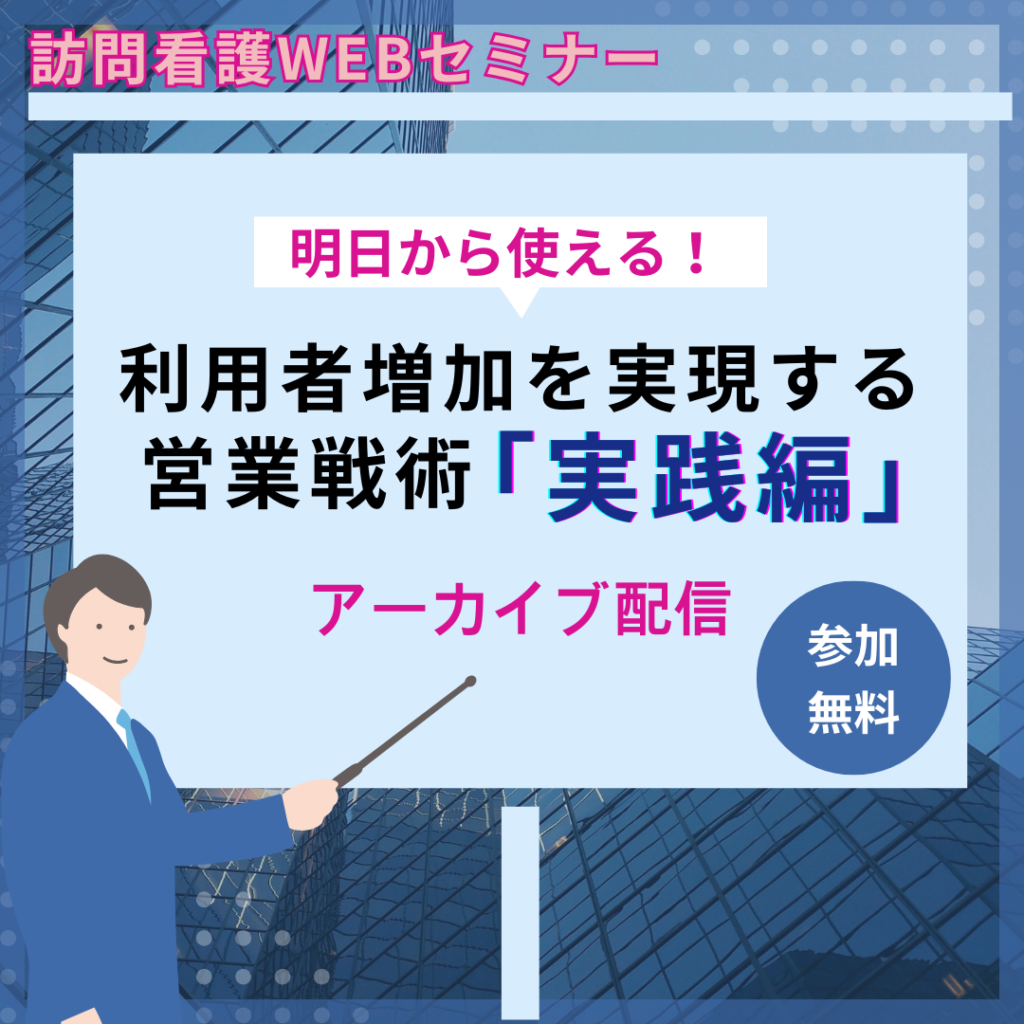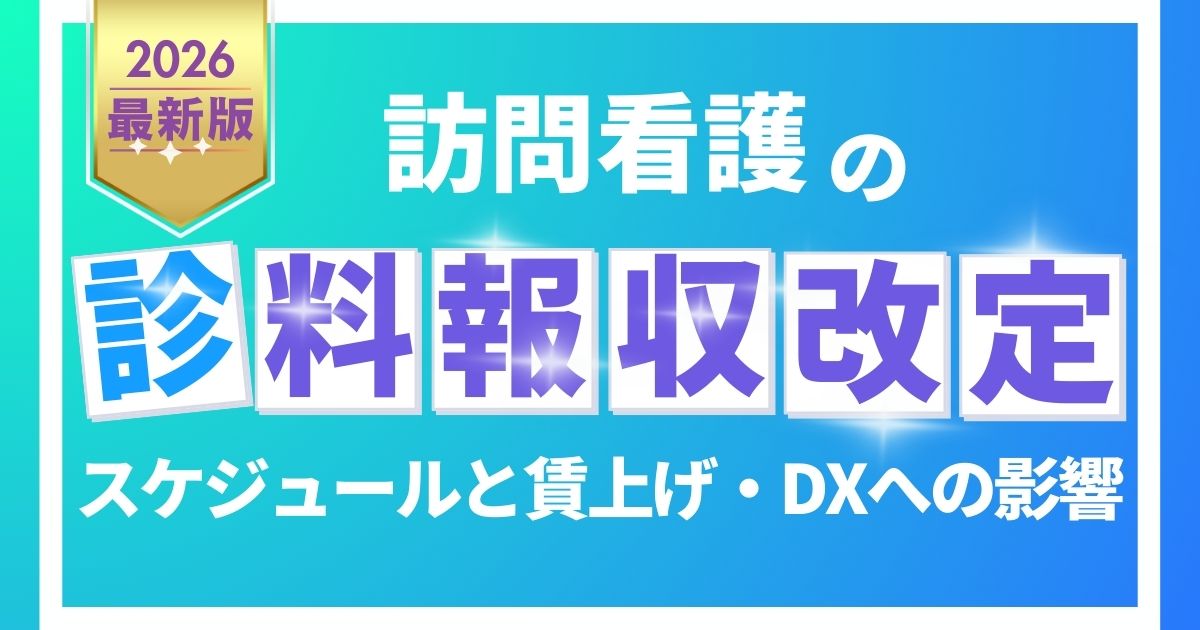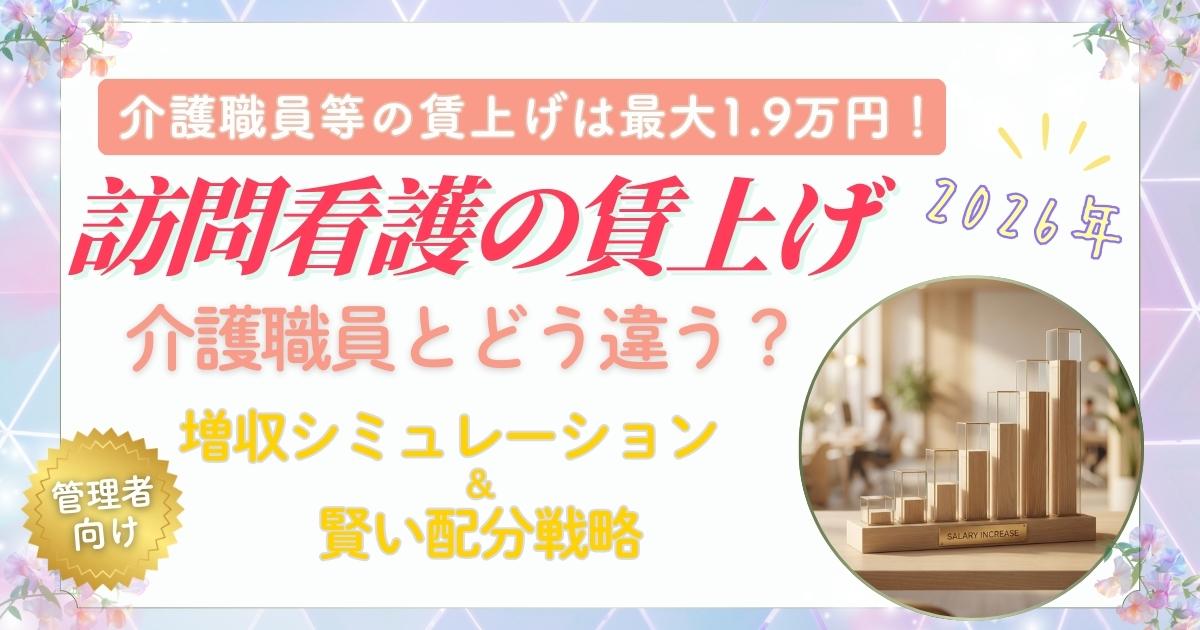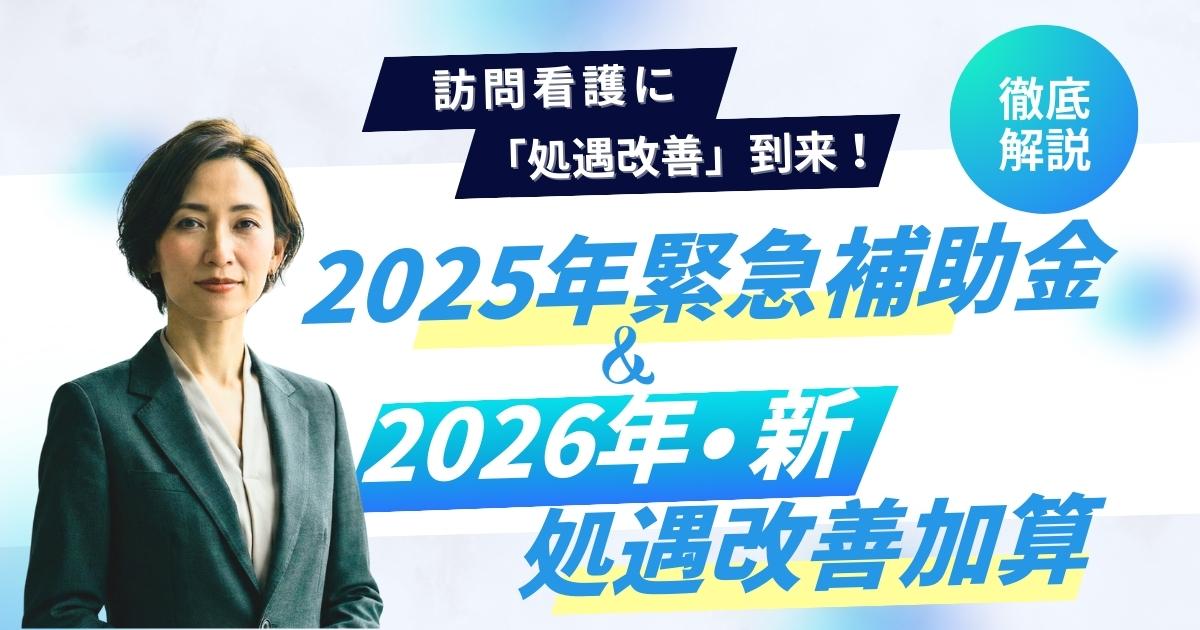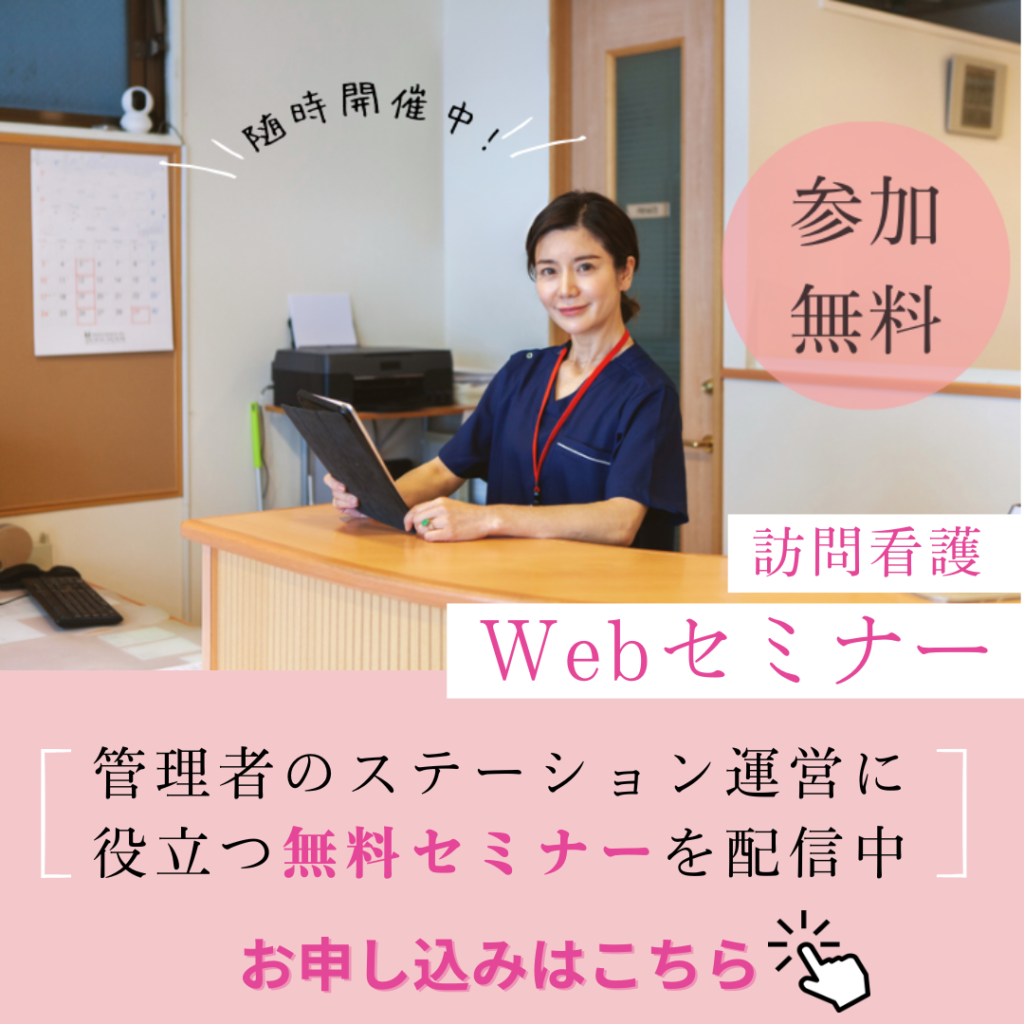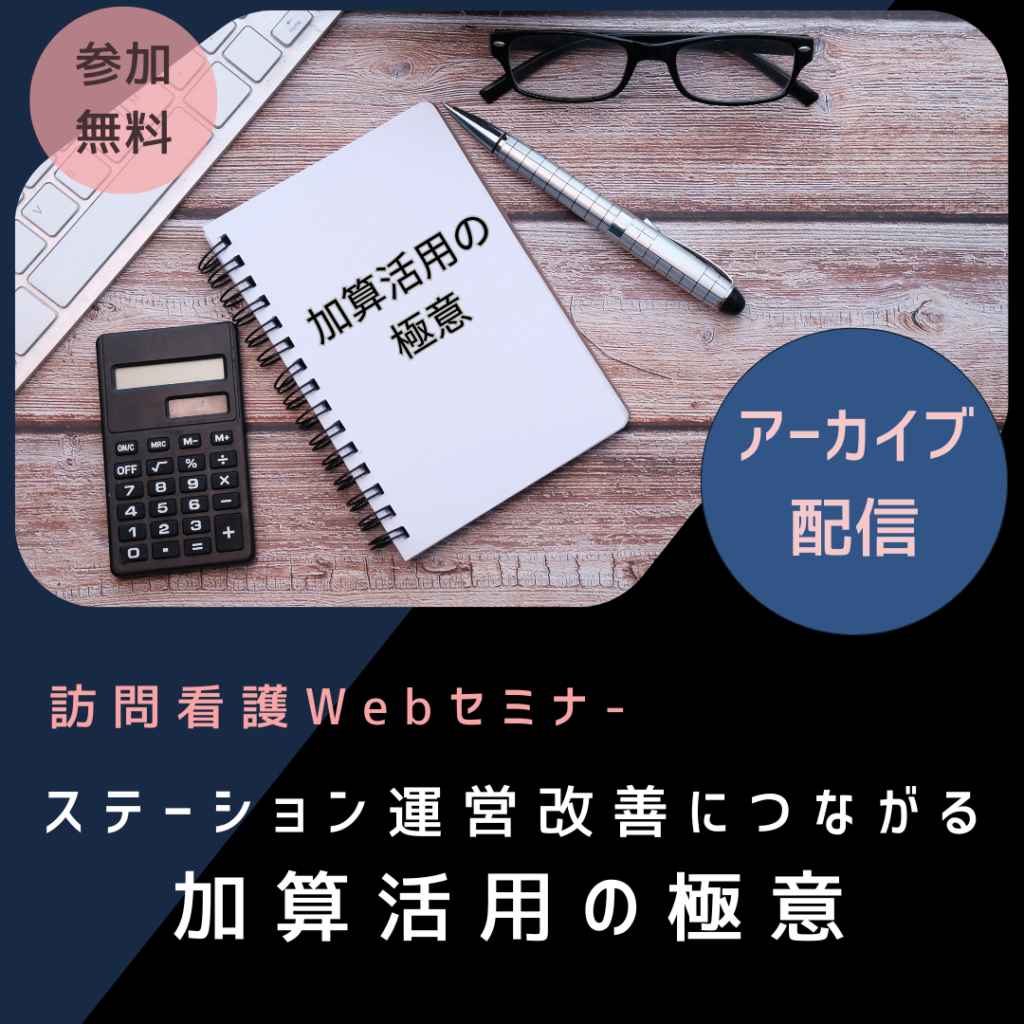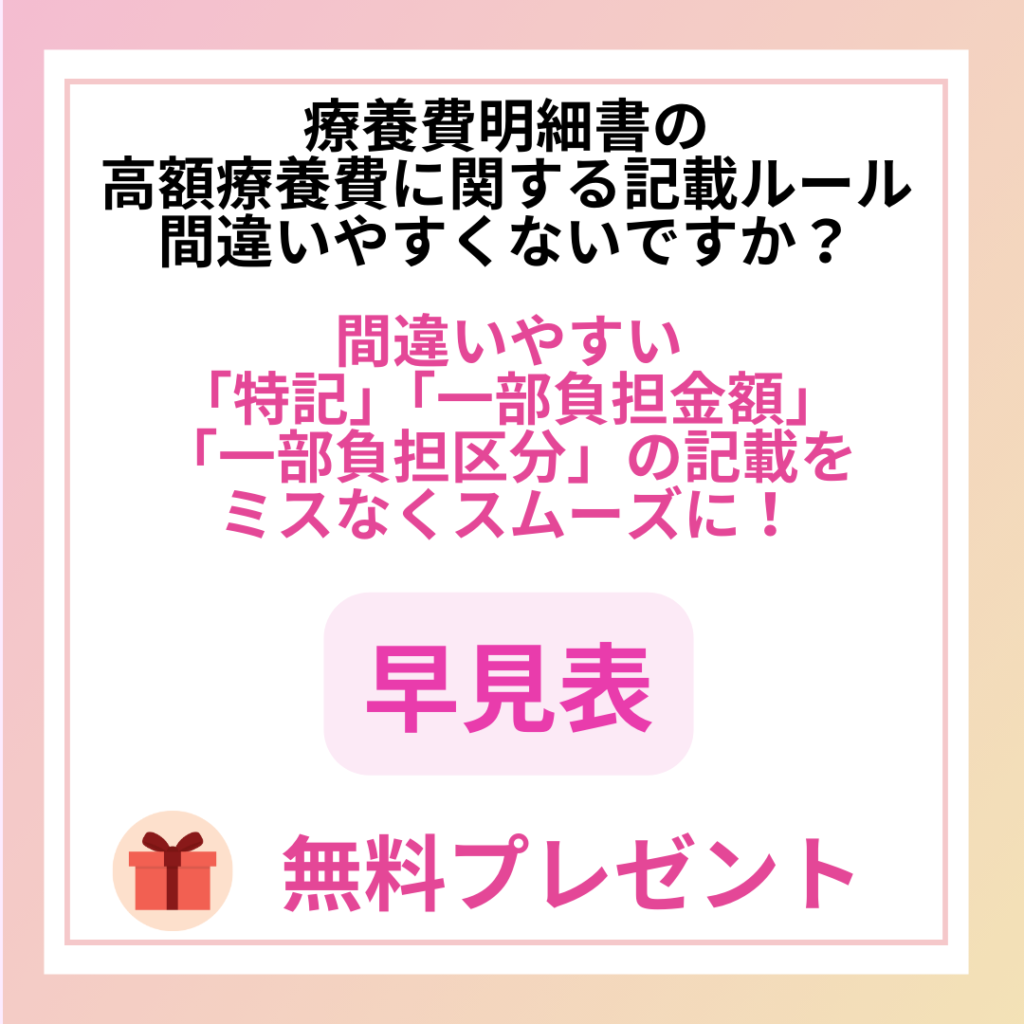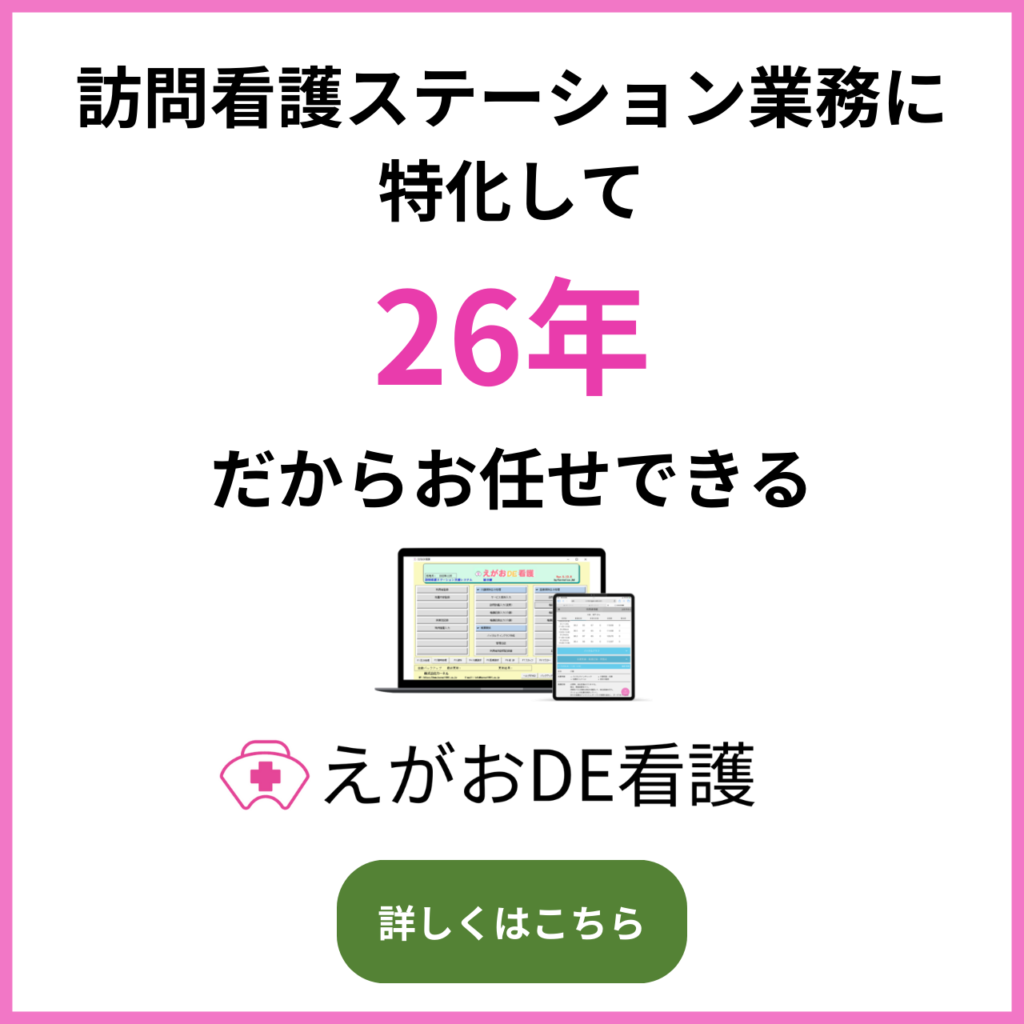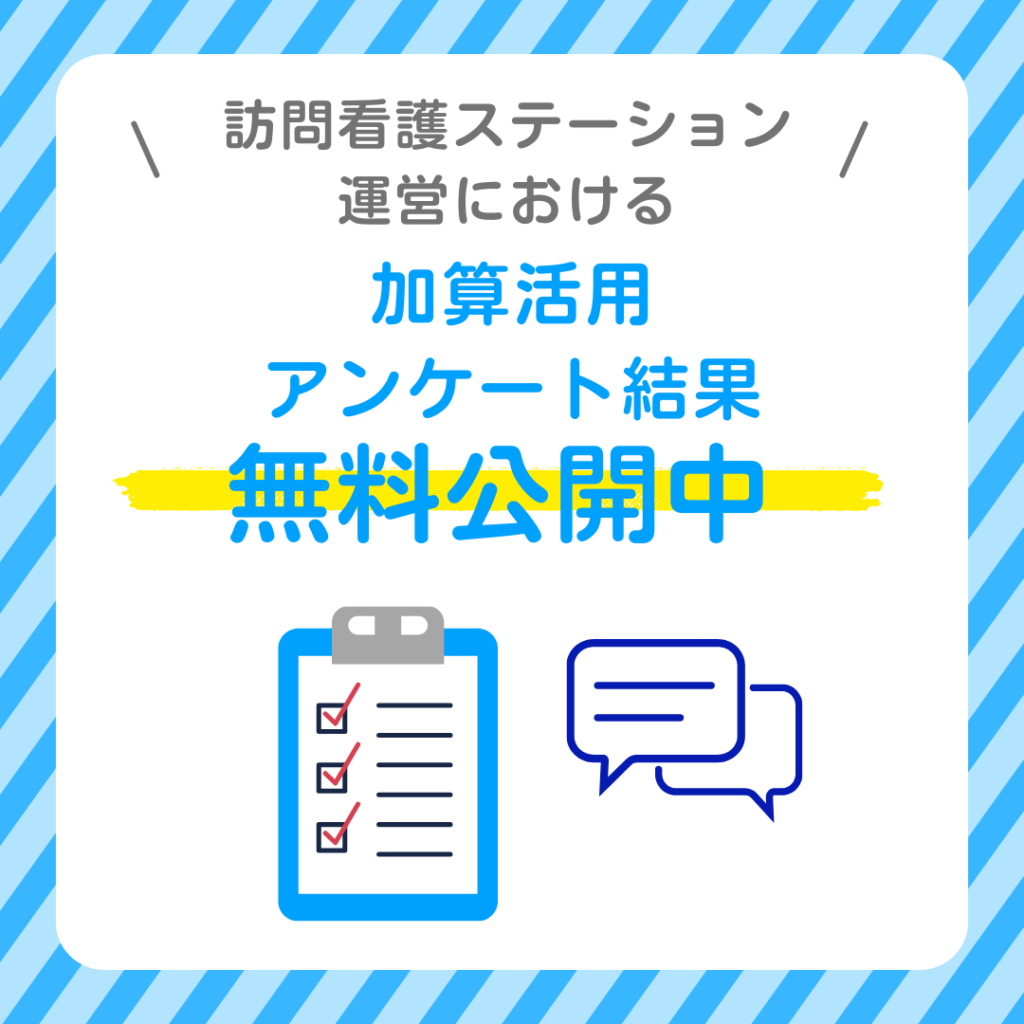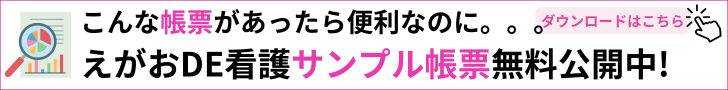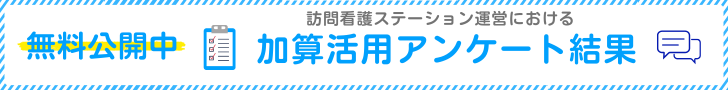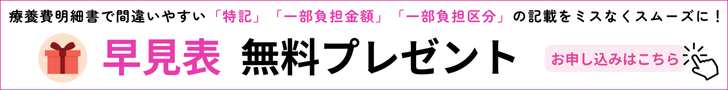リハビリテーションマネジメント加算とは?2024年介護報酬改定のポイント

リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)は、質の高いリハビリ提供体制を評価する加算です。2024年度改定で要件が大きく変わりました。
まずは、その目的と改定のポイントを整理しましょう。
加算の目的と対象サービス
この加算は、医師の指示のもと多職種が連携し、計画的なリハビリで利用者の自立支援や重度化防止を図る体制を評価するものです。
個別のリハビリ計画の立案から評価・見直しまでの一連のプロセス(PDCAサイクル)が評価対象となり、対象サービスは通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションです。
2024年度改定における主な変更点
2024年度改定では、LIFE活用とリハビリ・口腔・栄養の一体的な連携が、より重視されるようになりました。これは科学的データに基づき、利用者を多角的に捉えるケアが求められていることを意味します。
主な変更点は以下の2つです。
- LIFE提出の評価強化:高い単位数の区分では、LIFEへのデータ提出が必須条件となりました
- 新区分(ハ)の新設: 口腔・栄養のアセスメントと連携を評価する区分が追加されました
💡この変更により、単にリハビリを提供するだけでなく、データに基づいた科学的なアプローチが求められるようになっています。
【最新版】リハビリテーションマネジメント加算の単位数と算定要件を解説

ここからは、2024年度改定後の最新の単位数と算定要件をサービスごとに詳しく解説します。
通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算
まず、通所リハビリテーションの加算について見ていきましょう。
加算(イ)(ロ)(ハ)の単位数
単位数は、早期の集中的なリハビリを評価するため、リハビリ提供開始から6ヶ月を境に変動します。2024年度改定後の単位数は以下のとおりです。
| 加算区分 | 6ヶ月以内の期間 | 6ヶ月を超える期間 |
| 加算(イ) | 560単位/月 | 240単位/月 |
| 加算(ロ) | 593単位/月 | 273単位/月 |
| 加算(ハ) | 793単位/月 | 473単位/月 |
加算(イ)(ロ)(ハ)の算定要件と違いを比較
3つの区分には、まず土台となる共通の基本要件があります。
【共通の基本要件】
- 医師の指示
- 計画書の作成と同意、医師への報告
- 3ヶ月に1回以上のリハビリテーション会議(テレビ電話等も可)
- ケアマネジャーへの情報提供
- 居宅訪問による助言
これらの共通要件に加え、(ロ)と(ハ)では以下の追加要件が必要です。
- 加算(ロ)の追加要件
加算(イ)の要件に加え、LIFEへのデータ提出と、そのフィードバック情報を活用したPDCAサイクルの実践が必須です。 - 加算(ハ)の追加要件
加算(ロ)の要件に加え、さらに多職種による専門的なアセスメントと連携が求められます。言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、管理栄養士などが共同で口腔・栄養等のアセスメントを実施。把握した課題をリハビリ計画に反映させる必要があります。
各区分の違いを以下の一覧表にまとめました。
| 算定要件 | 加算(イ) | 加算(ロ) | 加算(ハ) |
| 基本要件(計画書作成、会議、居宅訪問など) | ◯ | ◯ | ◯ |
| LIFEへの情報提出と活用 | – | ◯ | ◯ |
| 多職種による口腔・栄養等のアセスメントと計画への反映 | – | – | ◯ |
💡上位の加算ほどデータ活用と多職種連携が評価されます。自施設の体制に合わせて目指す加算を検討しましょう。
訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算
次に、訪問リハビリテーションにおけるリハマネ加算について解説します。
加算(イ)(ロ)の単位数
訪問リハビリの単位数は、通所リハビリとは異なり、リハビリ提供期間による変動はありません。2024年度改定では、医師による利用者への直接的な説明を評価する加算が新設された点が大きな特徴です。
単位数は以下のとおりです。
| 加算区分 | 単位数/月 |
| 加算(イ) | 180単位 |
| 加算(ロ) | 213単位 |
| 新設加算(医師による計画書説明) | 270単位 |
加算(イ)(ロ)の算定要件と違いを比較
要件は通所リハと共通点が多いですが、居宅サービスという特性上、ケアマネジャーや他サービス従業者との連携がより具体的に求められる点が特徴です。
基本となる加算(イ)の算定要件は以下のとおりです。
【加算(イ)の算定要件】
- 医師の指示
- 計画書の作成と同意、医師への報告
- 3ヶ月に1回以上のリハビリテーション会議(テレビ電話等も可)
- ケアマネジャーへの情報提供
- 他サービス従業者への助言
(ロ)と新設加算では、以下の追加要件が必要です。
- 加算(ロ)の追加要件
加算(イ)の要件に加え、LIFEへのデータ提出とフィードバック情報を活用したPDCAサイクルの実践が必須です。 - 新設加算(医師による計画書説明)の要件
加算(イ)または(ロ)を算定中に、事業所の医師が自ら計画書の内容を説明し同意を得た場合に算定できます(理学療法士等による説明は対象外)。
各区分の違いを以下の表にまとめました。
| 算定要件 | 加算(イ) | 加算(ロ) | 新設加算 |
| 基本要件(計画書作成、会議、連携など) | ◯ | ◯ | ◯ |
| LIFEへの情報提出と活用 | – | ◯ | ◯ ※1 |
| 医師による計画書説明と同意取得 | – | – | ◯ |
💡LIFE活用に加え、医師の直接的な関与が評価のポイントです。
リハビリテーションマネジメント加算とLIFEの連携:データ提出の要件と注意点

リハマネ加算の上位区分ではLIFE連携が必須です。ここでは提出要件と、科学的介護推進体制加算との違いを解説します。
LIFEへの情報提出が要件となる加算区分と具体的な影響
高い単位数を目指す上で、LIFEへのデータ提出は必須条件となっています。
対象となる加算は以下のとおりです。
- 通所リハビリテーション: 加算(ロ)、加算(ハ)
- 訪問リハビリテーション: 加算(ロ)
これらの区分では、リハビリテーション計画書等の情報をLIFEに提出し、フィードバック情報を活用したPDCAサイクルを実践することが求められます。
科学的介護推進体制加算との関係性と混同しないためのポイント
本加算と「科学的介護推進体制加算」は、どちらもLIFEへ提出しますが、目的が異なる全く別の加算です。違いを理解しないと算定ミスに繋がるため注意しましょう。
両者の違いは以下のとおりです。
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ・ハ) | 科学的介護推進体制加算 | |
| 評価の視点 | 「個別のリハビリ計画」の質(PDCA) | 「事業所全体」の科学的介護への取り組み体制 |
| 主な提出情報 | リハビリテーション計画書(様式等) | 利用者の心身の状態等(ADL、栄養、口腔など) |
「科学的介護推進体制加算」について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
≫【通所・訪問リハ管理者必見】科学的介護推進体制加算とは?算定要件と業務負担を減らす実践的運用術
管理者の業務負担を軽減!リハビリテーションマネジメント加算の実践的運用術

複雑なリハマネ加算ですが、日々の運用を工夫すれば負担は大幅に軽減できます。ここでは、明日から実践できる効率化テクニックをご紹介します。
効率化の鍵:リハビリテーション計画書の作成ポイントと管理負担軽減策
計画書の作成・管理負担を減らす鍵は、「作業の標準化」と「ツールの活用」です。
現在、紙やExcelでの手作業を行っている場合、転記ミスや書類探しの手間が多く非効率になっています。特にLIFEへの手入力は、現場の負担を大きく増大させる要因となっています。
まず、すぐに取り組めるのが評価項目のテンプレート化です。基本フォーマットを準備すれば、作成時間が短縮され、記入漏れも防げます。
より効果的なのが、介護ソフト(リハビリ支援ソフト)の活用です。ソフトを導入すると、以下のようなメリットがあります。
- 入力の効率化: 利用者情報が自動反映され、過去計画の参照・複写も容易
- ミスの防止: 記録から計画書、LIFEまでデータが連携し、転記作業が不要
- ペーパーレス化: 作成から保管までシステムで完結し、帳票整理の手間を削減
これらの工夫で事務作業を効率化し、利用者ケアやスタッフ連携といった本来の業務に時間を使えるようになります。
多職種連携を促進!リハビリテーション会議を成功させる3つのコツ
算定の壁になりがちなリハビリテーション会議。現場の悩みを解決する、実践的な3つのコツを解説します。
コツ①:多忙な医師を巻き込む具体的なアプローチと参加促進の工夫
多忙な医師の参加調整は、ICTの活用と柔軟な対応が鍵となります。
「医師の会議参加が困難」という課題は、リハマネ加算の算定が難しい最大の理由として、厚生労働省の調査でも明らかになっています(参考:R2 厚生労働省「訪問リハビリテーション」p.30)。
この課題解決の第一歩が、ビデオ通話などICTの活用です。2018年度から制度的に認められており、移動負担がなくなるため参加へのハードルを大きく下げることができます。
例えば、「外来診療の合間の冒頭10分」に、医師の使い慣れたスマートフォン(FaceTimeやLINE通話など)で参加してもらう工夫が有効です。
次に、会議以外の選択肢も準備しておくことです。やむを得ず医師が不参加でも、会議後に担当者が内容を報告し、医師が計画書を本人・家族へ説明し同意を得ることで加算算定は可能です。この選択肢も事前に準備しておきましょう。
普段から要点をまとめた報告書で簡潔な情報共有を心掛け、協力しやすい関係性を築くことも重要です。「医師の参加は、利用者の状態向上とチーム連携強化に不可欠」という意義を事業所全体で共有し、医師の負担をサポートする姿勢を見せることで、より良い協力関係につながります。
コツ②:会議を円滑に進めるファシリテーション術と議論のまとめ方
会議を実りあるものにするには、進行役(ファシリテーター)の技術が重要です。単なる報告会で終わらせないためのポイントは3つあります。
- ゴールの事前共有: 事前にアジェンダ(議題)を配布し、「今回は〇〇を決めます」と目的を明確にする
- 視覚的資料の活用: グラフや写真、短い動画で利用者の状態を共有すると、多職種間の理解が深まる
- 決定事項の確認: 会議の最後に「決定事項」「今後のアクション」「担当者」を要約し、議事録に残す
以上の点を意識するだけで、会議の質は大きく向上するはずです。
コツ③:複数事業所での共同開催など業務負担を減らす運用事例
通所と訪問リハなど、複数のサービスを提供している場合、リハビリテーション会議の共同開催が有効です。
同一法人の通所・訪問リハを利用している方なら、関係者が一度に集まり、合同で会議を実施できます。これには次のようなメリットがあります。
- 負担軽減: 関係者が集まる機会を1回に集約できる
- 質の向上: 通所と在宅、両方の視点からの情報をその場で共有でき、より一貫性のある計画を立てやすくなる
参考:厚生労働省令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問5
リハビリテーションマネジメント加算のよくある疑問を解決! Q&A

管理者の皆様からよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。
Q1. 通所リハビリで6ヶ月を超えると単位数が下がりますが、この算定期間はいつリセットされますか?
⇒主なリセット条件は、要介護認定の区分変更があった場合や、3ヶ月以上サービスの利用がなかった場合です。
これらは利用者の状態が大きく変わり、計画を根本的に見直す必要があると判断されるためです。リセットされると、改めて6ヶ月間の高い単位数を算定できる期間が開始されます。
注意点:年が変わっただけではリセットされません。
Q2.利用者が要支援から要介護へ区分変更した場合の取扱いは?
⇒加算の算定プロセスを、最初から改めて実施する必要があります。
要支援から要介護への変更は、それまでの計画が終了となる大きな節目です。新しい要介護認定に基づき、再度リハビリテーション計画書を作成し、リハビリテーション会議の開催、利用者・家族からの同意取得を経て、新たに加算の算定を開始してください。
Q3.医師がリハビリテーション会議に欠席した場合、加算は算定できませんか?
⇒特定の条件を満たせば算定可能です。
やむを得ない事情で医師が会議に参加できなくても、会議後に担当者が結果を報告し、医師自身が利用者または家族へ計画書を説明・同意を得ることで算定できます。
ただし、医師が別に時間を設ける必要があり調整が難しいため、まずはICTを活用した会議参加を検討するのが現実的です。
Q4.計画書への医師のサインは毎回必要ですか?
⇒必ずしも物理的なサイン(署名・捺印)が必須ではありません。
重要なのは、「医師の具体的な指示の下でリハビリが行われている」という記録です。計画書への直接的なサインが最も明確な証拠となります。しかし、それが難しい場合でも、医師の指示や計画への同意が診療録(カルテ)に明確に記録されていれば、算定要件を満たします。
まとめ

2024年度改定により、リハマネ加算はLIFE活用と多職種連携を実践する「科学的介護」を評価する加算へと変わりました。要件は複雑ですが、ポイントを押さえれば安定した算定は可能です。
本記事で解説したポイントや、計画書作成からLIFE連携までを一気通貫で行える介護ソフトの活用は、業務負担の軽減に大きく貢献します。これらの取り組みは、質の高いケアと安定した事業所運営の基盤となります。ぜひ、明日からの業務改善にお役立てください。
最後までお読みくださりありがとうございました。