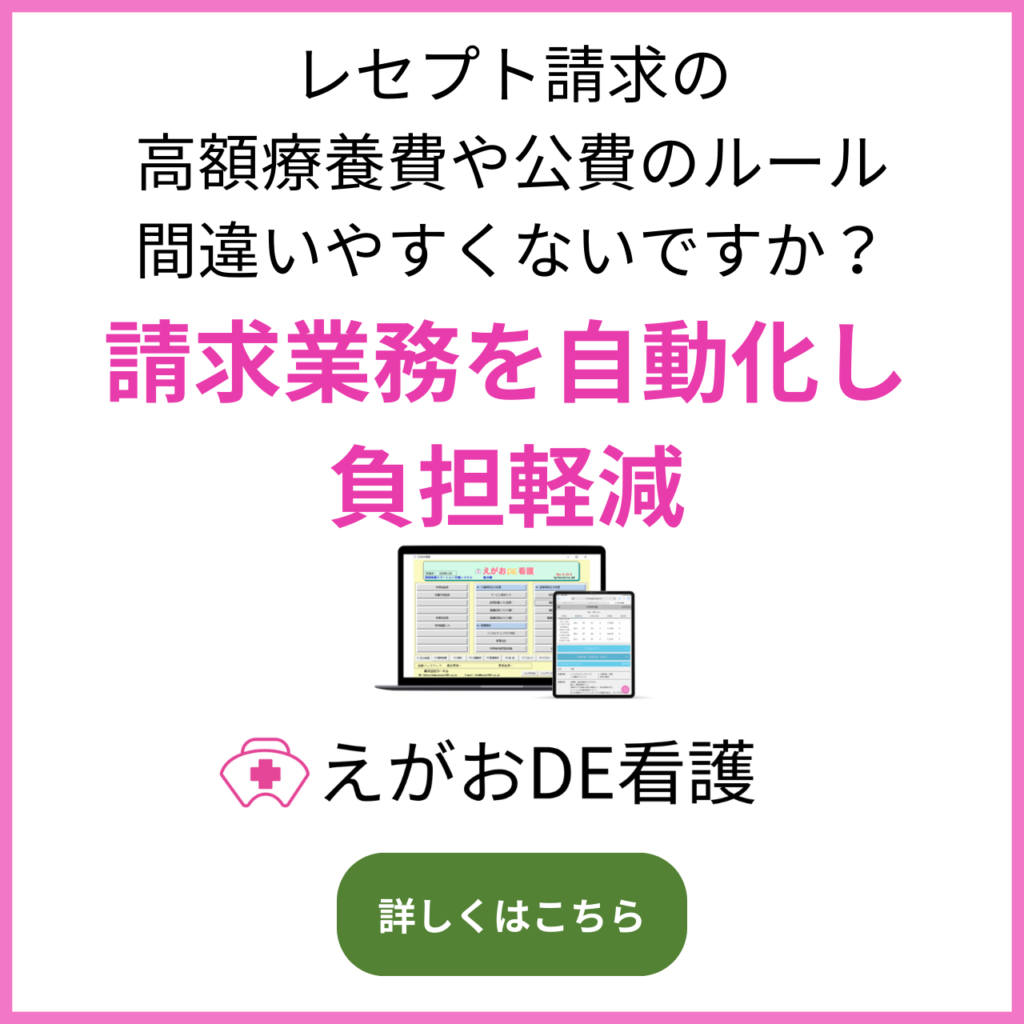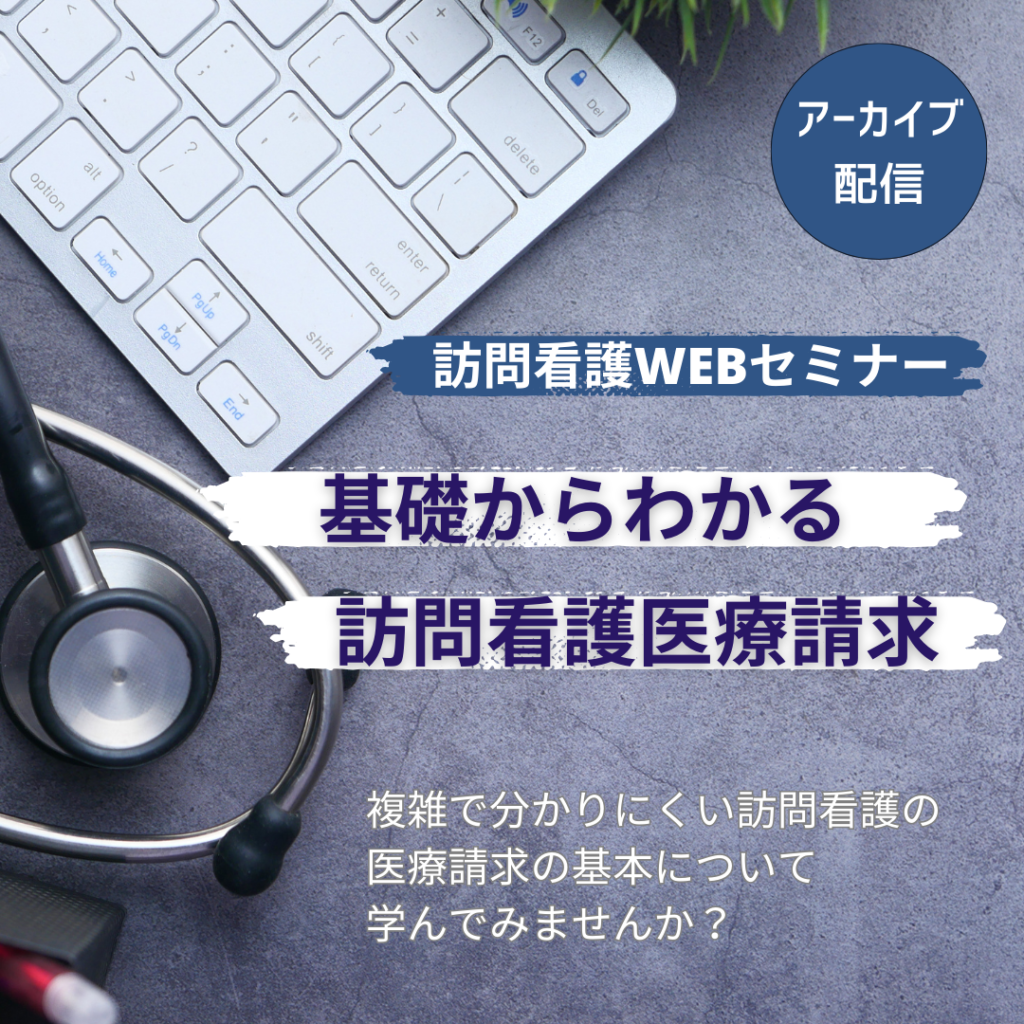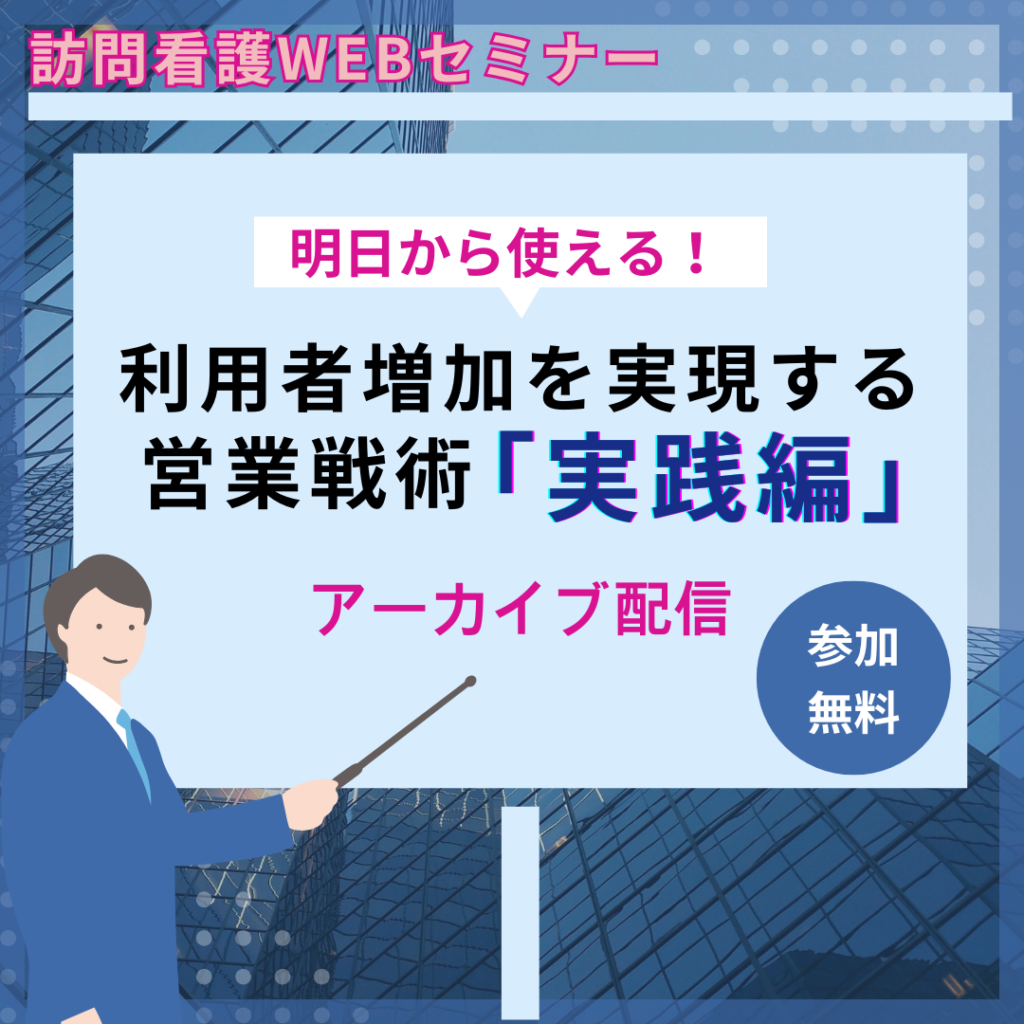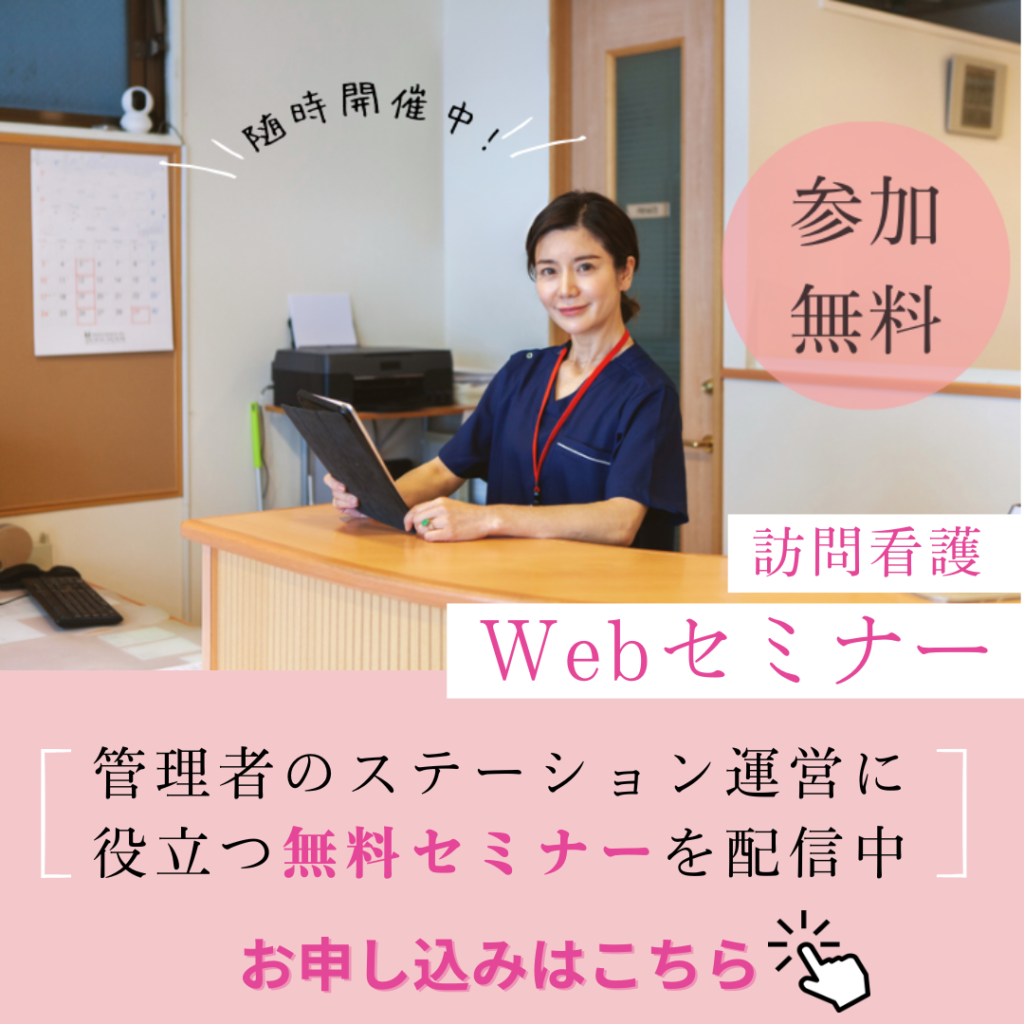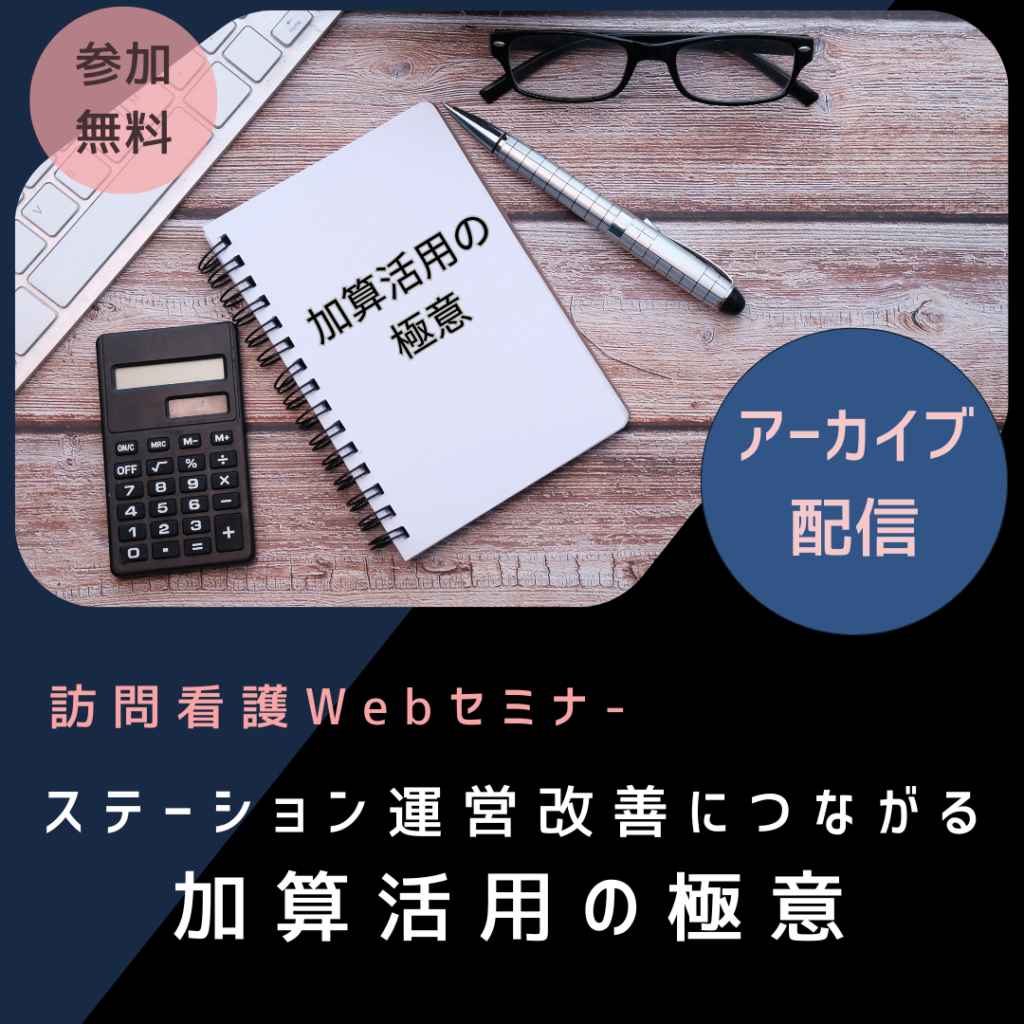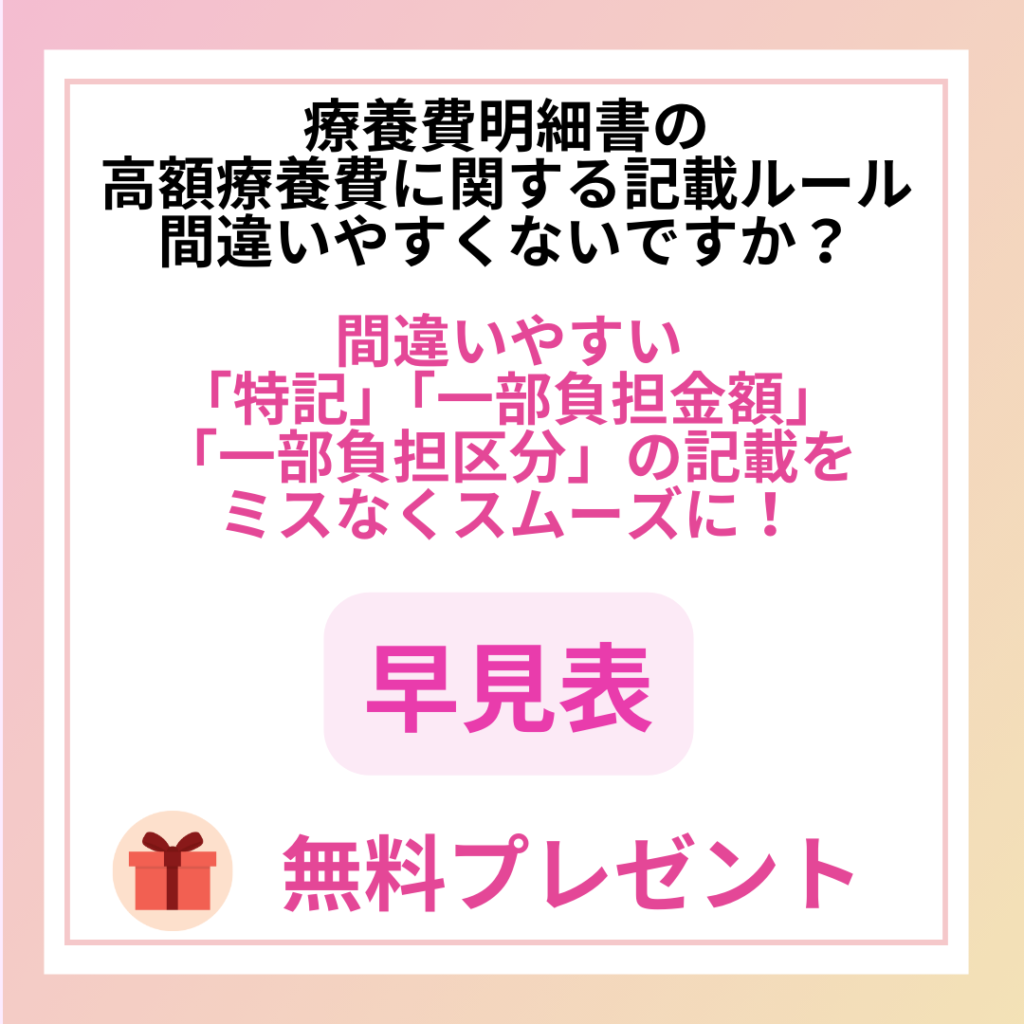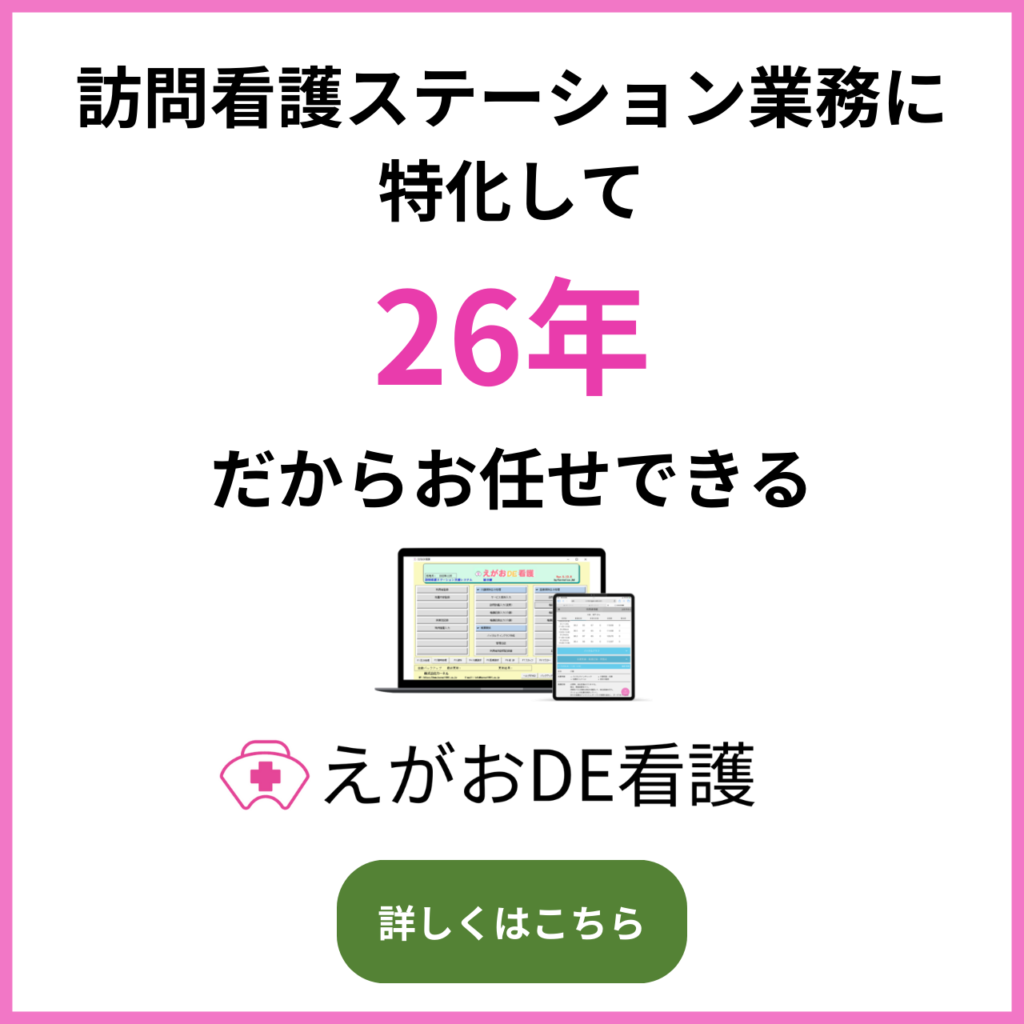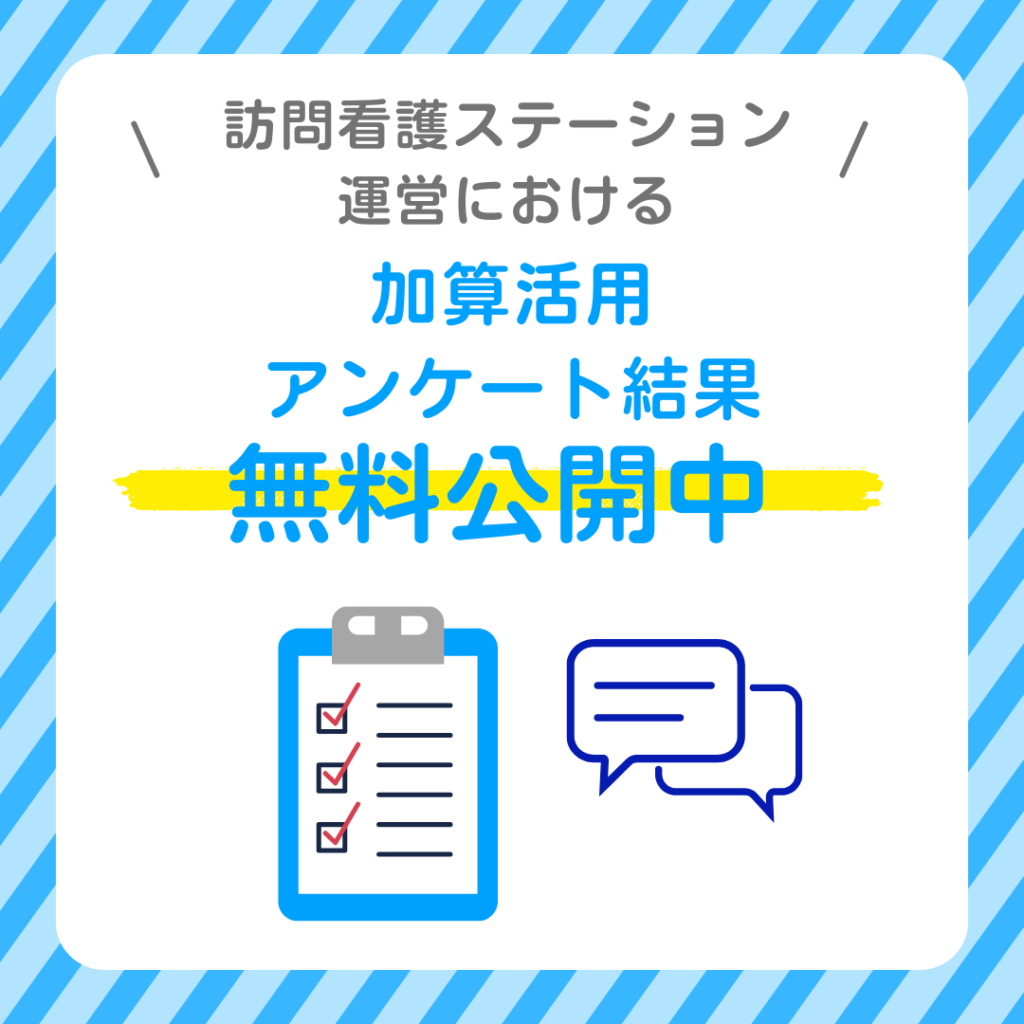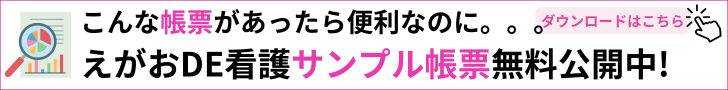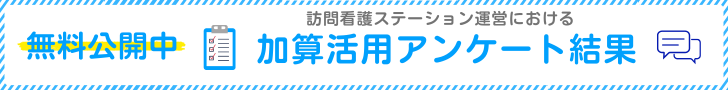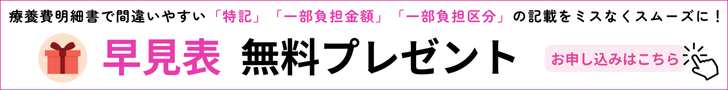栄養アセスメント加算とは?算定で得られるメリット

栄養アセスメント加算は、高齢者の低栄養リスクに対応するため令和3年度に新設された加算です。管理栄養士を中心とした多職種連携による支援体制を評価し、利用者の健康状態改善と質の高いサービス提供を目指します。
加算を取得すると、利用者と施設の双方にメリットが生まれます。
利用者にとってのメリット
- 栄養状態に関する専門的な評価と相談を受けられる
- 食生活の改善に向けた具体的な支援を受けられる
施設にとってのメリット
- 利用者の状態改善
- 加算による収益増
- 多職種連携体制の強化
【2024年度版】栄養アセスメント加算の算定要件と単位数

加算を算定するには、事業所の体制と利用者ごとの両面で要件を満たす必要があります。
算定対象サービスと基本要件
栄養アセスメント加算は、以下の介護サービスで算定が可能です。
| 対象サービス種別 |
| 通所介護(デイサービス) |
| 通所リハビリテーション |
| 地域密着型通所介護 |
| 認知症対応型通所介護 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 |
基本要件として、事業所に管理栄養士を1名以上配置する必要があります。 ただし、外部の医療機関や他の介護事業所、栄養ケア・ステーションなどと連携し、外部の管理栄養士と共同で行う場合でも要件を満たせます。
利用者ごとの算定要件
利用者一人ひとりに対して、以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 栄養アセスメントの実施
- 利用者・家族への結果説明と相談対応
- ケアマネジャーへの情報提供 → 居宅サービス計画への反映
- LIFEへのデータ提出 → 詳細は後述の「LIFE連携」で解説
- PDCAサイクルの実施 → フィードバック活用によるケア改善
算定単位数と月額上限
栄養アセスメント加算の単位数は50単位/月です。
この加算は、利用者1名につき1ヵ月に1回まで算定できます。算定開始後は、おおむね3ヵ月に1回の頻度でアセスメントを行い、利用者の状態に変更があればその都度見直しを行います。
栄養アセスメント加算の具体的な実施手順|記録・帳票作成を効率化する3ステップ
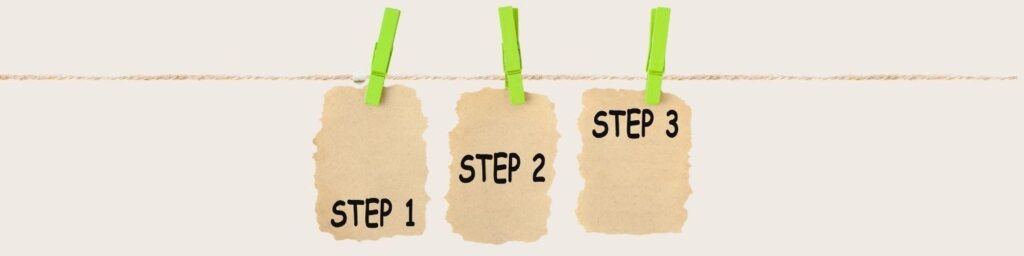
栄養アセスメント加算を算定するための具体的な手順を3つのステップで解説します。記録や帳票作成を効率化する観点も含めて確認しましょう。
ステップ1:利用者情報収集とスクリーニング
最初のステップは、利用者の基本的な情報を収集し、低栄養リスクを把握するスクリーニングです。アセスメントが必要な利用者を的確に判断するために重要な作業となります。
収集すべき基本情報
- 既往歴、服薬状況、認知症の有無
- 食事摂取量や体重の変化(特に体重測定は重要な指標)
スクリーニング項目(低栄養リスクの目安)
【簡易スクリーニングチェックリスト】
- BMI が18.5未満
- 体重測定で3ヶ月に2kg以上の減少
- 血清アルブミン値が3.5g/dl以下
- 食事摂取量が普段の75%以下
- 食事中のむせや食べこぼしが目立つ
💡このうち1つでも該当すれば、詳細なアセスメント対象として検討します。まずはこのシンプルなチェックから始めて、徐々に体制を整えていくのが現実的です。
ステップ2:アセスメント実施と栄養課題特定、栄養ケア計画書作成
スクリーニングでリスクが認められた利用者に対し、より詳細なアセスメントを行い、課題を特定します。
- 管理栄養士が中心となり、生活相談員や看護職員、作業療法士等の多職種が共同でアセスメントを実施します。
- アセスメントでは、スクリーニングで得た情報に加えて、以下のような観点から総合的に評価を行います。
- 摂食・嚥下機能の状態
- 口腔内の健康状態
- 食事への配慮(食事形態、アレルギーの有無など)
- 食生活の状況や嗜好
評価結果に基づく課題を解決するため、個別の栄養ケア計画書を作成します。この計画書が、支援の土台となります。
ステップ3:関係者への情報共有とケアプランへの反映、記録
最後のステップとして、アセスメント結果と計画書の内容を関係者と情報共有し、日々のケアに活かしていきます。
- 作成した栄養ケア計画書の内容について、利用者やその家族にわかりやすく説明し、同意を得る
- 担当のケアマネジャーにアセスメント結果や計画書を情報提供し、居宅サービス計画への反映を依頼
- アセスメントの実施日や内容、情報共有の記録を的確に記録
- 介護ソフト活用により、LIFEへのデータ提出まで一気通貫で処理可能
【費用対効果】栄養アセスメント加算で売上アップ&業務効率化を実現

加算取得は、利用者へのケアの質向上だけでなく、施設の収益改善と業務効率化にも直結します。具体的な収益シミュレーションと、現場の負担を軽減するヒントをご紹介します。
通所リハ(デイケア)における栄養アセスメント加算の収益増加シミュレーション
栄養アセスメント加算の取得が、どの程度の収益増につながるのか、具体的な例で見てみましょう。
例えば、利用登録者が100名の通所リハビリテーション事業所で、そのうち2割にあたる20名が対象となるケースを想定します。
計算例
- 算定: 50単位/回
- 対象利用者数: 20名
- 地域区分が10円/単位の場合の計算例:
- 1ヵ月の収益増: 50単位 × 20名 × 10円/単位 = 10,000円
- 年間の収益増: 10,000円 × 12ヵ月 = 120,000円
年間12万円の収益向上により、車いす用体重計の導入も現実的となり、より正確なアセスメントとケアの質向上に向けた投資が可能になります。
記録・帳票作成の効率化とペーパーレス化のヒント
紙やExcelでの管理は、転記ミスや情報共有の遅れといった課題を生みがちです。加算算定を機に、ICTを活用した業務効率化を検討してみてはいかがでしょうか。
介護ソフトやシステムを導入すると、以下のようなメリットが期待できます。
- 記録・帳票作成の効率化: アセスメント内容を一度入力するだけで、栄養ケア計画書やLIFEへの提出データに自動で反映され、転記作業が不要
- リアルタイムな情報共有: 職員間で利用者の最新情報をいつでも確認でき、ケアの質向上に寄与
- ペーパーレス化の推進: 帳票をデータで一元管理することで、保管スペースの削減や検索性の向上
💡ソフトを導入する際は、自施設の規模やサービス形態に合ったシステムを選ぶことが大切です。サポート体制が充実している会社を選び、無料トライアルやセミナーなどを活用して、使いやすさを十分に検討しましょう。
栄養アセスメント加算とLIFE連携|データ提出の実務と注意点

栄養アセスメント加算の算定には、科学的介護情報システムである「LIFE」へのデータ提出が必須です。ここでは、提出すべき情報項目や頻度、実務上の注意点を解説します。
LIFEへのデータ提出項目と頻度
LIFEへ提出する情報は、アセスメントを行った利用者ごとに必要です。
主な情報項目は以下のとおりです。
- 事業所および利用者の基本情報
- 栄養・口腔機能の評価項目(体重、BMI、食事摂取量、摂食・嚥下の状態 など)
- アセスメントの実施日
- その他厚生労働省が指定する項目
提出の頻度は、アセスメントを実施した月の翌月10日までで、少なくとも3ヵ月に1回提出する必要があります。
LIFEについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
≫【今更きけない】LIFE(科学的介護情報システム)とは?管理者向け 業務負担軽減の実践ガイド
データ提出時の注意点とよくあるミス
LIFEへのデータ提出をスムーズに行うために、いくつかの点に注意しましょう。
よくあるミスとして、入力内容の誤りや提出期限の遅れが挙げられます。特に、複数の利用者のデータを扱う際には、入力ミスが起こりやすいため、ダブルチェック体制を整えることが有効です。
💡提出したデータは、全国のデータと比較・分析されたフィードバックとして事業所に戻ってきます。このフィードバックを職員間で共有し、次のケア計画に活かすPDCAサイクルを回すことが、科学的介護の目的であり、加算の重要な要件です。
栄養アセスメント加算と関連加算:併算定のポイント

栄養アセスメント加算は、他の栄養関連やリハビリ関連の加算との関係性を理解しておくことが重要です。特に関連の深い加算との違いや併算定のルールを整理します。
栄養改善加算との違いと併算定
栄養改善加算と栄養アセスメント加算は、どちらも利用者の栄養状態にアプローチする加算ですが、対象者や目的に違いがあります。
| 栄養アセスメント加算 | 栄養改善加算 | |
| 目的 | 全ての利用者の栄養状態を把握・評価する体制を評価 | 低栄養状態のリスクが高い利用者に対し、具体的な改善サービスを提供することを評価 |
|---|---|---|
| 対象者 | 原則として全ての利用者 | 低栄養状態にある、またはそのリスクが高い利用者 |
| 併算定 | 可能(ただし、同一利用者・同一月の両方算定は不可) | |
基本的な流れは、まず栄養アセスメント加算で広く利用者の状態を把握し、リスクが高い方に栄養改善加算を算定して集中的ケアを行います。
リハビリテーションマネジメント加算との関連
【2024年度改定の重要ポイント】
2024年度の介護報酬改定により、栄養アセスメント加算とリハビリテーションマネジメント加算の併算定はできなくなりました。
栄養状態がリハビリの効果に大きく影響するという事実は変わりありません。むしろ、今回の改定でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件の中に「多職種が連携して栄養アセスメントを行うこと」が含まれることになりました。
そのため、加算の同時取得はできませんが、アセスメントを通じて得た栄情報をリハビリ計画に活かすという、リハビリ専門職と管理栄養士の連携は、これまで以上に重要と言えます。
リハビリテーションマネジメント加算の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参考ください。
≫紙・Excel運用から脱却!リハビリテーションマネジメント加算の業務効率化完全マニュアル【2024年度版】
栄養アセスメント加算に関する現場の疑問を解決!
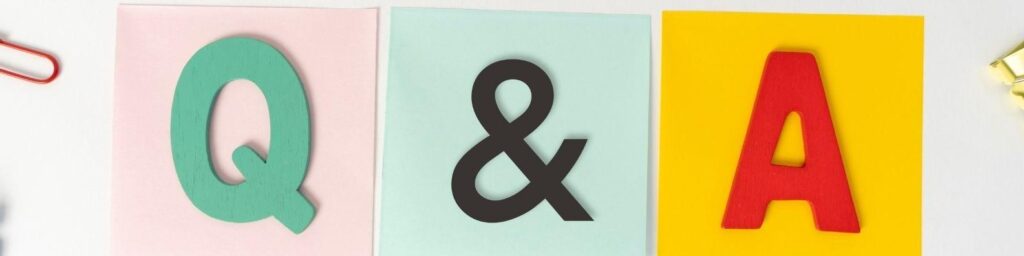
算定前の最終確認に役立つ、よくある質問をまとめました。
Q1:通所リハでは、全利用者に栄養アセスメントの実施が必須ですか?
⇒ いいえ、必須ではありません。本加算はアセスメントを行なった利用者ごとに算定する個別加算です。ただし、施設全体で利用者の栄養リスクを把握する体制が望ましいです。
Q2:栄養アセスメントの実施頻度はどのくらいですか?
⇒ 算定は月1回までです。継続するには、3ヵ月に1回以上のアセスメントと、毎月の体重測定による状態把握が推奨されています。
Q3:栄養ケア計画書の作成は必須ですか?
⇒ 独立した「栄養ケア計画書」の作成は必須ではありません。実務上は、LIFEの様式例を事実上の計画書として活用するのが最も効率的です。
Q4:利用者が複数の事業所を利用している場合、どの事業所が算定するのですか?
⇒ 複数の事業所を利用している場合、ケアマネジャーが調整役となります。サービス担当者会議等で検討の上、算定する事業所を1つに決定し、原則としてその事業所が継続してアセスメントを行います。
(参照:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.10)」)
まとめ:栄養アセスメント加算で、利用者ケアの質向上と施設運営の安定化へ

今回は、2024年度の改定に対応した栄養アセスメント加算の算定要件から具体的な手順、LIFE連携、費用対効果まで解説しました。
本加算への取り組みは、ケアの質向上と施設の収益強化に直結する重要な一手です。
ぜひ、本記事を活用し、算定取得に向けた第一歩を踏み出してください。
最後までお読みくださりありがとうございました。