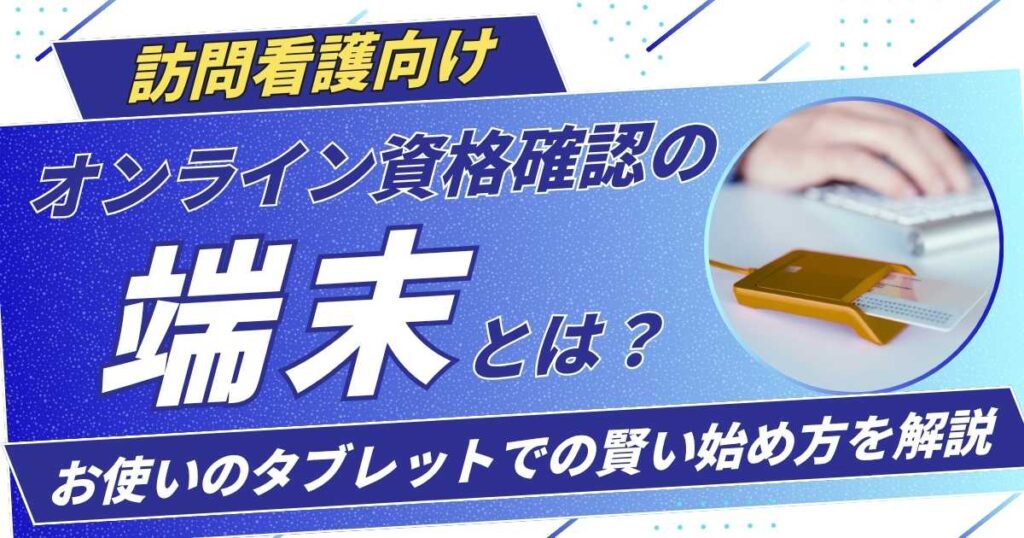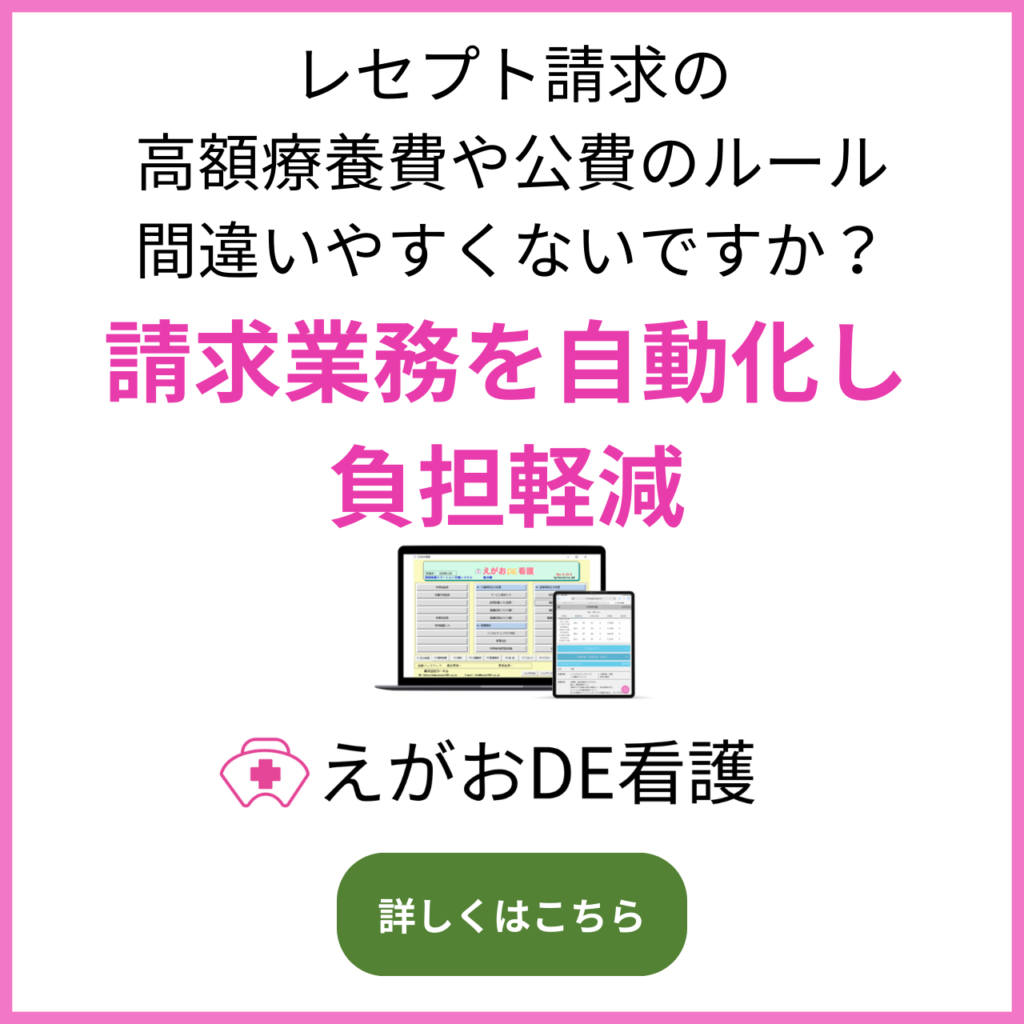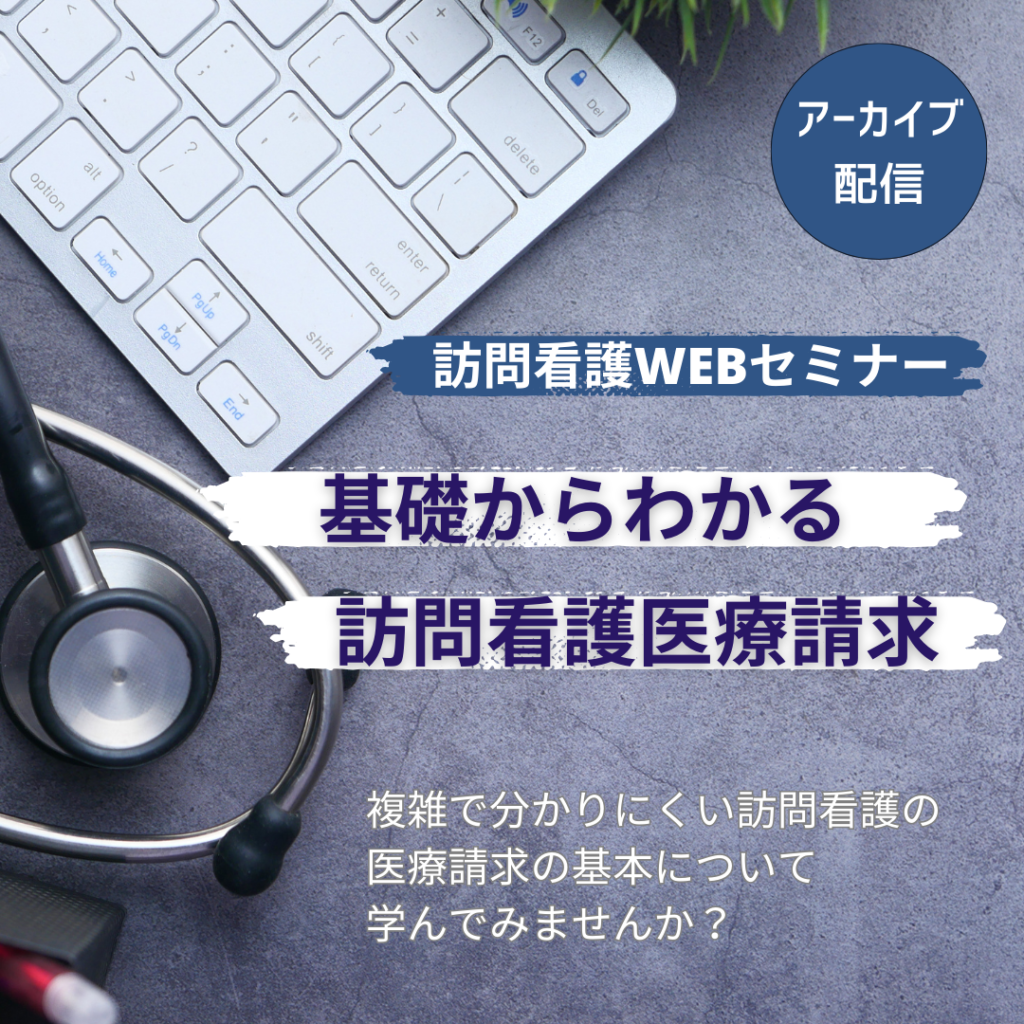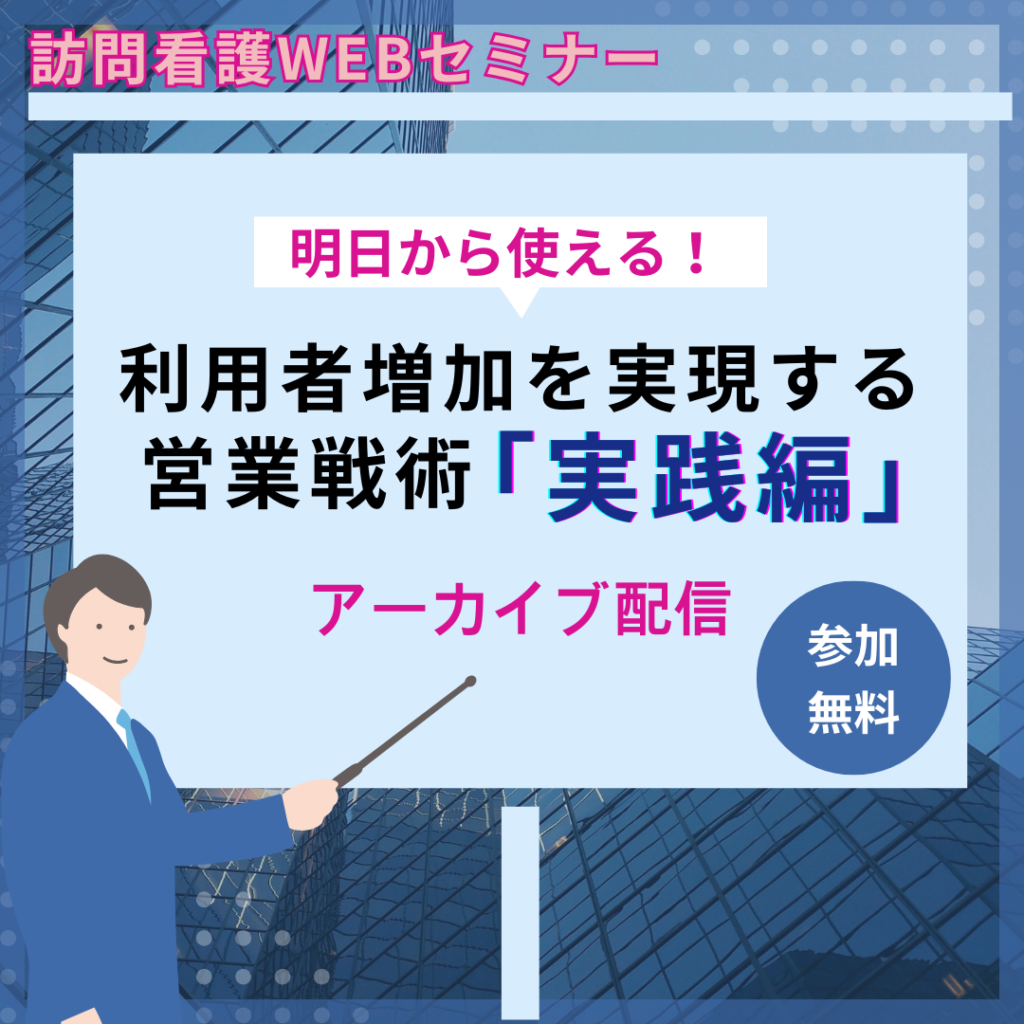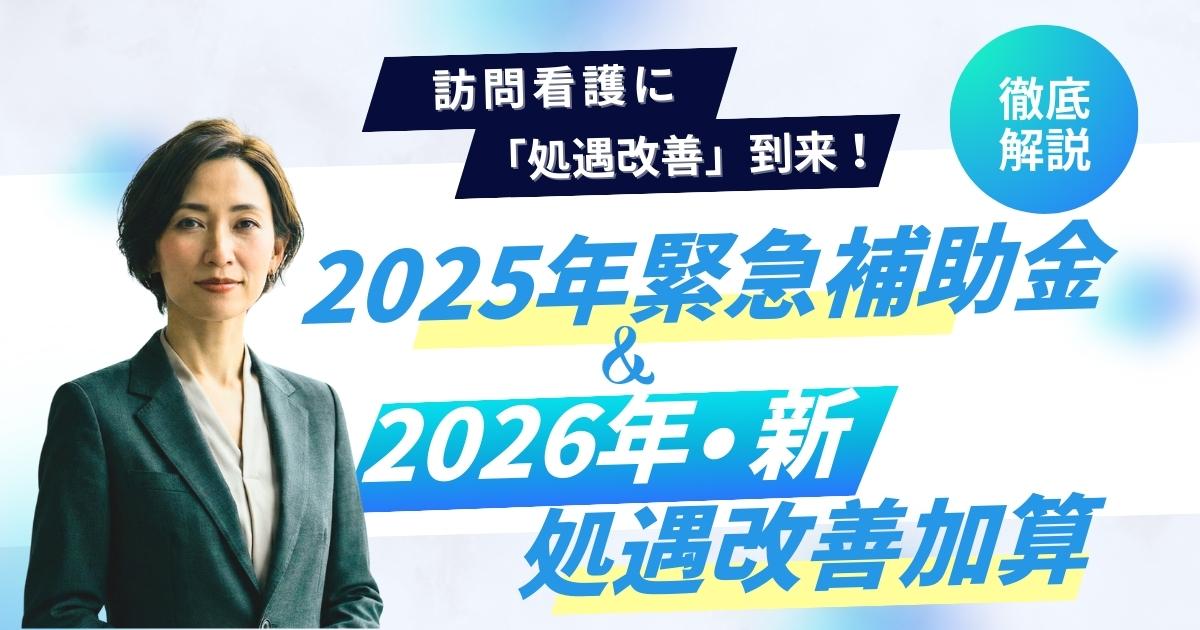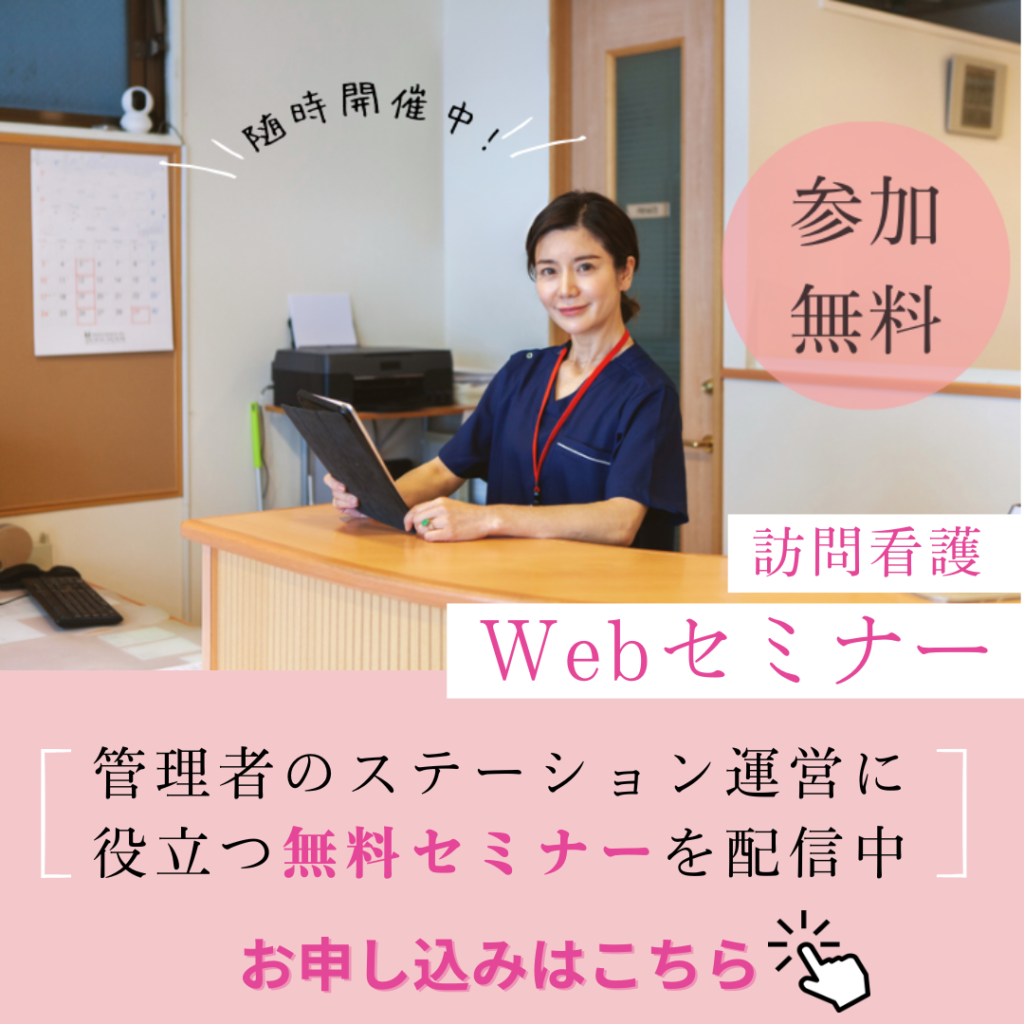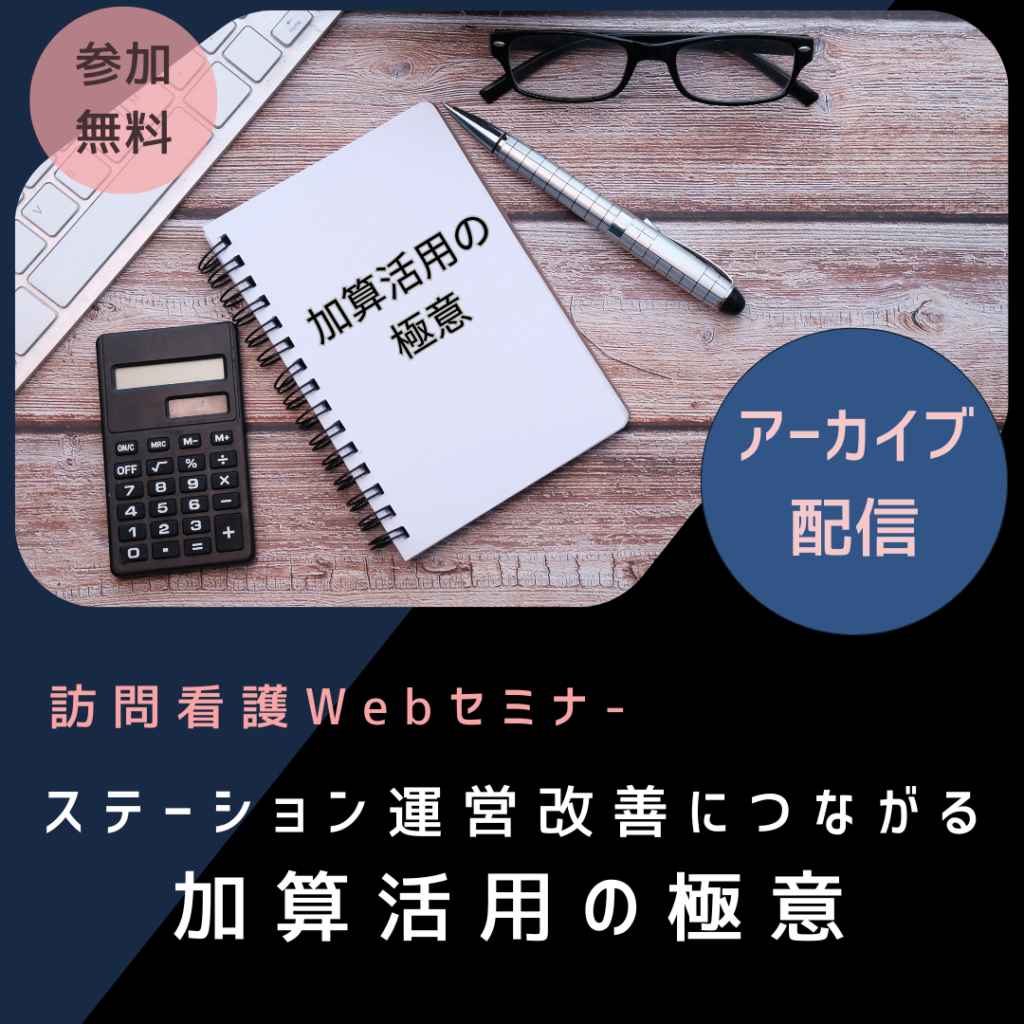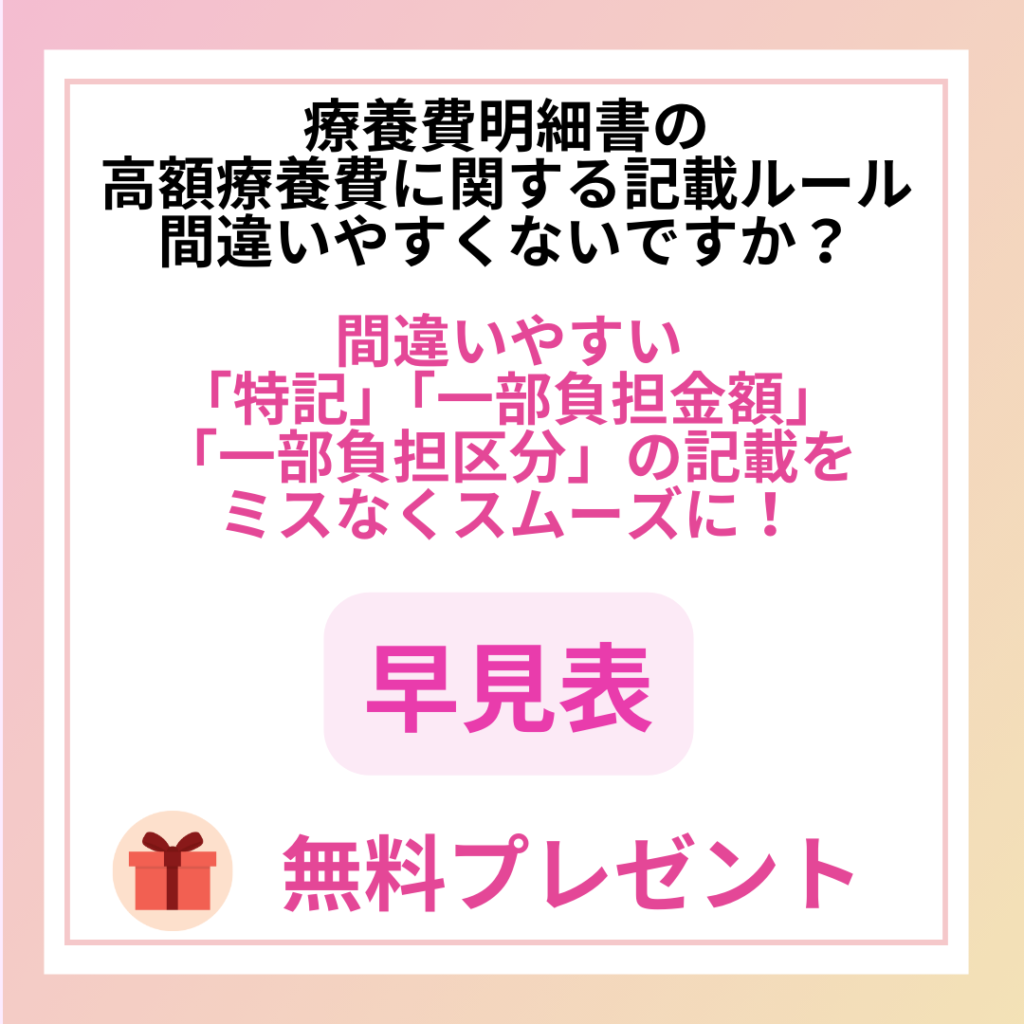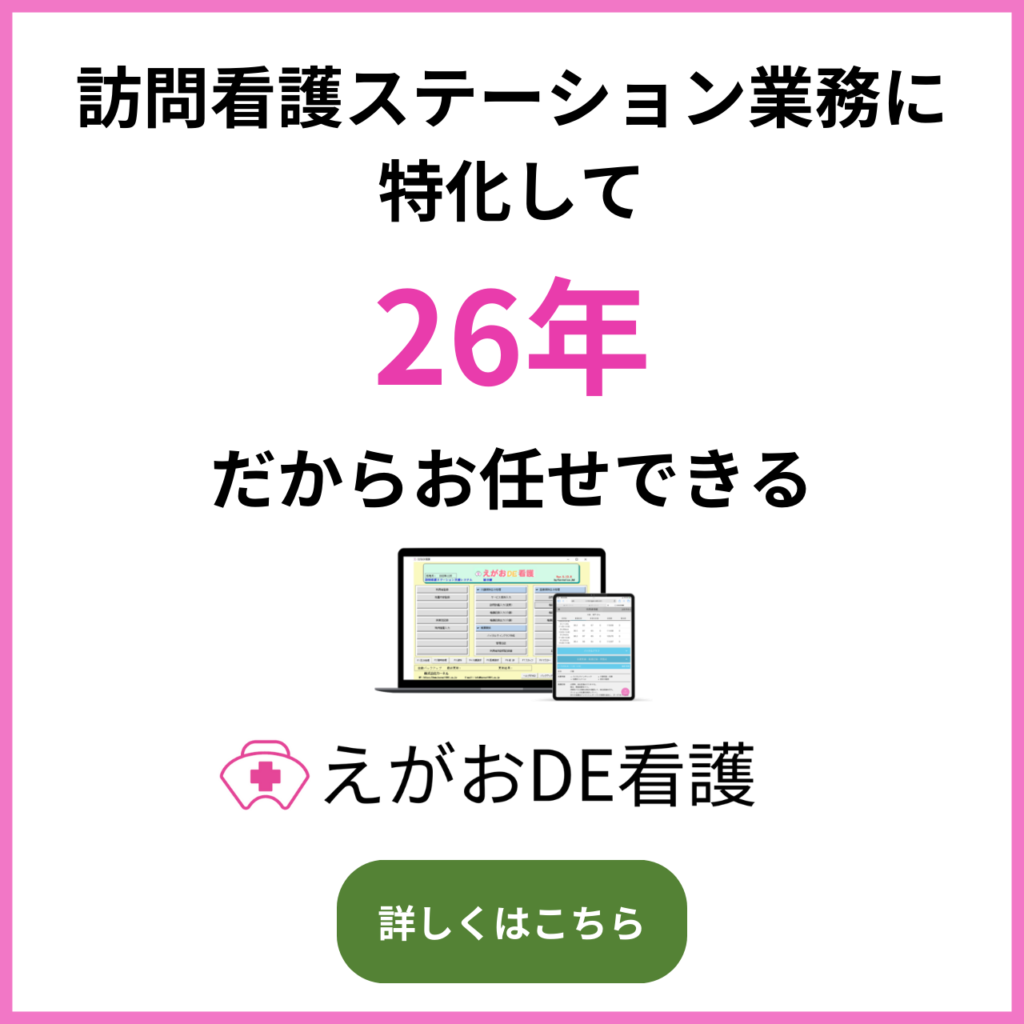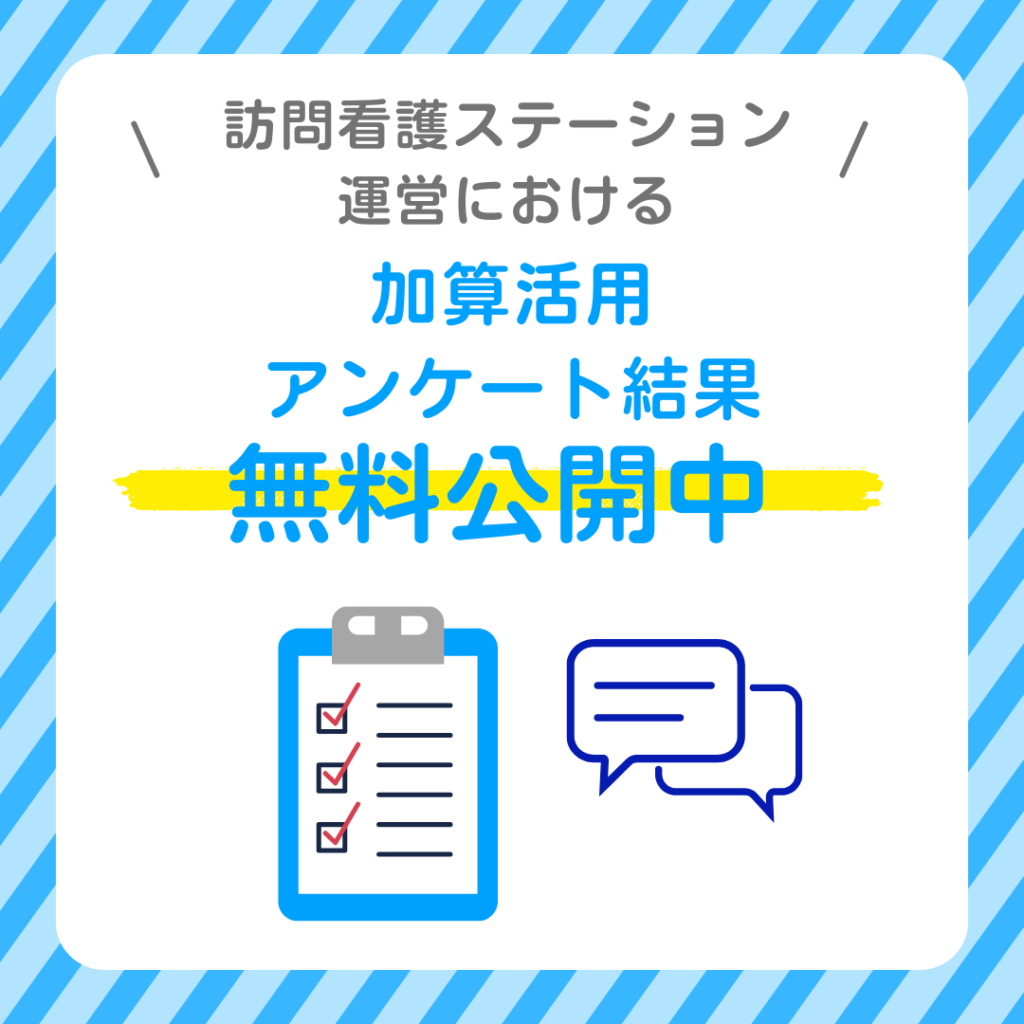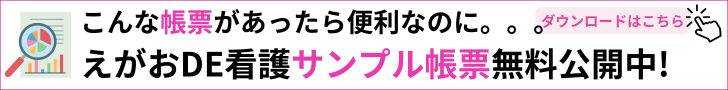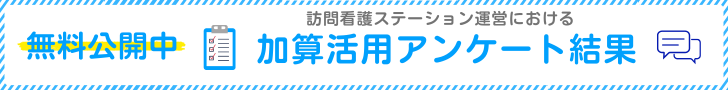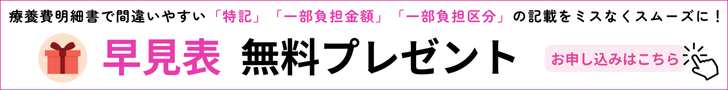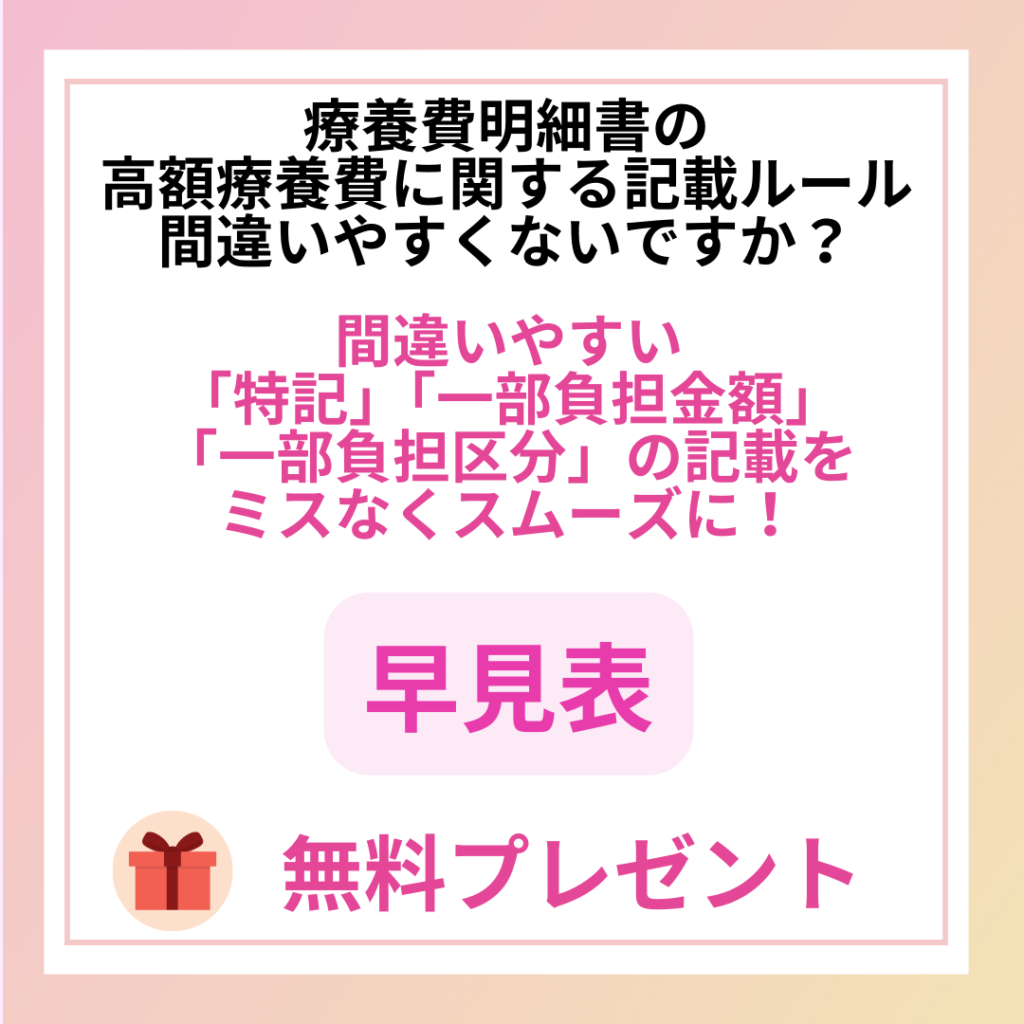訪問看護のオンライン資格確認で使う“端末”とは?3つの選択肢を比較

「オンライン資格確認の端末」には、主に3つの選択肢があります。
必ずしも高価な専用機は必要ありません。それぞれの特徴を知り、ステーションに最適な方法を選びましょう。
選択肢①:スマホ1台で完結「NFC搭載スマートフォン」
NFC機能付きのスマホなら、追加のカードリーダーなしでマイナンバーカードを読み取れます。対応機種をすでにお持ちであれば、新たな機器購入が不要ですぐに始められるのが最大のメリットです。
ただし、画面が小さく操作しづらく感じる場面もあるでしょう。
また、個人スマホを業務利用する場合は、機種の不統一や情報セキュリティなど、管理上の課題も生じます。
選択肢②:慣れた画面で操作「タブレット+ICカードリーダー」
普段お使いのiPadなどに、数千円から購入できる汎用ICカードリーダーを接続して使います。
タブレットにはNFC機能がないためリーダーは必須ですが、大きな画面で操作しやすく、記録から資格確認まで一台で完結します。
使い慣れた端末なので、新しい操作を覚える負担も最小限です。
選択肢③:事業所で使う「PC設置型」
オンライン請求用のPCに、汎用ICカードリーダーを接続して認証します。新たにPCを購入する必要がないため、追加コストはリーダー代のみと最も安価です。
ただし、訪問先では使えず、事業所内での利用に限られます。
3つの選択肢の特徴を、下の表にまとめました。
| 比較項目 | ①NFCスマホ | ②タブレット+リーダー | ③PC設置型 |
| 主な利用場所 | 訪問先・事業所内 | 訪問先・事業所内 | 事業所内 |
|---|---|---|---|
| 携帯性 | ◎(1台で完結) | 〇(2点持ち運び) | × |
| 操作性 | △(画面が小さい) | ◎(画面が大きく見やすい) | 〇 |
| 導入コスト | △(複数台の新規購入なら高額) | 〇(既存タブレット活用ならリーダー代のみ) | ◎(リーダー代のみで最安) |
▼オンライン請求・資格確認の義務化や、補助金の詳細について詳しく知りたい方はこちら
【まだ間に合う!】訪問看護のオンライン請求・オンライン資格確認の義務化 | 対応や補助金申請期限などをわかりやすく解説
小規模ステーションに最適な端末は?管理者目線で考える現実的な選択

3つの選択肢のうち、小規模ステーションにとって最も現実的な端末はどれでしょうか。
日々の運用管理を担う管理者の視点から、選び方のポイントを解説します。
「NFCスマホ」の注意点:端末統一・管理の手間がかかる
NFCスマホは手軽に見えますが、スタッフ全員が対応機種を持つとは限らず、複数台を新規購入すれば高コストです。
また、個人スマホ利用は機種の不統一や、セキュリティ管理の手間が増え、管理者の負担が大きくなります。
なぜ「タブレット+リーダー」が現実的なのか?(コストと運用のバランス)
「タブレット+ICカードリーダー」は、多くの小規模ステーションにとって現実的な選択肢です。
記録用のiPadなどを活用できるため、追加コストは数千円のリーダー代のみ。
使い慣れた端末で操作でき、コストと運用のバランスが最も良い方法です。
手持ちのスマホ・タブレットをオンライン資格確認の端末にするための準備

ここでは、具体的な準備物と、その確認方法、そして費用について解説します。
必須スペック(NFC機能・OS)と確認方法
手持ちの機器が使えるかは、機種やOSで決まります。以下のポイントを確認しましょう。
- スマートフォン
iPhone8以降(iOS 16以上)や多くのおサイフケータイ対応Android機が該当しますが、確実な情報はマイナポータルの公式サイトで対応機種一覧を確認してください。
▶︎マイナポータル「マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください」
- タブレット
iPadなどのタブレットにはNFC機能がないため、ICカードリーダーが必須となります。「マイナ資格確認アプリ」が問題なくインストールできるOSバージョンであれば、基本的に利用可能です。
失敗しないICカードリーダーの選び方【費用と利便性で比較】
訪問看護では、病院の大型端末は使えません。訪問先で使えるマイナンバーカード対応の「汎用ICカードリーダー」を準備します。
リーダーには「有線タイプ」と「無線タイプ」があり、費用と利便性が異なります。予算と使い勝手で選びましょう。
1. とにかくコストを抑えたいなら「有線(USB)タイプ」
- 価格帯: 2,000円~5,000円程度
- メリット: 安価で、充電も不要。コストを最優先するなら最適な選択肢
- 注意点: 訪問時にタブレットで使う場合、ケーブルが煩わしく感じたり、変換アダプタが別途必要になったりすることがある
2. 訪問先での使いやすさを重視するなら「無線(Bluetooth)タイプ」
- 価格帯: 2万円弱
- メリット: コードレスで取り回しが良く、訪問先での操作が非常にスムーズ
- 注意点: 比較的高価で、定期的な充電が必要
⚠️どちらを選ぶ場合でも「拡張APDU対応」の確認を
少し専門的な要件ですが、どちらのタイプを選ぶにせよ、マイナ資格確認アプリで利用するには「拡張APDU」という機能に対応している必要があります。
以下の公式リストに掲載されている製品であれば、この要件を満たしているため安心です。購入前に必ず確認しましょう。
▶︎適合性検証済ICカードリーダライタ一覧(公式リスト)
参考:ポータルサイト「【お知らせ】マイナ資格確認アプリを利用する際に必要な機器について」
よくある質問:「目視確認でOK」の意味とは?
「目視確認」は、単に保険証の顔写真を見るのとは意味が異なります。
マイナ資格確認アプリでは、ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取った後、タブレットの画面に「カード内の顔写真データ」が表示されます。この顔写真データと、「目の前にいる利用者様の顔」が一致していることを看護師が目で見て確認し、アプリ上でチェックを入れる。この一連の操作が「目視確認」です。
この機能があることで、利用者様が暗証番号を忘れてしまった場合でも、スムーズに資格確認を進めることが可能です。
補助金の対象になる機器・ならない機器
国が主体となっていた上限42.9万円の大規模な導入補助金は、ごく一部の例外を除き、基本的に2025年5月31日で申請期限が終了しています。
そのため、今後の導入は自己資金が中心となります。
ただし、自治体によっては独自の支援制度がないか、一度お住まいの地域の情報を調べてみることをお勧めします。
また、今後も新たな国の補助制度の開始も考えられるため、情報をチェックしましょう。
参照:社会保険診療報酬支払基金国民健康保険中央会「オンライン資格確認・訪問看護 – 訪問看護関係補助金の申請について」
オンライン資格確認の端末導入から運用開始までの簡単3ステップ
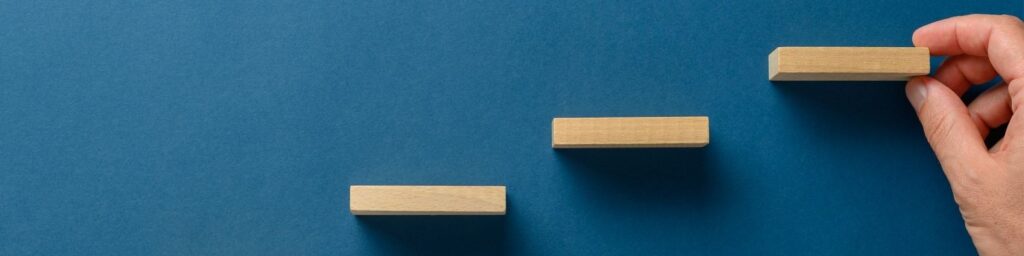
「準備が大変そう」と感じるかもしれませんが、やるべきことは意外とシンプルです。
ここでは、端末の導入から実際の運用開始までを、3つのステップに分けて解説します。
| ステップ | やること | 場所・方法 | ポイント・注意点 |
| ステップ1 | 利用申請 | オンライン資格確認ポータルサイト | すでにオンライン請求の申請が済んでいれば、アカウントは作成済みのはずです。ポータルサイトにログインし、「利用申請」メニューから手続きを進めます。 ▶︎医療機関等向けポータルサイト |
|---|---|---|---|
| ステップ2 | 端末と周辺機器の準備・設定 | 家電量販店やECサイト、App Storeなど | 端末(タブレット等)に「マイナ資格確認アプリ」をインストールし、購入したICカードリーダーを接続・設定します。設定方法はポータルサイトのマニュアルで確認できます。 ▶︎ポータルサイト マニュアル検索ページ |
| ステップ3 | ステーション内での運用ルール作り | ステーション内での話し合い、簡単なマニュアル作成 | 「いつ確認するか(例:月初初回訪問時)」「マイナ保険証がない方の対応」「機器の管理方法」など、簡単なルールを決めておきましょう。スタッフ全員が同じ手順で使えるようにすることが、スムーズな運用の鍵です。 |
iPadがそのままオンライン資格確認の端末になる「えがおDE看護」

ここまで解説してきた「タブレット+リーダー」での運用を、さらにスムーズにする方法を紹介します。
いつもの記録用タブレットで資格確認まで完結
訪問看護ソフト「えがおDE看護」は、お使いのiPadがそのまま資格確認端末になるWEBアプリです。いつもの記録用タブレットに、数千円のICカードリーダーを追加するだけで、すぐにオンライン資格確認を始められます。
記録から資格確認まで一つの流れで完結するため、低コストで、スムーズな導入を実現します。
ICTが苦手な管理者・スタッフでも安心のサポート体制
ICTが苦手な方でも安心して使えるよう、電話やリモート操作による手厚いサポート体制を整えています。
「リーダーの接続がわからない」といった導入時のつまずきも、専門スタッフが丁寧に支援。AIチャ-ットではなく、直接人と話して解決したい管理者様にも安心していただけます。
▼「えがおDE看護」の詳しい機能や料金について知りたい方はこちら
えがおDE看護
まとめ

今回は、訪問看護におけるオンライン資格確認の「端末」について、専用PCがなくても、今あるタブレットと安価なICカードリーダーで始められる現実的な方法を中心に解説しました。
マイナ保険証の利用者がまだ少なく、導入をためらう気持ちもあるかもしれません。しかし、オンライン資格確認は返戻リスクからステーションを守る、賢い”お守り”のようなツールです。
この記事が、日々の業務に追われる管理者様の、はじめの一歩をそっと後押しできれば幸いです。
▼オンライン資格確認もDXの一環。ステーション全体の業務効率化に興味がある方はこちら
訪問看護DX加算50円の価値とは?小規模ステーション管理者が知るべき導入メリットと要件